| ルネサンスをここでは「復古」の意味で用い、「人間ルネサンス」は、教会が消し去った「ギリシャ哲学」を呼び戻し、人が人らしく自由になるということであった。「宗教ルネサンス」とは、その逆で、本当の自由とは「聖母子」信仰によってもたらされるとするものである。なぜ宗教に復古すると言うのか、なぜわざわざ時代遅れのことを言い出すのか。人よ、聖母子は今なお聖なる光の中にあり、時空を越えた存在である。「古い」のは、浅はかな人の知恵によって聖母子を図ろうとしたからであり、その知恵が古くなるのである。 「ヨハネによる福音書」がそれである。根拠のないウソに満ちた、不気味な文書であるのに、哲学者たちは人々にさもありがたいものであるかのように吹聴しているのである。聖書にそれが収められているのは、「キリスト教思想文書」の整理統合作業の編集者に、ローマ教会だけでなくアレキサンドリヤ教会の哲学者がいたからである。「ヨハネによる福音書」がわたしに批判される謂(いわ)れはないが、わたしはそれ自体を批判しているのではなく、人々を実存のマリヤさまから遠ざけるために、「人の知恵にすぎぬ」その文書をさもありがたいものと錯覚させている反教皇の「哲学的教師」たちの「無礼」を指摘しているのである。2022/4/24(推敲) |
||||||||||||||||||||
| 「2022/2/10」の朝、手帳のメモ ふと湧き上がった「マリヤさまに捧げる」・・・ |
||||||||||||||||||||
| 奇跡「処女受胎」の聖母子 カトリック教会のはじまり |
||||||||||||||||||||
| 聖母子の使命、カトリック教会の使命 | ||||||||||||||||||||
| マリヤさまのアロン家の者としての使命の自覚は、自らに生じた「処女受胎」によって誘起された。すなわち、アロン家の者がヘロデに殺害されるのを待たず自決を選んでこの世から消えた。マリヤさまは婚約者がユダ族であることから、もはやアロン家の子を産むことはできず、アロン家存続の望みは絶たれたとの覚悟の日々を過ごされた。だが奇跡が起こった。マリヤさまの全身全霊がもたらす壮絶な祈りの日々の果てに自(みずか)ら妊娠されたのである。 「わたしはアロン家の子を妊娠した」、そのマリヤさまの歓喜はヨセフの歓喜ともなった。マリヤさまから生まれ出た子は予告どおり「男子」であった。御使の言う「恵まれた女」であるマリヤさまは、その時、アロン家の使命を自覚されたのだ。それが聖母子による。「人(イエス)が人の罪を負い、自らの血であがないのとりなしをする」という究極の試みになり、それが見事「苦杯と十字架」として実現したのである。 しかし、それはパウロにはわからなかった。彼は「処女受胎」を無視し、「復活」による栄光のイエスにこだわった。彼の宣教先はローマ帝国内諸都市のユダヤ人であったが、かえって彼はそのユダヤ人から迫害されるはめになった。皇帝に直訴し、危険な冬の航海で難破するが、マルタ島に難を逃れ、ついにローマに立った。しかし、現地のユダヤ人らもまた、彼を受け入れなかった。彼は自分で借りた家に二年間住んだとのおだやかな記述で「使徒行伝」は終わっている。 パウロは眼の持病で苦しみ続けた。もはや新たな旅はおぼつかない。クレオパとルカのカトリック教会が釈放された彼の面倒をみたとするのが妥当であろう。 エルサレム教会もまた「処女受胎」を公に語ることはできなかった。彼らはパウロよりは温厚であり、ユダヤ教との共存を図ったが結局西暦70年のエルサレム陥落すなわち土着のユダヤ人の消滅をもってその活動は終わった。 パウロもエルサレム教会も、キリスト教が「処女受胎」に端を発し、アロン家代々の嗣業(しぎょう)であった「獣に人の罪を移し、その命である血を用いてあがなう」神事を、「人(イエス)に人の罪を移し」ということに昇華させ、個々人の「罪」のあがないに一新(いっしん)したことに思い至らなかった。 |
||||||||||||||||||||
| それを異邦人であるローマ市民に導いたのははからずもローマ軍の将校クレオパであった。彼は、イエス処刑の報に接し、ローマ法廷のイエスの態度と十字架への歩みを伝令者から聞くにつけ、イエスの死の意味を知りたいと思ったのである。そして有能な僕(しもべ)であり、子とも思うルカをユダヤ人の長老と共にエルサレムに派遣した。ここに神意がある。 ルカがエルサレムのかの宿に到着したのは、イエスの処刑から三日目の夕方であった。その時、広間に集まっていた弟子たちにも異変があった。彼らの前にイエスが現れたのだ。彼は驚き惑う弟子たちにイエスの死の意味を語った。その時、異邦人の訪問が告げられたのである。長老とルカが広間に案内されると長髪の人物が入口の立つルカに振り向いた。その顔を見たルカは絶句した、「イエスだ。イエスがここにいる」。だがそれは女性だった。所作やアクセントは同じだが、顔や声は女性のものだった。 それが、「処女受胎」の証拠であることが、あとで判るのだった。そして「処女受胎」こそは、「イエスの死の意味」の最初であり、マリヤさまがアロン家の嗣業(しぎょう)を総括する「イエスによる罪あがない」の使命を認識されることになったのだ。 |
||||||||||||||||||||
| ルカの報告を聞いたクレオパは軍を辞し、エルサレムでルカと合流した。そしてマリヤさまをローマに招聘(しょうへい)した。マリヤさまと奉仕の女性たちそれにペテロたち元漁師はマリヤさまにイエスさまを重ね一行に加わった。軍港カイザリヤから海路アンテオケに向かい、クレオパの私邸で最初の集会を開いた。集会に集(つど)ったのはクレオパの友人や解放奴隷たちであって、婦人たちも多く含まれた。こうしてユダヤ人たちが反発した「究極のアロン家」の話を聞いたのは異邦人であった。彼らは「処女受胎」をルカの証言のゆえに「奇跡」として受け入れた。 | ||||||||||||||||||||
| そして福音はローマを目指した。その一行の先頭には十字架の模型が掲げられていた。ローマに誕生したカトリック教会組織はその最初からピラミッド型であった。そしてそのカトリック教会の使命は、アロン家のマリヤさまとイエスさま、聖母子による「罪のあがない」を伝えることであった。 | ||||||||||||||||||||
| アロン家最後者であるお二人(ふたり)は、神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」に至る個々人の罪のあがないの道を拓かれた。それこそはカトリック教会の護るべきものである。すなわち、旧約では大祭司は死んで交代していたが、大祭司の資格を持つイエスの場合はカトリック教会のある限り続くのである。そこにカトリック教会の使命があるのである。 個人の持つ使命は死んで終わりである。だが組織の場合はそれが続く。クレオパの属したローマ軍は続いたのである。クレオパは教会もまたピラミッド型組織からスタートせねばならぬと考えたのである。 |
||||||||||||||||||||
| 帝国の版図の分割統治の時代に、そのピラミッド型はギリシャ的「智」のエジプトに崩された。アレキサンドリヤの哲学者たちが著した「ヨハネによる福音書」はマリヤさまの名を消し、頭で考えたことでリメークしたのである。だがそれは本来のキリスト教とはかけ離れているが、知識人たちはそれを誇る。「ヨハネによる福音書」を基盤とする東方教会はカトリック教会とは異質である。それは「 ヨハネによる福音書」誕生背景からして、普遍宗教ではなく民族宗教である。 カトリック教会は唯一の普遍教会であり、その使命は「マリヤさま」の名をパンの秘蹟と共に語り続けることなのである。2022/4/24、4/25 |
||||||||||||||||||||
| 「ごりやく」とは神仏を信じ、礼拝の態度に、人智を超えた利益(りえき)があることを言う。それは心身の充実であったり、それに伴う収益の増加であったり、「家内安全(かないあんぜん)」、「交通安全」、「世界平和」であったりするであろう。御利益の祈願は人それぞれであり、その緩(ゆる)さのゆえに「いわしの頭も信心から」と言われたりする。 キリスト教の「ごりやく」とは何であろうか。それがキリスト教を信仰する原点とならねばならぬ。もちろんそれには国民性もあり、「みんながしているからわたしも」、もちろんそれでもかまわない。それに「ごりやく」が伴えばなお結構ということである。 |
||||||||||||||||||||
| キリスト教思想の源流はユダヤ人の「律法」にあり、「罪」とその「あがない」に関する規定があり、それはアロン家代々の務めとされた。実際、その規定が有効に機能したのは、出エジプトにおける荒野の40年間であったろう。幕屋の神殿の周りにヘブル人イスラエルの12部族が宿営して期間であり、離散を防いだのである。だが、世代交代が起こり、モーセの訓練した戦闘員を、ヨシュアが率いてヨルダンを渡って西のパレスチナに侵攻し、領地の配分が完了すると、幕屋の神殿の存在は忘れられた。それが思い出されるのは、バビロン捕囚が終わって荒廃したエルサレムに人々が戻った時である。「ユダヤ人」という部族統合の象徴としての「神殿」が求められたのである。そしてレビ人の棟梁としてのアロン家も思い出されたのである。アロン家は「罪」に関われるお家柄である。 | ||||||||||||||||||||
| だが歴史は激しく変動していた。アレキサンダーがペルシャを滅ぼしたのである。そして彼が若死にし、妻子が暗殺されたため、将軍たちが実力に応じて遺領を割譲した。そして、歴史にその名を残した都市がパレスチナの「アンテオケ」とエジプトの「アレキサンドリヤ」である。前者はギリシャ的エロス、後者は「智」を象徴した。そのアンテオケの王が近くのユダヤ地域を「エロスのギリシャ」風土に変えようと手を伸ばした。 これに反発したレビ族のマタティヤ親子が武力蜂起し、長期間の抵抗を経て、ついにあきらめさせ、自らは王の権力を保持したまま、「大祭司」を名乗った。レビ族はアロン家を援ける「律法」の守護がその嗣業であるから「王」の称号は使えない。これが「ハスモン家」王朝の始めである。「大祭司」が僭称されたが、アロン家も影が薄く、それを覆(くつがえ)すことはできなかった。 ユダヤに、ハスモン家とアロン家の大祭司が存在する時代が100年ほど続いた。ユダヤは事実上の独立国であったが、ローマ軍がギリシャを席巻しパレスチナに侵攻すると、ユダヤは戦火に包まれることになった。ユダヤ人は各地で執拗に武力闘争を続けた。ついにローマ軍はその戦意の支柱がハスモン家の大祭司にあることを知り、改宗のユダヤ人ヘロデを使って、ハスモン家を探らせ、一族を滅ぼした。そして戦功のヘロデをユダヤ人の王とした。ユダヤでの武力闘争はヘロデ王によって沈静化した。 その30数年後、老いたヘロデは「大祭司」が残っていることを知った。それはアロン家であり、神事しかしない家柄なのだが、ヘロデにはその区別はつかない。それでアロン家も始末することになった。マリヤさまが10歳の頃である。 |
||||||||||||||||||||
| だがその計画は洩れた。アロン家の当主は恵まれた資質の少女、「この子が男であったら」と思うほどの子を殺してしまうことを惜(お)しんだ。そして、ベツレヘムから大工仕事にエルサレムに通い、神殿の仕事もしていたヨセフに注目した。彼はただちに、ヨセフの父を祭司の町「エマオ」に呼び、マリヤさまとの婚姻を承諾させた。そして二人をエマオから嗣業地のナザレに疎開させた。二人につけられた従者たちは、アロン家伝来の聖書、巻物を運んだ。そしてアロン家一族は自決した。ここにアロン家はマリヤさまを残して滅んだ。 この後の「大祭司」はアロン家の者ではなく。ヘロデの息のかかった者たちである。イエスの時代のカヤパらもそうである。 |
||||||||||||||||||||
| ナザレでのマリヤさまの嘆きははなはだ大きかった。嘆きの第一は「もう、アロン家の子を産めない」それであった。毎日壮絶な祈りが捧げられた。許婚(いいなずけ)のヨセフと従者たちも、ただマリヤさまを見守り、祈るだけであった。そして、ヘロデが死に、アロン家自決の衝撃が収まったころ、マリヤさま12歳のころ、祈っておられたマリヤさまに、「おめでとう、恵まれた女よ」の声が臨んだのである。 12歳になられたマリヤさまは妊娠された。ヨセフは結婚を急ぎ、結婚披露のためベツレヘムに向かった。その途中、彼らはエマオに立ち寄りエリザベツを訪(たず)ねたのである。マリヤさまはエリザベツにことの次第を打ち明けた。「アロン家の男子が生まれる」、エリザベツはマリヤさまを祝福した。そしてマリヤさまもまた、自身の身に起こったことを感謝して謳(うた)われた。エリザベツはアロン家の者がマリヤさまに与えられることの神意を思った。 エリザベツ自身も老齢ながら妊娠していたからでもあり、マリヤさまに起こった「処女受胎」を信じた。しかし。その秘密は漏れてはならぬことだった。ヨセフの子でなければ、かえって「神を冒涜(ぼうとく)する者」として、母子ともに殺されてしまう。こうして、まず洗礼者となるヨハネが生まれ、ベツレヘム滞在中にイエスがユダ族の子としてお生まれになったのである。 |
||||||||||||||||||||
| そして30年の歳月が流れた。まず、ヨハネが荒野からヨルダン川に現れ、人の罪を洗った。ヨハネの母はアロン家の娘のひとりである。その彼が「罪」を語るのは大目にみられた。そして、ヨハネの名が全土に知れ渡ったころ、イエスが現れた。イエスがヨハネの洗礼を受けられた時、天から声があって「わたしの心にかなう者」と聞こえた。その情景の目撃者はマリヤさまでなくてはなるまい。「心にかなう」の真意は、「人の罪」を負えるということである。その手段はわからないが何と恐ろしくおぞましい言葉であろう。人の霊的汚物が犠牲とされる者の心にからみつくのである。 | ||||||||||||||||||||
| イエスはその年の過越しの祭りに向かって「アロン家」の仕事をスタートされた。弟子を持ったのは「宣教」のためであり、ダビデの位に就いての大臣のイスを与えるためではない。そして、「あなたの罪はゆるされた」を口にした。だがヨハネと違ってイエスはユダ族である。祭司以外は口にしてはならない「罪」を口にし、律法違反の疑惑が生じたのである。そのような異端者は「死罪」に定められなければならない。イエスは「死」に向かって行進していたのである。それを理解しておられたのはマリヤさまのみ。マリヤさまは顔を隠して奉仕の女たちに混じっておられた。 | ||||||||||||||||||||
| そしてついにその時が来た。人が人の罪を負う瞬間が。それを目撃したのは宿屋の息子のマルコである。夜に女はエルサレムの城壁の門を出入することはできないので、マリヤさまはマルコにイエスから目を離さないように頼まれたのである。宿屋を経営しているのはレビ人の女主人であり、マリヤさまは主筋にあたられるのである。宿は「巡礼者」のためのものである。そして、マリヤさまは夜遅く逃げ帰ってきたマルコからイエスのようすを詳しくお聞きになったのである。イエスの異様な苦しみそれこそは「人が人の罪を負った瞬間」であり、「苦杯」と呼ぶことにしよう。イエスの心に「罪」、霊的汚物がからみつき、その不快感はおよそ人智を超えたものであり、イエスから「聖」が隠され、「力」が失せた。「アロン家」の最後の男子であり、大祭司の資格を持つイエスに成就したのである。 そのイエスは次のステップに入ったことを自覚された。マリヤさまもそうである。どうしてイエスの血であがなうのであろう。未明の裁判でイエスの死罪が宣告されたが、大祭司(アロン家ではない)たちは「石打ち」の刑を執行しなかった。彼らはローマの総督に訴え出た。ユダヤ人たちが早朝に裁判を要求したのでどんな一大事が起こったのかと思った総督ピラトだったが、囚人を見て腹が立った。どう見てもイエスが凶暴犯には見えない。ユダヤ人の奴らはわたしにイエスを殺させようとしているのだ。 |
||||||||||||||||||||
| イエスの出身地がガリラヤであると聞いたピラトは祭りのために上京していたヘロデ(二代目)に引き渡した。ヘロデもまたユダヤ人のたくらみを見抜き、おどけて見せて、イエスをピラトに送り返した。ピラトはがっかりしたが、何とかイエスを放免しようとムチ打たせた。ボロボロになったイエスを見ればいかなユダヤ人でもイエスを哀れに思うに違いない。しかし、ユダヤ人たちは哀れむどころか「十字架につけよ」と本音を叫んだのである。 ピラトは次の一手として「祭りの恩赦」をイエスに適用すると宣告した。しかしそれこそはユダヤ人の思う壺であった。ユダヤ人は叫んだ、「バラバを許せ。イエスを十字架につけよ」。それはイエスを投獄せずに即処刑するという実に効率的な始末の仕方である。こうして、バラバの十字架をイエスが担うことになったのである。しかし、ムチによる出血と肉体のダメージで、刑場までの歩みもままならない。 |
||||||||||||||||||||
| マリヤさまと奉仕の女性たちは、イエスの裁判を見守り、刑場までの歩みも見守られた。ピラトが懸念した「騒動」は起こらなかった。イエスは「驚くべき平安」を保っていた。彼の表情は何と穏やかであることだろう。それが十字架にかけられる者の態度とは信じられない。十字架のイエスには平安があった。霊的汚物が悪血と共に流れ出ていく快感は何ともいえない。肉体が引き裂かれる苦痛は、霊的快感によって相殺されているのである。「獣」ではなく「アロン家の者」たる自分が人の「罪」を負い、流す血によって、命である血によって、「罪のあがない」が実現する、その使命の達成感もあったであろう。「母よ、あとはおまかせする」。そして、ムチのダメージのためにイエスは三時間ほどで息絶えた。 | ||||||||||||||||||||
| 「イエス処刑」の伝令が四方に飛んだ。カペナウムの兵営にもその日の遅くに早馬がついた。そして集まった将校に伝令が読まれた。そのあと伝令者は自分の感想を述べた。それは囚人の態度であった。世の常の囚人とは異なり、その表情にはむしろ「安心」が見られ、十字架に至るまでも「従順」であった。それは何かの達成感ゆえであろうと思われたと言うのである。その言葉を聞いた者のひとりにクレオパがいた。そして思った、「イエスの死の意味」それが知りたいと。 | ||||||||||||||||||||
| 彼はルカにそれを伝えた。翌日は安息日でありユダヤ人は旅行できない。イエスの処刑から三日目の朝、ルカは主人の友人である長老を伴い、部下の操縦する馬車でエルサレムに向かった。そしてその日の午後にかの「巡礼者の宿」に着いたのである。イエスの母に面会したいと女主人に伝え、二階の広間にあがると弟子たちがいた。その弟子たちに話をしていた「男」が振り向いたのを見たルカは絶句した、「イエスだ。イエスが生きていた。これは一体」。 | ||||||||||||||||||||
| この時のルカの驚きが、世に「処女受胎」を導くのである。イエスはカペナウムではローマ軍にマークされていた。あのヨセフの子だからであった。だからルカはイエスの顔を良く知っていたのである。しかし、その母の顔を見るのは今が始めてであった。「処女受胎」それこそはイエスがアロン家の者であることを証言できるのである。 | ||||||||||||||||||||
| それこそは、ユダヤ人の「律法」の中に、異邦人の介入した一瞬であった。そして、ルカの報告はクレオパの「機は熟した」とするところとなり、マリヤさまの異邦人への伝道が実現していくのである。それこそは、ローマ教会すなわちカトリック教会の初めであり、神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」に集約され、ミサは連綿と続いてきたのである。 マリヤさまとクレオパの一行はアンテオケから出発し、ローマへへと向かったが、彼らを先導したのは「十字架」であった。「十字架の先導する一行」、極刑のシンボルを掲げたパフォーマンスは、ローマ市民に特段の宣伝効果を発揮した。 だが弊害もあった。十字架はテロリストたちにも利用され政治不安の現況ともなった。これがキリスト教の禁止の原因になるのである。 信徒が増えるにしたがって形成される教会組織は、クレオパが軍人であったことから、自(おの)ずとピラミッド型になった。しかし、エジプトのアレキサンドリヤは、ローマ教会の風下に立つことを嫌った。それは、ローマの版図が東西に分割統治されていたことと、アレキサンドリヤがギリシャ系王朝の都であったことに起因する。彼らは「ギリシャ」を意識する哲学者であった。だから、ローマ教会のあがめる「女と漁師」にがまんならなかったのである。それは、彼らが「苦杯と十字架」による「罪すなわち狂気」のあがないが「哲学」によらないことを理解できなかったからである。また、「ギリシャ哲学」の誇(ほこ)りのゆえに、「理解することを忌避したのである。アロン家の「旧」「新」を理解するなど思いのほかである。 彼らの反ローマ感情は、「ヨハネによる福音書」を著すことで、「ルカによる福音書」によるローマの上に立ったと溜飲を下げたのである。マリヤさまは「イエスの母」としてその名を封印し、「マリヤ」はマグダラの女とラザロの妹のものとした。そして、その「イエスの母」は普通の頼りない女としたのである。「ヨハネによる福音書」しか読み聞かされることがなくなったエジプトの人々は、聖母子をエジプトの女神であったイシス母子に重ねたのである。 その後、四世紀に至ってコンスタンティヌスが皇帝となり、「禁教」そのものを解いたためにキリスト教も表立って活動できることになった。また、キリスト教思想の統合者はローマ司教と定められ、キリスト教思想の文書は整理・統合され「新約聖書」となった。それ以外の文書は皇帝による厳罰を伴う焼却処分となった。「新約聖書」が単独峰なのはそのゆえである。この時、「ヨハネによる福音書」が加えられ、また使徒行伝には「伝道師」ピリポとそれを誘導するステパノが挿入された。文書の選考委員には「エジプト哲学者」たちもいたからである。 コンスタンティヌス帝の死後、キリスト教がローマ神に代わって国教となった。そして、帝国の版図はまたも統治されることになって、東の都はギリシャの漁村ビザンチウムに造成した城塞都市「コンスタンティノープル」になった。ローマから司教が派遣されたが、アレキサンドリヤからも哲学者たちがやってきた。ローマからの司教たちは「ギリシャ哲学」にひれ伏した。コンスタンティノープルは「ヨハネによる福音書」の教義に染まるのであるが、それには御利益(ごりやく)はなく、言葉の彷徨(ほうこう)があるのみである。だが、ミサでもない「壮麗な儀式」に重点をおくご用教会となったので、人々には別にどうのこうのと言う理由はなかったのである。 そういうわけで、「東」の聖母子のほっかむりの「イエスの母」は名前のない不気味な存在である。ただその特徴的なコスチュームは、それが東の女であることを象徴する。シチリヤの聖堂もベネチヤのそれも、そのコスチュームの肖像があり、反教皇を象徴しているのである。「東」は反教皇の元祖であり、権力者のご用教会でいてくれるから、便利に使われるのである。 だが、「東」のそれは、キリスト教の御利益が個々人にではなく、権力者の道具として作用しているのである。キリスト教の真髄は、アロン家の聖母子のもたらした「人の罪」を「アロン家の者」がその身に負い、流した血によってあがなわれることにある。すなわち、自らは消去できない感情、「心の汚物」を消去できること、そして「み心にかなう人」となって「平和がある」に至るその御利益のことであり、それが神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」なのである。 |
||||||||||||||||||||
| それは、カトリック教会が連綿と続けてきたミサにあり、それに集うことが「愚直な信徒」に与えられる一週間の恵みである。ミサでのパン(とぶどう酒)はイエスの身体を記念するものであり、それが哲学ではなく実在したアロン家の母子と弟子たちの「証言」によることを子孫に伝えるのである。「哲学者」の作り話を警戒せよということである。 | ||||||||||||||||||||
| カトリック教会が「愚直さ」と「マリヤさま」とを忘れ、哲学に向かえば、次の3000年を待たずに崩壊への道をたどるであろう。自分の考えを恥ずかしげもなくべらべらしゃべる哲学者がのさばれば、それは早まるであろう。わたしが何とはなしに「キリスト教の説明書」作成に着手し、10年を超える歳月の中で「カトリックの取説」への道を辿(たど)っているのは理由のないことではないと思う。この「取説」は石ころの叫びである。その石ころは「思うがままに」書くことをゆるされていると自認している。2022/4/18 | ||||||||||||||||||||
| 宗教ルネサンスの主題 | ||||||||||||||||||||
| それはもちろん「聖母子」信仰に帰する。「マリヤさま、ペテロ、クレオパ、ルカ」たちから始まったカトリック教会を、ローマ帝国の版図でありながら統治者の違ったエジプトの哲学者たちは、「女と漁師」の教会とあざ笑い、「女」すなわちマリヤさまを聖母の座からひき降ろし、その名を消し去った。 それを文書にしたのが「ヨハネによる福音書」であることはすでに述べた。4世紀に入ってコンスタンティヌスが皇帝に就位、「全ての」宗教はその活動を妨げられないとし、キリスト教は禁教を解かれた。そして、本来キリスト教会のリーダーはローマ司教であることを確認させ、野放しになっていたキリスト教文書を補完修正し、文書を確定させた。すなわちそれ以外の文書は皇帝の「焼却」命令として厳罰を伴なう形で実行された。 しかし、その中には「ヨハネによる福音書」が残ったし、使徒行伝には「ピリポ」の活動を滑り込ませていた。ピリポを導くためにステパノを創出し、違和感を緩和させた。 |
||||||||||||||||||||
| 「ヨハネによる福音書」しか読み聞かされないエジプトの人々は、イエスの母の名前を知らない。聖母子はエジプトでは「女神イシス」母子と認識されたのである。キリスト教が国教となり、ローマ帝国が東西に分割され漁村「ビザンチウム」にコンスタンティノープルが造成され、東都(とうと)となったが同じ東ローマ教会の版図であったエジプトの思想が持ち込まれた。東ローマ帝国ではエジプトと同じく「ヨハネによる福音書」が読まれた。だから東の人々も聖母マリヤには抵抗がある。聖母子像の母の名は「マリヤ」ではないのである。エジプトなら「イシス」を連想するが東都の場合にはそれがない。得体の知れない「女」なのである。 時代が進み、社会構造が「領主と農民」に「商工業者」が加わった。彼らは日照に左右される農業とは違い、いつでも仕事ができ、時間に余裕ができ、富裕者も現れた。彼らは「暇」を知的好奇心で満たそうと考えた。「個人」が意識されるようになった。画家には教会だけではなく、富裕者たちからの注文がはいるようになった。暇人を相手にした「知識人」が登場した。 それまでの教会を中心とした社会の営みもまたそうした社会の構造変化の波をかぶることになった。「子よ、あなたの罪はゆるされた」とする教会は「知識人」たちから軽んじられるようになった。カトリック教会からの注文のこないレオナルド・ダ・ビンチの不満は、彼の「聖母子」の絵画にそのまま反映されている。あわれである。 |
||||||||||||||||||||
| そうした風潮の極みがカトリック教会からの離脱運動であり、彼らが自称するキリスト教会と信者は「プロテスタント」と総称された。教皇と一体と認識される「聖母マリヤ」は、彼らも忌避し、「ヨハネによる福音書」を引用するのをよしとした。だが彼らは聖書第一と言いながら、「ルカによる福音書」は読み飛ばす。都合のいい文章だけが「聖句」なのである。 だが、500年ののち、「取説」を作成しようとする者が現れ、「読んでわかるもの」を作成しようとした。そして、まず4福音書の違いを「ひとつ」にまとめようとした。ところがその製作過程で、彼は「ヨハネによる福音書」は、他と比較できる資格のない、「ウソ文書」と認識するに至った。同時に「ルカによる福音書」こそは、個々人に内在する「狂気」の清算について記したものであると認識に達していた。 |
||||||||||||||||||||
| それは「聖母子」がアロン家の者であり、ユダ族との婚約中の「処女受胎」こそが、イエスをアロン家の者とするのである。イエスは「個々人の狂気という名の罪」を杯に受けて自らに負い、それを十字架であがなうのである。それまではアロン家から選出された大祭司は、牛や羊などの獣に罪を移し、その獣を屠(ほふ)って「罪のあがない」をしたのである。それは実効(じっこう)を伴わない「儀式」であった。大祭司は死ぬから、代々それを繰り返すのがアロン家の嗣業(しぎょう)の意味であった。 | ||||||||||||||||||||
| だがイエスが「苦杯」と「十字架」の道を歩んだことは、肉においてただ一度きりのものであり、霊においてそれは「永遠化」されたのである。それを説き明かされたのは、イエスの死後三日目に弟子たちに現れたイエス、復活のイエスあるいは母のマリヤさまであった。そして、その場に現れたのがカペナウムのローマ軍将校から遣(つか)わされたルカであり、彼は「イエスの母」を見て驚愕(きょうがく)したのである。「イエスが生きていた!」と。それが「顔認証」となり、彼が「処女受胎」を信じた根拠となったのである。そして、ユダ族のヨセフの子と思われていた彼が実はアロン家の者であったと悟るのである。そのアロン家は「ユダヤ教」の律法において、「罪」のあがないに関与できる唯一の家系であると知った。そしてルカは「イエスの死の意味」について書き記し、主人のクレオパに第一報を送るのである。 | ||||||||||||||||||||
| 「ルカによる福音書」は、その報告書であると取説の作成者は考えたが、それは後に「さまざまな話」を簡潔にまとめたものだったのである。さらには、「カペナウムの百卒長」の逸話(いつわ)は、カトリック教会の成立そのものを思わせるにも至った。 人が生まれながらにかかえ苦しみの元である「狂気」、それをあがない解消する手段がイエスの「苦杯と十字架」であり、肉においては一度きりであるが、霊すなわち「信仰」によっては、時代によらず、民族によらず、個々人に及ぶのであり、その宣教と礼拝を担当しているのがカトリック教会なのである。カトリック教会が、そのあがないを説き明かされた聖母マリヤさまを敬い賛美するのは当然なのであり、聖母とイエス・キリストとは、カトリック教会存続の原因であり原動力でなければならぬ。 人が「狂気」から解放された状態こそは、「み心にかなう者」とされる状態なのであり、主なる神からの平和があるのである。人はこれ以外に何を望むことがあろう。人が飢餓、戦争、さまざまな惨禍の環境にあるとしても、「罪あがなわれた」者には平和があるであろう。無意味な「苦しみ」から解放されて、人としての営みができるであろう。 それを可能にできるのが「聖母子」信仰である。この取説はそれを述べようとするが、その全ては「子よ、あなたの罪はゆるされた」に集約されるのである。 「人」から「聖母子」へ回帰する、それが「宗教ルネサンス」の主題である。2022/3/13、3/14、3/21 |
||||||||||||||||||||
| 十字架を先頭に福音はローマへと向かった | ||||||||||||||||||||
| ローマ教会の最初の組織(きょうかい)は元ローマ軍将校クレオパによるものであり、礼拝は神官の姫による儀式がその始めに存在した。ローマに向かう一行を先導したのは「十字架」である。ローマの残酷刑であった十字架を掲げて進む一行に市民の耳目が注がれた。一行の「集会」は、話よりも儀式にその重点が置かれた。それこそは、「子よ、あなたの罪はゆるされた」の原点でなければならない。集会の参加者には驚くべき心の変化が起こり、すなわち個々人それぞれの「わだかまり」が解消し、彼らは心晴々と集会を後(あと)にしたのである。 | ||||||||||||||||||||
| 同時に、その注目度の高さこそは、反ローマ感情の者たちの関心をも引いた。「十字架」は抵抗運動のシンボルともなって、社会不安をあおり、「キリスト教」の禁止やむなしへと至るのである。だが、政治利用の扇動者たちが死ぬと活動は自然と衰えた。 |
||||||||||||||||||||
| 一方、聖母子の教会組織は儀式を基本に帝国に浸透していった。だが、帝国の版図は4世紀のコンスタンティヌス帝までにも分割統治されたいきさつがあり、西がローマ、東はエジプトのアレキサンドリヤが政治の中心であった。東には「古代ギリシャ」からの「智」の誇りがあった。そこには「女と漁師」のローマ教会を見下す感情があり、「ヨハネによる福音書」が著され聖母から「マリヤ」の名が消された。「ヨハネによる福音書」は反ローマ教会の創作あるいは小説文書である。 | ||||||||||||||||||||
| コンスタンティヌス帝の御世となり、東西が一括統治された。キリスト教思想の統合者はローマ司教とされ、文書が整理統合され「新約聖書」となった。それには「ヨハネによる福音書」も含まれ、「使徒行伝」にもピリポとピリポを導くステパノが挿入された。「ヨハネによる福音書」の成立が「使徒行伝」と同時期と錯誤させるためである。 | ||||||||||||||||||||
| ローマ教会すなわちカトリック教会は信徒に聖書を講釈したりはしない。だが反教皇のプロテスタントは「聖書」を第一とし、聖書を読めば司祭を通さなくても神に近づけるとしたのである。そして聖書は神からの賜物とし、全ての文言を「聖」とした。その目的は信徒に「通読」させないように導き、各自の「聖句」を持つように誘(いざな)うことである。信徒が聖書を通読すればさまざまな矛盾が生じる。矛盾に満ちた「ヨハネによる福音書」は変だということになる。「マリヤさまはどうした」ということになる。マリヤさまの名は教皇に直結し、カトリック教会そのものなのである。 | ||||||||||||||||||||
| コンスタンティヌス帝の死後、キリスト教はローマ帝国の国教とされたが、その時の首都は古代ギリシャのさらに東にあった漁村ビザンチウムに造成されたコンスタンティノープルであった。そして帝国の版図は東西に分割統治されることになり、東の都がコンスタンティノープルになった。この時、ローマから司教が派遣されたが、エジプトのアレキサンドリヤからも司教がやってきた。ローマから来た聖職者たちはアレキサンドリヤの「智」の前にひれ伏した。そしてたちまちギリシャ哲学の虜(とりこ)となり聖母の名を忘れ去った。「東」の人々は聖母の名を知らないことがその証明になる。 ギリシャ化した東の帝国の版図はイスラムの神アラーによってついに古代ギリシャの領域までに狭(せば)まり、ついにオスマントルコに息の根を止められた。東のアレキサンドリヤ系教会は「アヤ・ソフィア」聖堂であったが、それはモスクに再利用された。建物の見事さはイスラムも認めたのである。教会はギリシャ正教を名乗り、イスラムの環境に逼塞(ひっそく)した。このコンスタンティノープル陥落の直前にロシア正教が誕生している。オスマン・トルコが第一次世界大戦の敗戦国になるとその版図は分割されギリシャが誕生した。東の教会はアテネに移った。民族名を冠した「正教」はローマ教会とは何の関係もない。単なる冠婚葬祭に重点を置く私的教会である。私的とは、マリヤさまとペテロを根拠なく否定する者との意味である。 カトリック教会への懸念は、神父やシスターたちが聖書を賜物とし、断片的な文言を引用して自らの「智」をしゃべり、聖母の名を忘れ去る兆候である。「智」が離脱のDNAを持つことはプロテスタントと総称する教会の現状を見れば明らかである。(ここでふっと心拍の異常を体感した)合体成長する宇宙の理(ことわり)にさからい、爆発して飛び散り惑星の輪となってただよう岩石に同じである。どうしてそのようなものと和合してよかろうか。2022/4/8 |
||||||||||||||||||||
| ここでわたしたちはカトリック教会の原点、「十字架を先頭にした一行が目指したのはローマ」、そこに視点を戻さなければならない。2022/4/9 律法のアロン家の聖母子、処女受胎、人が人の罪を負う、人の仰ぎ見ることのできる十字架とあがない、異邦人クレオパの信仰とルカによる聖母子の顔認証、復活のイエスはマリヤさま、クレオパの懇請に応えられたマリヤさま、マリヤさま一行を先導するのは「十字架」、カトリック教会組織は最初からピラミッド型・・・・ |
||||||||||||||||||||
| (1)「取説」作成者のキリスト教 | ||||||||||||||||||||
| ふと、大阪市の玉造(たまつくり)にある聖堂に迷い込んだ。たぶんJR(ジェイ・アール)環状線の玉造駅の広告を見て「クリスチャンセンター」に行こうとしたのだと思う。信仰を求めたが仏縁は生まれず、ふらふらした20代後半のことだった。門が開(あ)いていたので、つい入ったのだった。大きな聖堂の前方の片隅で礼拝が行われていた。聖堂内の正面に大きなマリヤさまの肖像画があり、右下に黒っぽいイエスの十字架像があった。「なぜマリヤさまの肖像画がイエスさまの像よりも大きいのだろう」と思ったのだった。それがわたしの「キリスト教」の始まりだった。結局、そこには行かないままに、プロテスタントになったのだった。 だが、結婚相手にも「キリスト教」を求めたものの、家族全体に及ぶ「クリスチャン」にはさまざまな疑問が生じた。そして明快な答えのないまま、なすすべも無く時を過ごしていたが、ふとキリスト教の説明書をWeb上に置くことを始めた。インターネットが社会インフラになりつつあったことが、わたしのその動機を後押(あとお)しした。 当初は、貧しい聖書知識ではあったが、ひるむことなく、その説明に取りかかった。最初は四つある福音書の比較だった。その「比較」には全く意味のないことがわかるのは、それから10年も経(た)ってからのことだった。 それは「ヨハネによる福音書」がエジプトのアレキサンドリヤ教会の書いたもので、3世紀ごろのものであり、帝国の版図が分割統治の影響で「東側」のエジプトの教会組織は「西側」のローマ司教すなわち教皇のピラミッド型組織の枠内に入らなかった。その理由が、アレキサンドリヤはギリシャ由来の「智」を誇るゆえに、「女と漁師」を敬う教皇の風下には立たないという自尊心である。「ヨハネによる福音書」は、マリヤさまの名を「イエスの母」としたほか、イエスをべらべらしゃべる哲学者に貶(おと)めている他、民衆の気をひくためのウソ、たとえばラザロや「水をワインに」を創作しているもので、福音書とは呼べず「小説」なのである。 だから、「ルカによる福音書」と「ヨハネによる福音書」を比較することには意味がなかったのである。キリスト教の土台、深く掘られて届く岩盤は、実に「ルカによる福音書」だった。 マリヤさまの「処女受胎」は、カトリック教会の最初につながるものだった。その奇跡によって「恵まれた女よ」と形容されたマリヤさまは、ユダ族のヨセフと婚約中であったが、アロン家の使命を自覚されたのである。それは成長されたイエスさまにも及んだことであろう。代々のアロン家の務めであった「獣に罪を負わせる」から、禁断の「人に罪を負わせる」ことへの自覚である。 イエスの宣教は1年に満ずして必要十分な期間だった。イエスの目的は「神の国」の宣教ではなかったからである。イエスの言葉は、「罪のあがない」の成就を信じる者にこそ有効なのである。その年の「過越の祭」のためにイエスの行動のすべてが進行して行ったのである。そして、「苦杯と十字架」が成り、「罪という名の狂気」のあがない、「狂気の解消」が成立した。地上からは律法のアロン家は絶えたが、天上(てんじょう)には聖母子のアロン家が、カトリック教会のミサを通して存続している。それがカトリック教会の目的であり、カトリック教会は聖母子を忘れてはならないのである。 それであればこそ、神父の言う、「子よ、あなたの罪はゆるされた」に威力が生じるのである。それが「宗教ルネサンス」の主題となる所以(ゆえん)である。2022/3/6、5/2 |
||||||||||||||||||||
| (2)導かれて今ここに 60歳で定年退職したわたしの辞書からは「未来」という言葉は消えた。ただ次の労働に残された日々を消化するだけだった。62歳の頃、Webに「キリスト教の説明書」をアップし始めた。ただ、クリスチャンなら誰も知っていそうなレベルのもので、1年あれば十分なはずだった。 ところが、そうはならなかった。その作業は延々と「だらだら」と続き、ついに「仕事」と自認するに及んで、消えていた「未来」という文字が浮かび上がった。「こちらへ」と何かにうながされる形の日々となった。 ふと、わたしは「70歳になったら」と思っていた海外旅行を前倒しし、イタリヤに行った。8日間のパック旅行で、ベニス、フィレンツェ、ローマそしてバチカンを訪れた。そして、「物語イタリヤの歴史」を読むに及んで、カトリック教会を見直すことになった。 カトリック教会は、思っていたように、じめじめしたものでなく、からっとした存在であることがわかり、キリシタンが吹っ飛んだ。旅行は続き、ガラ・プラキディア皇妃のラベンナ、聖フランチェスコのアッシジ、またフェデリーコのパレルモ、「使徒行伝」のマルタ島を訪れることにつながった。「見聞を広めよ」、その実行を促(うなが)されたのだと思った。 (3)「聖母子」信仰の眺望に到達 そして12年が経過し、ついに、イエスはアロン家の最後の男子に違いなく、母のマリヤさまはその姫に違いないとの認識に至った。また、御使(みつかい)の言う、「恵まれた女よ、おめでとう、主があなたと共におられます」の言葉こそはマリヤさまの「すぐれた資質」と「教会への業績」をたたえるものだったのだ。すなわち、マリヤさまはイエスとの共同作業で、アロン家の課題であった、「人の罪を獣に移し」を、「人が人の罪を負う」への転換に成功されたのだ。 「獣」には人の罪を負えない、だからその効能は神殿の神事にとどまる。福音書に記されたゲッセマネの園でのイエスの言われた「杯(さかずき)」それこそは、人の罪を、狂気と言えばさらに理解が深まると思うが、イエスの身に注入する手段である。その時は、イエスと共にいた人々のそれ、「霊的汚物」であったろう。だからこそイエスは苦しまれたのである。この「人が人の罪を負う」そのことの実現こそが、アロン家を永遠とならしめるに至るのである。アロン家最後の男子、すなわち自ずと大祭司の資格を持つイエスに実現したことこそは、カトリック教会のミサが続く限りにおいて、「永遠のアロン家」となったのである。 神父の言う、「子よ、あなたの罪はゆるされた」は、まさにそれを端的に表わす言葉である。2022/3/6、5/2 |
||||||||||||||||||||
| (4)カトリック教会の始祖クレオパ そして、それがカトリック教会に結びつくためには、クレオパの信仰とルカによる「イエスとマリヤさまとの顔認証」が不可欠である。生前のイエスとマリヤさまの顔を見ることができたのは彼だけである。それが「処女受胎」に結びつき、イエスの死の意味に到達するのである。すなわち「罪」に関わったイエスはアロン家の者でならぬこと、そして彼がアロン家の者として「大祭司」となるには、彼の他にはアロン家の男子がいないことが条件になる。 そしてアロン家の最後の者としての「使命」と「覚悟」は、獣に人の罪を負わせてその血であがなうというアロン家代々のやり方を一歩進めて、人がすなわちイエスが人の罪を負い自分の血であがなってこそ、その一度きりこそ、永遠のアロン家の役割となるのだ。クレオパはそれを理解した最初の異邦人なのである。 そして彼は、ローマ軍の将校として、「組織」を考えた。「イエスの苦杯と十字架のあがない」その悦ばしき訪れを広め、さらには後世に伝えるには教会という「組織」が必要であり、一人を頂点とするピラミッド型でなくてはならぬ。「共和制」は聞こえはいいが、議論するだけで、何の仕事もしない。 その果実としてカトリック教会がある。カトリック教会はローマ司教すなわち教皇を頂点とするピラミッド型組織である。そして初代教皇がペテロである。マリヤさまの名は、教皇を連想させるほど、カトリック教会のシンボルである。ローマ教会を今に継いでいるカトリック教会の現状が、その最初の姿を継承しているのである。途中からピラミッド型組織になったというようなことはあり得ない。教会の構想はクレオパが主導したが、初代教皇にはペテロを置いた。 (4-1)異邦人への宣教主体 カトリック教会は、異邦人への宣教主体であり、その関わりはマリヤさまと奉仕の女性たち、それにマリヤさまにイエスを見るペテロたちに相違ないのである。なぜなら、マリヤさまの説かれたアロン家最後の「仕事」をユダヤ人たちが受け入れるはずもなく、かえって異邦人のクレオパが理解し、宣教のためにローマに招聘(しょうへい)したからである。 |
||||||||||||||||||||
| (4-2)ユダヤ人への宣教主体 ユダヤ人に対しては、ローマ帝国内の諸都市に住む「離散の者」と、エルサレムを首都とするユダヤに住む「土着の者」があり、パウロは前者に、エルサレム教会は後者に宣教を試みた。だが、双方とも頓挫(とんざ)した。ユダヤ人とってはイエスはユダ族のくせに「罪」に関わろうとした「律法違反者」であり、ローマ法廷では「騒動を起こす者」として処刑された犯罪者にすぎない。とんだ「ダビデの子孫」というわけである。 パウロ パウロは、生前のイエスを知らない。だから、処女受胎などは思いのほかのことであり、栄光のイエスにこだわらざるを得なかった。また、「割礼は律法そのものだから無用」と説いてユダヤ人の激しい怒りに触れて、「殺害」の危険にさらされ、華々しいローマ入城は夢と消え、囚人として護送されたのだった。そしてローマでもユダヤ人の理解は得られず、さびしく日を過ごしたのである。「使徒行伝」最終章 だから、パウロの延長線上にはカトリック教会はない。 エルサレム教会 エルサレム教会は、西暦70年のエルサレム陥落でその拠点を失った。パウロのような過激なことを言わなかったが、パウロには迷惑した。カイザリヤの獄にあったパウロも援けなかった。エルサレム教会の宣教は、土着のユダヤ人には広がらなかった。 そして双方とも「組織」を軽んじた。 |
||||||||||||||||||||
| この気づきを教皇に カトリック教会に聖母マリヤの肖像画が掲げれている根拠を示すようにわたしは促(うなが)されていたのだ。それが満願に達したと思う今、「宗教ルネサンス」の話ができるのだ。キリスト教思想の統合者はコンスタンティヌス帝の御世に、ローマ司教すなわち教皇と定められたのであるから、この気づきを教皇に捧げんとするのは当然である。 |
||||||||||||||||||||
| (5)カペナウムの 「ルカによる福音書」は、単なる「イエスの言行録」ではないとわかった。ローマ教会すなわちカトリック教会の成り立ちが書かれているのである。冒頭の「テオピロ」は匿名(とくめい)であった。だとすれば、その実名がどこかにあるはずだったのである。それに気づくのに10年が必要だった。 その気づきと同時に、「ユダの山里の町」の名前も同様(どうよう)にどこかにその名が書かれていてもおかしくない。アロン家の娘のひとりであるエリザベツの家があり、マリヤさまが訪れられた町、その町の実名がないとは、実に「おかしい」なことだったのである。 はたしてその二つの重要な名前は、「ルカによる福音書」の最終章に置かれた「エマオ村に向かう二人の弟子」のエピソードで明かされていたのである。すなわち「エマオ」こそはその「ユダの山里の町」の名前でなければならない。その場所は、エルサレムに近い。またエルサレムを介して同程度の距離にベツレヘムがある。エマオこそは、祭司の町であり、アロン家の屋敷があり、マリヤさまはその町で育たれたのだ。ヨセフはベツレヘムの出であり、エルサレムで大工(だいく)仕事をしていた。ナザレはマリヤさまの疎開地であり、ヨセフはマリヤさまの守護という任務を与えられたのだ。婚約はマリヤさまの命を守るための緊急避難だった。そのようなイメージが自然に広がった。ナザレはマリヤさまの疎開地にすぎぬ。 一方テオピロの実名は、ふたりの弟子のひとりの名前として明かされている。クレオパという名がそれである。クレオパこそはテオピロであり、イエスにほめられたカペナウムの百卒長である。 町が村になったのは、30年を経(へ)て寂(さび)れたからである。エルサレムに近く、アロン家のあった司祭の町は、アロン家とザカリヤという主(あるじ)を失い、人々が去っていったのである。ザカリヤの家はヨハネが生まれたが、高齢出産のためか、身体に欠損があって祭司の職を継げなかったのである。だから、彼は野の修行者の中に身をおいた。「エマオに向かう二人の弟子」のエピソードは、読者にとって、福音書の最後を飾るには役不足の思いがあったはずである。だが、エマオとクレオパこそは、その最終章を飾るにふさわしい名前だったのである。 「カペナウムの百卒長主従」のエピソードで、軍人が強調されているのは、クレオパの言葉にあるように、組織のピラミッド型である。カトリック教会は今も教皇を頂点とするピラミッド型である。それはクレオパの理念であり、ペテロを初代教皇とするピラミッド型組織としてカトリック教会(ローマ教会)はスタートしているのである。そうでなければ教会が大きく成長することはなかったのである。途中から組織が変更されることはない。その最初からカトリック教会はピラミッド型組織だった、それを「ルカによる福音書」は教えている。そしてイエスのほめ言葉は、クレオパの教会への貢献を顕彰するものである。取説作成に着手し、遅々として進まぬ日々の中で、ふとそう気づかされたのである。それは自分の考えではなく、教えられたのである。 |
||||||||||||||||||||
| (6)父よ、組織を 「子よ、あなたはわたしに何を求めるか」とご下問あらば、こう書くのはその時わたしはこの世のものではないことが考えられるからであるが、「父よ、組織を」と答える。 「イエスはアロン家の者でなければ」、「処女受胎はそのためにこそ」から始めて、「クレオパがローマ教会設立の始祖との認識」に至るまでの気づきの数々は、個人の権利保護が重視される今の時代、「笹倉正義、ささくら まさよし、Sasakura Masayoshi」にこれら著作物(Webページ)の独占的著作権がある。 だから、その独占的著作権は、「まつり」を介して、「ささくら修道会」に引き継がれる。さもないと、自分の立場を弁護しようとする「哲学者」たちが、ばらばらに引用して、別物に変えてしまうだろう。それは歴史を顧みれば明らかであり、「ヨハネによる福音書」を著して聖母マリヤの名「マリヤ」を消し去った、エジプトの「智」のアレキサンドリヤの哲学者たちがその手本である。彼らは「智」を用いてカトリック教会すなわち教皇の上に立とうとしたのである。それはコンスタンティノープル教会にも引き継がれ、ローマ帝国の東側は「ギリシャ哲学」に染まった。 そして東都コンスタンティノープルがイスラムによりイスタンブールとなった今は、プロテスタントに引き継がれている。彼らの信仰も「ヨハネによる福音書」に基づき、聖書を神の賜物とし、部分読みし、信者には聖句を持てと言う。信徒には何の御利益(ごりやく)も無く、哲学者まがいに聖句の「智」を誇る。信徒間に共有できる信仰の一致は何も無い。あわれである。 プロテスタントは反教皇、反聖母マリヤのみで一致する。そして最大の特徴は「分裂」のDNAを持つことである。プロテスタント教会は「牧師」に依存するゆえ、牧師が死ねばそれで終わりである。ピラミッド型組織でないゆえ、何も継がれない。そのプロテスタントとカトリック教会が協調して「キリスト教」を支えようなどとは、どういう理屈から成り立つのか。プロテスタントのおかげでカトリックも聖書に親しむようになったとはあまりに軽率な発想である。カトリックのプロテスタント化であり、分裂に導き、西暦3000年を迎えることはなくなろう。西暦は、こう書くのは「起源」よりもなじみ深いからであるが、カトリック教会の聖母子のゆえである。 それだからこそ、この取説は哲学による混迷ではなく、神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」こそ必要十分であることを人々にわかってもらい、自らに湧き上がる「狂気」をあがなうためにミサに参列することを薦めるのである。それこそは「み心にかなう人々」の集まりとなり、どのような社会環境にもかかわらず、平和があるであろう。それが「父よ、組織を」の必然なのである。2022/2/18、2/19、2/21、5/3 |
||||||||||||||||||||
| (7)たとえ神の子であろうと イエスはユダヤ人として生まれたのだから、たとえ「神の子」であろうと、アロン家の者でなくては「罪」に関わる資格はない。それは「律法」に書かれていることなのだから。そしてそれは「出エジプト」の最中に、神ご自身がモーセに語り、律法として定められたアロン家の嗣業なのだから。 マリヤさまはユダ族と婚約されたのだから、マリヤさまの産まれる子はユダ族となる。だからこそ、アロン家の子が産めなくなったとのマリヤさまの嘆きは大きかった。身も心も揺さぶられる壮絶な祈りが日夜捧げられた。「おめでとう、恵まれた女よ」との御使の声はそうした「絶望」と「希望」の交錯する日々の祈りの果実でもあるかのように、アロン家の姫たる少女に望んだのである。 その声は「男の子を産む」と言った。未婚のそれは本来不倫の果実そのものであり、女を絶望に落とし、気絶させずにはおかぬ恐ろしい言葉である。だが、マリヤさまには「希望」の明かりがともったのである。「どうしてそんなことがありえましょうか」とは、「それがほんとうならどんなにかうれしいことでしょう」との気持ちである。「アロン家の子が産めるのですね」ということなのだから。 |
||||||||||||||||||||
| (8)旧約は「獣」、新約は「イエス」の血 そして「ルカによる福音書」のイエスがクレオパをほめた言葉、「これほどの信仰はイスラエルの中でも見たことがない」とは、クレオパの活動がローマ教会すなわちカトリック教会の「組織造り」において、ユダヤ教を凌(しの)ぐものになることを言っているのである。 すなわち、「人の罪を獣に」はユダヤ人に留(とど)まり、「人の罪を人に」が、ユダヤ人以外の民族、国々に受け入れられ展開されるのである。これによってユダヤ教は「旧約」に留(とど)まり、キリスト教が「新約」となったのである。 キリスト教の御利益(ごりやく)は、「狂気という名の罪」のあがない、すなわち一時的にせよその消去が可能になったことである。その御利益は、いかなる時代、いかなる場所においても、聖母子信仰によって再現される。その宣教組織が、ピラミッド型のローマ教会(今のカトリック教会)だったのであり、神父の高らかに言う、「子よ、あなたの罪はゆるされた」がそれを象徴する。古くはエジプトのアレキサンドリヤの哲学者たち、新しくはルネサンスの「知識人」たちのあざ笑ったそれこそは、キリスト教そのものなのである。 彼らは聖母マリヤを消し去ろうとし、「神の愛」や「永遠の命」などで代用しようとした。しかし、それは「哲学」の「智」にすぎぬ。彼らの祈りを聞き流すのは神ではなく、サタンである。サタンこそは「智」の統合者であり、彼らが神と称するものの正体(しょうたい)である。 「罪」、それは理屈や哲学では除去できぬ。だが、西側のヨーロッパ世界も過去500年にわたって、宗教を偽装した「哲学」、すなわちウソに満ちた「ヨハネによる福音書」をあがめ、汚染され、聖母子を覆い隠し、イエス・キリストを連呼してきた。そこには罪すなわち狂気のあがないに関する気づきを人々に与えるものは何も無かった。今こそ、この「取説」はその厚い雲を払いのけて、聖母子の光を浴びることを薦めようとする。ミサに参列し、「苦杯と十字架」とにより、人れぞれの狂気を消去してもらって、皆、晴々となれるように。ここに、「宗教ルネサンス」を推進する宣教主体設立要望の動機がある。これらを信じられる者たちは幸いである。 「ルカによる福音書」2章 2-14「いと高きところでは、神に栄光があるように、 地の上では、み心にかなう人々に平和があるように」。 「み心にかなう人々」とは、「聖母子」信仰によって「狂気と言う名の罪」から開放された人々であり、具体的にはカトリック教徒である。カトリック教徒もいろいろな思想があろうから、「ささくら修道会」の人々とするなら、この「取説」が彼らの信仰を担保するであろう。 プロテスタントの重んじる、イエスの訓話の数々は、過越(すぎこし)に至る前段あるいは前座である。イエスの訓話や説話がキリスト教なのではない。それらは、釈迦の尊い教えや孔子の論語と比較できるレベルであり、キリスト教と呼べるものではない。ただし無効と言うのではなく、「罪あがなわれた」状態でこそ生きる言葉であろう。2022/2/18、2/19、2/21、3/6、5/3 |
||||||||||||||||||||
| (9) カトリック教会が「聖母子」を忘れ、「哲学」に傾倒していきつつあるのではないか、すなわちプロテスタント化しつつあるのではないか、ということが思わされるので、こういうことがわたしに思い浮かんでいるのではないか、思い浮かばされているのではないか、それがこれを書き留める動機ではないか、それこそはカトリック教会に思いをはせる私の杞憂の源(みなもと)である。 その杞憂は、カトリック教会の没落の未来を憂(うれ)うるためではなく、「聖母子」信仰を鮮明化し、カトリック教会成立の原点に思いをはせることではないか。 それが、「み心にかなう人々」のためになり、彼らに「平和があるため」の基盤にならねばならないのではないか。すなわち、「聖母子」信仰の原点に戻り、人々がカトリック教会に行く気持ちを起こすように、また帰らんがための動機とならねばならないのではないか。こういう湧き上がる思いが杞憂であればそれでよい。 だが、この内に湧き上がる思いは、今仕えているいるはずの方(かた)からの「カトリック教会の軌道修正を 「狂気と言う名の罪」を個々人からその都度解決できる信仰の (10)「狂気」という名の「罪」なれば その「根拠」の出発点は「罪」の解釈である。プロテスタントの言う、「すべての人は罪を犯した。その罪をあがなうために、神の子、イエス・キリストが人の世に来られた」では、まったく何のことかわからない。「よくわかる」という人もあるいはいるので、プロテスタントという受け皿がある。だが、その実態は「哲学」であり、作り話である。信徒は聖書の「言葉の海」を彷徨(ほうこう)させられる。ひどい話である。 この罪の名を「狂気」とすると、視界は一変する。すなわち、すべての人は生まれながらに程度の差はあれ、「狂気」をかかえている。それが全ての人の不幸の原因なのである。それに気づけば、異存のある人は少ないであろう。狂気は自力で制御できない「感情」ゆえに「狂気」なのである。この狂気を一時的にせよ「消去(リセット)」できるようになったことが「聖母子」信仰の霊験新たかな御利益(ごりやく)なのである。 「何だ、それだけか」という人は大勢いるかも知れないが、それこそは人が幸せになれる秘訣の全体である。「子よ、あなたの罪はゆるされた」を言い換えれば、「子よ、あなたの狂気は消去された」であろう。これを聞いた信徒はホッとして教会を出、「み心にかなう」人として、その週を過ごすであろう。プロテスタントと比べれば、その幸せには雲泥の差がある。2022/2/15、5/3 |
||||||||||||||||||||
| (11)ルネサンスは「人」から「聖母子」に回帰 | ||||||||||||||||||||
| ローマ帝国教会は東西分割統治の影響を受けて、ピラミッド型組織を保てず、「西」のカトリック教会(ローマ教会)と「東」のアレキサンドリヤの流れを汲む反聖母子の正教会とに分かれていた。西の版図(はんと)は早々に消え、東の版図は7世紀に台頭(たいとう)したイスラムの侵攻激しく、その版図を「古代ギリシャ地域」までに縮めていた。 11世紀になると、西側のイタリヤとヨーロッパでは商工業者が出現し、城壁で囲った都市を造り、領主と対抗した。彼らは農作業から解放され、中には裕福な者も出て暇を持て余すようになった。十字軍がもたらす東側からの「みやげ」の中には、ギリシャ哲学の本もあった。たとえば、フィレンツェのメディチ家のサロンでは、東の学者が招かれ、ギリシャ哲学の話題にに花が咲いた。 そして、彼ら富裕層の「道楽」が、絵画にも及んだ。それまでの絵師の顧客は、教会だけだったが、個人の注文となると、宗教画にしても注文主の「嗜好(しこう)」に沿うようにせざるをえなくなった。こうして「智」がもてはやされるようになり、わたしが「人間ルネサンス」と呼ぶ時代に突入し、「子よ、あなたの罪はゆるされた」の教会には「智」がないと喧伝する者が現れ、プロテスタント出現の土壌となった。「人間ルネサンス」は、「聖母子」の教会から人々を離脱させる運動であり、人々を教会の無智から救うものであるとする。 だが、その実態は、反教皇運動にすぎず、エジプトのアレキサンドリヤの哲学者の轍(てつ)を踏んでいるだけだったのである。ここで言う、「宗教ルネサンス」とは、「子よ、あなたの罪はゆるされた」のルーツ、「智」ではなく「律法」を基盤として、実際にあったこと、それに関わった人々に思いをはせ、聖母子の「カトリック教会に帰ろう」の行動に導く運動全体である。 それこそは、「み心にかなう人々」に捧げられるものであり、彼らが「平和であるように」とされるためである。それは「罪」よりも「狂気」の方が具体的でわかりやすいし、御子(みこ)の成された「あがない」によって得られるのである。それによって、「智」の与えるものは「彷徨(ほうこう)」にすぎないことが反省されるであろう。2022/2/21、5/3 |
||||||||||||||||||||
| (12)「聖書は |
||||||||||||||||||||
| 「ヨハネによる福音書」ではイエスが何度もエルサレムに上っている。だが、それが無意味であることは、イエスの「目的」を知っていればわかる。だから、著者はイエスの「目的」を知らなかったのである。イエスの目的こそは、「アロン家の者」として、「罪のあがない」の完成であった。それは、罪を獣に移すのではなくて、人、具体的にはアロン家の大祭司自身がその身に負い、自らの血をもってあがないを実現するのである。それによって、個々人の罪、狂気をあがなう、つまり狂気を解消できるのである。それはユダヤ人自身も想定だにできないイエスの宣教の目的だったのである。福音書の読者も、このイエスの目的を知っていないと読み誤(あや)まるのである。部分読みする者には、この話は理解不可能である。2022/2/22 | ||||||||||||||||||||
| (13) |
||||||||||||||||||||
| 本来「キリスト教会」の組織は、キリスト教思想の統合者であるローマ司教の下にピラミッド型であるはずが、歴史的には「禁教下」の時代にも、ローマ帝国の分割統治があったこと、東側統治下には「智」を自認するエジプトのアレキサンドリヤがあって、独自の司教を立てていた。アレキサンドリヤはギリシャ系王朝下に育まれた「ギリシャ哲学」の誉れ高い土地柄であった。4世紀になってコンスタンティヌス帝の御世になって、一旦統一されたものの、その後再び東西に分割された。 東の都はビザンチウムに新たに造成されたコンスタンティノープルに置かれたがそこの司教もローマ教会の枠組みには入らず、アレキサンドリヤ教会の思想を踏襲した。西側教会を「カトリック教会」、東側教会を「正教」と呼ぶが、前者はマリヤさまであり、後者は「イエスの母」であるゆえに、全くの別物である。聖書は神からの賜物ではなく、カトリック教会のために書かれたのである。それをあたかも同じもののように偽装したものが「ヨハネ書」であり、東の者が聖書編纂時に混入したのである。新約聖書はコンスタンティヌス帝の御世(みよ)に成立したが、「ヨハネ書」はそれ以前の分割統治時代に成立していたのである。その時代は、エジプトの人々は「ヨハネによる福音書」しか読み聞かさず、聖母の名は「イエスの母」とのみ読み聞かされたのである。 |
||||||||||||||||||||
| (14) |
||||||||||||||||||||
| ギリシャ正教というのは、コンスタンティノープルがオスマン・トルコに占領され、名がイスタンブールと改められ、聖堂はモスク(イスラムの礼拝堂)に改装された時期の呼称であろう。そのオスマン・トルコ帝国は第一次世界大戦では敗戦国側となったので解体され、トルコ共和国となった。そして、ギリシャが独立を果たした。 それを機に東側教会はギリシャに移り、地域名「ギリシャ」を冠して「ギリシャ正教」としたのである。だから元々ローマ教会とは何の関係もない正体不明のキリスト教会である。 話を「禁教時代」まで戻すが、東西分割統治の時代、東側のエジプトのアレキサンドリヤ教会は、西側の「女と漁師」のローマ司教の風下(かざしも)に立つことをよしとせず、「聖母」からマリヤの名を取り去り去っただけでなく、念を入れて「マリヤ」を「マグダラ」の女と、「ラザロの妹」の名として強調した。 そしてマリヤさまは「イエスの母」に封じ、その母の名は書かなかった。エジプトにはイシス女神(めがみ)の信仰があり、「ヨハネによる福音書」しか読み聞かされなくなったエジプト人にとって、聖母子は女神イシス母子に他ならなかった。それこそはアレキサンドリヤの「哲学者」たちの到達点であった。彼らの思考には律法に記されたアロン家の御利益は思い及ばなかった。 ラザロはウソ 他にも彼らの哲学には知的ウソが平然と使われた。そのひとつに、「ヨハネによる福音書」にのみ登場する「ラザロ」の捏造(ねつぞう)である。ラザロは実在した人物ではなく、哲学者が勝手にラザロをマルタとマリヤの兄としたのである。ラザロの記事はウソであり、福音書を「小説(しょうせつ)」にしたのである。その点では、時代の先駆けというべき業績かも知れない。 「ヨハネによる福音書」11章 11-1さて、ひとりの病人がいた。ラザロといい、マリヤとその姉妹マルタの村ベタニヤの人であった。11-2このマリヤは主に香油をぬり、自分の髪の毛で、主の足をふいた女であって、病気であったのは、彼女の兄弟ラザロであった。11-3姉妹たちは人をイエスのもとにつかわして、「主よ、ただ今、あなたが愛しておられる者が病気をしています」と言わせた。 マルタとマリヤの村事情 ベタニヤ村とは書いてない。マルタとマリヤの姉妹である。 「ルカによる福音書」10章 10-38一同が旅を続けているうちに、イエスがある村へはいられた。するとマルタという名の女がイエスを家に迎え入れた。10-39この女にマリヤという妹がいたが、主の足もとにすわって、御言に聞き入っていた。 マルタとマリヤという名前があるのに、「ある村」の名前がない。そこで最終章の24章を見よう。復活のイエスは弟子たちを「ベタニヤ」の近くまで連れて行っている。このイエスは男装のマリヤさまである。「処女受胎」は、「性」だけが違う二人のイエスを造った。男は「苦杯と十字架」の道を拓き、女は「宣教」を担(にな)ったのである。 「ルカによる福音書」24章 24-50それから、イエスは彼らをベタニヤの近くまで連れて行き、手をあげて彼らを祝福された。24-51祝福しておられるうちに、彼らを離れて、[天にあげられた。]24-52彼らは[イエスを拝し、]非常な喜びをもってエルサレムに帰り、24-53絶えず宮にいて、神をほめたたえていた。 イエスが「天にあげられた」のは、マリヤさまが男装を解き、女に戻られたことの比喩(ひゆ)である。衣装の着替えを担当したのがマルタとマリヤの姉妹であろう。 「ヨハネ」は 次に、「ヨハネによる福音書」の愛弟子(まなでし)は自ずと「ヨハネ」に誘導されるが、文書の中に「洗礼者」を除いてはその名は一度も出てこない。 この弟子とは誰か、ヨハネなのか、それすら明確ではない。「彼のあかしが真実」とは、この文書を作ったものとそれを検証した者がいるということだろうが「わたしたち」とは誰か、それはことごとくぼやかした文書なのである。 「ヨハネによる福音書」21章 21-24これらの事についてあかしをし、またこれらの事を書いたのは、この弟子である。そして彼のあかしが真実であることを、わたしたち(11)は知っている。 主人公は「ピリポ」の怪 一度も出てこない「ヨハネ」に対して、何回も書かれた名前は漁師以外の使徒の名前で、ピリポ、トマス、アンデレであり、最多は「ピリポ」である。だから「ヨハネによる福音書」の名は本当は「ピリポの福音書」なのである。そして著者は文書中の「われわれ」、すなわち「アレキサンドリヤの哲学者たち」なのである。「われわれ」が分業して作った文書であり、通読すれば正体不明の不気味な文書なのである。 イエスは「救い主」ではなく哲学者 |
||||||||||||||||||||
| 「われわれ」はイエスを「苦杯と十字架」による「罪」の解放者ではなく、議論好きの哲学者にしてしまった。哲学こそは、何よりも優位でなければ気がすまぬのである。書き出すのは面倒なので目次(もくじ)を抜粋した。2022/5/4 | ||||||||||||||||||||
| 「ヨハネによる福音書」目次より | ||||||||||||||||||||
| 14章「トマスとピリポ」 哲学(1) ピリポ(12、13)、トマス(2)。わたしたち(7)。14-6イエスは彼に言われた、「わたしは道であり、真理であり、命である。だれでもわたしによらないでは、父のみもとに行くことはできない。なんでもかなえてあげよう。 立て、さあ、ここから出かけて行こう。 |
||||||||||||||||||||
| 15章「ぶどうの木」 哲学(2) 15-1わたしはまことのぶどうの木、わたしの父は農夫である。15-13人がその友のために自分の命を捨てること、これよりも大きな愛はない。 |
||||||||||||||||||||
| 16章「散らされて」 哲学(3) 16-24今までは、あなたがたはわたしの名によって求めたことはなかった。求めなさい、そうすれば、与えられるであろう。そして、あなたがたの喜びが満ちあふれるであろう。 |
||||||||||||||||||||
| 17章「永遠の命」 哲学(4) わたしたち(8、9、10)。17-3永遠の命とは、唯一の、まことの神でいますあなたと、また、あなたがつかわされたイエス・キリストとを知ることであります。 |
||||||||||||||||||||
| 東方教会は「反」教皇のシンボルとなった 東方教会の存在価値は「反」ローマ司教すなわち反教皇である。だから、「東方教会」のシンボルともいえる、「イエスの母の肖像」や建築様式は、権力や富を手にした者で、教皇の風下に立ちたくなかった者たちに歓迎された。たとえば、シチリヤ王のフェデリーコや海洋貿易都市の北イタリヤのベネチヤは、ローマ教会を退け、「東方」教会を招いたのである。 ベネチヤの場合は、御丁寧(ごていねい)に、アレキサンドリヤからマルコの遺体を買い取り、その遺体の上にアラビヤ風の屋根を持つ「サン・マルコ寺院」を建てたのである。アラビヤ風というのは、その時には、アレキサンドリヤを含むエジプト、北アフリカ、スペインはイスラムの版図(はんと)になっていたからである。 「愛」のアウグスティヌス 北アフリカ・ヒッポの司教であった「愛」のアウグスティヌスは「ルカによる福音書」ではなく、「ヨハネによる福音書」を好んだ司祭というよりは哲学者である。彼の著作はカトリック教会にも影響を及ぼし、「聖母子」信仰は、安っぽい「愛」と「智」の暗雲に覆われていったのである。「愛」と「智」の統括者はサタンである。神は聖母子のアロン家の事業に垣間(かいま)見えるのみである。 プロテスタントは「聖書第一」 プロテスタントもまた反教皇であり、「聖書第一」とし、「ヨハネによる福音書」を基盤とする。すなわち、「聖母マリヤ」の無視である。そして、「子よ、あなたの罪はゆるされた」すら、根拠がないとして捨て去ったのである。彼らは聖書第一と言いながら、「読んではいない」、文章を「拾い読み」しているだけなのである。「読めば」、聖書の矛盾に直面する。そんな面倒は「ごめん」なのである。 (15)「取説」が福音書の矛盾を読み解く 「まさよし」は取説作成の目的、「読んでわかる」文書とするために、聖書は通読した。それを読み解く過程で生じた矛盾の意味を考えた。最初はわからなかったが、年月を経ると、教えられることが多くなった。その矛盾の最大の原因が以上に述べた通り「アレキサンドリヤの智」に起因することだったのである。 では、「ヨハネによる福音書」と、それに関連して「使徒行伝」に滑り込ませた、「ピリポ」、「ステパノ」をキリスト教から除外して、「ルカによる福音書」から、キリスト教成立に導いた人々の活動を再現してみよう。 |
||||||||||||||||||||
| そういうわけで 最後にカトリック教会のおさらい 話が長すぎてわけがわからなくなった方のために |
||||||||||||||||||||
| (1)「 ローマから始まった福音(ふくいん)は、帝国内に拡大していった。その教えは「子よ、あなたの罪はゆるされた」に集約された、単純なものであった。その単純さこそはキリスト教が「宗教」である所以(ゆえん)となるのである。そして、その源は、「アロン家」なのである。「罪」に関わることは、律法に記(しる)されたアロン家の嗣業(しぎょう)であるから、罪を口(くち)にするイエスはアロン家の者でなくてはならないのである。 世間的にはイエスはユダ族であったから、ローマ軍と戦うならまだしも、「罪」を口(くち)にすることは、当時のユダヤ人社会では不届きなことだったのである。 だとすると、イエスの母のマリヤさまはアロン家の最期(さいご)の姫さまでなくてはならぬ。マリヤさまは、ユダ族と婚約されていたから、イエスがアロン家の者である唯一の手段は、結果として言えることであるが、「処女受胎」以外にはなかったのである。 その時、生まれ出た子が「女」ではなかったことが不思議でもあるがクローンではなかった証拠でもあるだろう。 また、「処女受胎」の結果として、母子の特徴を考えてみなければならない。そのふたりは、「性」のもたらす違いのほかは、全く同じだったとしなければならぬ。そのことが、ルカによる「顔認証」につながるのである。そしてそのことは30年を遡って起きた「処女受胎」をルカから報告を受け、マリヤさまに会ったクレオパが信じる根拠となったのである。 そのことが、クレオパが疑問とした「イエスの十字架での死」は、ユダ族としてのイエスの挫折ではなく、アロン家の者としての「人」の罪の清算の成就だったことにつながったのである。そこからクレオパが、その話をローマ市民にして下さるように、マリヤさまに懇請したのである。その果実がローマ教会なのである。 なぜ「教会」という組織が必要なのか。クレオパはローマ軍の将校である。彼は皇帝を頂点とするピラミッド型の軍隊組織に身を置いていたのである。どんな優秀な軍人であっても「個人」なら死んでしまえばそれで終わりである。しかし軍隊という組織には永続性がある。だからクレオパにとって、自分が死んだ後(のち)も宣教活動を続けてくれる「組織」が必要だったのである。カトリック教会の組織にはその最初の「原形」が見られるはずである。途中から組織化されピラミッド型になることは考えられない。 そういうわけだから、ローマ教会が、信徒に与える御利益(ごりやく)は、「苦杯と十字架」により「狂気と言う名の罪」があがなわれることなのである。「何だそれだけか」と思わされるほどの単純さこそは、人が人らしく生きられるすべてであり、「み心にかなう人々」を出現させる奇跡であり、彼ら信徒にはいかなる社会環境にもかかわらず「平和」がある。2022/2/23、5/5 |
||||||||||||||||||||
| (2)「 くどいようだが、エジプトのアレキサンドリヤはギリシャ的「智」の王朝があった都で、アレキサンダー大王の将軍のひとり、プトレマイオが興したものでクレオパトラがシーザーの後継者であったオクタビアンとアグリッパ将軍に滅ぼされるまで続いた。その後、7世紀にエジプトがイスラムに占領されるまで、ローマの都市として栄えていた。コンスタンティヌスが皇帝となり、ローマ帝国の統治が一元化されるまで、聖書が成立するまでにも、帝国は大きくは東西に分割統治されていた。 東西の統治者はそれぞれ対等の関係であったことから、教会組織もその影響を受けた。すなわち、東の「智」は西の「女と漁師」の風下に立つことを拒(こば)んだ。すなわち、「女と漁師」の「ルカによる福音書」を拒ばみ、「智」の総力をあげて「ヨハネによる福音書」を創作した。西暦200年ごろの話である。ふたつの福音書のタイムラグは100年以上あり、著者である「われわれ」たちは、イエスはおろかマリヤさまや女性たち、それにペテロやクレオパ、ルカなどとの面識は無いのである。 アレキサンドリヤ教会の「われわれ」たちは、イエスがアロン家の者とか、そのための「処女受胎」とかの面倒なことには関わらず、「智」を用いて新たな福音書としたのである。 マリヤさまは「教皇」とひとつであるであると考えた彼らは、マリヤさまを「イエスの母」に封じた。それをごまかすために愛弟子(まなでし)の名を明かさず、読者が勝手にその名は「ヨハネ」とすることを是(ぜ)とした。 ラザロは実在しないウソの人物である。 主人公は「ギリシャ人」であるとするための、ピリポ、トマス、アンデレの連呼である。 「水をぶどう酒」にと、ラザロの復活の奇跡は読者の気を引くためのウソである。 マグダラの女と、ラザロの妹のマリヤを連呼して「マリヤ」の名をその二人に封じた。 イエスは哲学を問わず語りする哲学者にした。男が自分の成したことをべらべらしゃべるだろうか、そんな男はペテン師と相場が決まっているのである。イエスの成したことを説き明かされるのは「復活のイエス」であるマリヤさまでなければならない。それを可能にしたのは唯一「処女受胎」の奇跡である。 「 ヨハネによる福音書」を小説とするならそれでよい。だが、福音書とすることに問題がある。 2022/2/23、2022/5/5 |
||||||||||||||||||||
| (3)「西」は罪の解消の ①罪とアロン家 御利益というのには「具体性」がある。「罪」というと旧約聖書の「神にそむく行為」を連想するが、それだと具体性はない。具体性がなく漠然としたものには御利益はない。「罪」を「狂気」とし、「個々人の内に湧き上がる抑えがたい異常な感情」とすると、確かにそれは人がそれぞれに生まれながらに持つものと言えるだろう。神にそむく感情もそれに含まれるだろう。 それを自ら振り払って解消することができないゆえに「狂気」なのである。努力や修行でも哲学でも、また酒で紛らわそうとしても後(あと)には空しさがこみ上げるので深酒になってゆく。薬物に手を出せば破滅である。 それを解決する唯一の手段が「イエスの十字架」なのである。これは省略しすぎているが、補足すると、「苦杯と十字架」による罪のあがない、すなわち解消なのである。「苦杯」がキーワードである。この意味がわからないと、「イエスの十字架」には効力が伴わない。もっと言うと、何度も言っているはずだが、イエスが罪に関わるにはイエスが律法のアロン家の唯一の後継者でなければならぬということであるが、そのためには母のマリヤさまがアロン家唯一の生き残りでなければならず、結果として「処女受胎」の奇跡によってそれ、すなわちイエスが唯一のアロン家の者となったのである。御利益を得るためにはまず「処女受胎」の奇跡を信じなければならぬが、その理解を後押しするのが「処女受胎」を福音書に書いたルカによる「顔認証」の可能性である。 ②カトリック教会は西側 ルカはカペナウムの「百卒長と僕(しもべ)」のエピソードの僕であり、カペナウムはマリヤさまとイエスの家族のあった町であり、ルカはヨセフの子ということからローマ軍にマークされていたのである。百卒長の名はクレオパである。彼こそはカトリック教会設立の立役者である。それはカトリック教会が教皇を頂点とするピラミッド型組織であることから納得できるのである。共和制のようなものでスタートしていたら、とっくに霧散している。途中から共和制から独裁制になったわけでもない。 繰り返しになるので以降は省くが、「処女受胎」の奇跡は「想像力豊かな者、信仰篤(あつ)き者」には信じられるのである。結論を言うと、西方教会すなわちカトリック教会にはイエスによる「苦杯と十字架」を信じる者にそのあがないが具体的に御利益として臨むのである。 ③東側の「正教会」は 一方、東方教会、すなわちアレキサンドリヤから始まって、コンスタンティノープル、そしてフェデリーコ時代のシチリヤ、商人支配時代のベネチヤらがそれであり、プロテスタントもそれに含まれる。共通しているのは「反女と漁師」すなわち「反教皇」である。 彼らは哲学的「智」と「愛」を連発し、「ヨハネによる福音書」を部分読みする。通読するとさまざまな「矛盾」に行き当たり面倒だからである。哲学者は、面倒なことの解消には「仕事」に通じるものがあり、忌避する。自分の世界、思考にひたることこそ、哲学者の本懐(ほんかい)である。 ラザロが死の世界から復活し、そのラザロの命をユダヤ人が狙うというのは、まさに読者の好奇心を満足させたい「小説」であり、ウソであるから福音書の価値はなにもない。 ④なぜ東西の違いが生まれたか 東西の違いは「ルカによる福音書」の100余年後に著された「ヨハネによる福音書」によって現れた。どうしてピラミッド型組織であるはずのローマ教会に「違い」が生まれたのかは、「分割統治」時代があったことによる。すなわち、「違い」をもたらしたのは「東」の「智」という傲慢(ごうまん)である。その智は当時エジプトのアレキサンドリヤに存在した。 智は「女と漁師」の教えをあざ笑った。そして、自らの「智」を駆使して文書を作成したが、分業したため、つじつまの合わないものである。主人公は「女と漁師」を退け、ピリポ、トマス、アンデレをギリシャ語の弟子として採用した。少なくとも彼らは漁師ではないと信じられている。 その後(ご)、コンスタンティヌスが皇帝の座につき帝国の東西の版図は統一され、その時代に新約聖書が成立した。その文書選定と整理の作業には東側の者も参加していた。そのため、「ヨハネによる福音書」を筆頭とする「ヨハネ文書」が存在し、「使徒行伝」にもピリポと彼を導くためのステパノの安っぽいエピソードの混入を許したのである。単なる「智」に関しては、西は東に及ばない。 |
||||||||||||||||||||
| (4)アロン家の昇華としての聖母子 ユダ族と婚約中であったアロン家最後の姫は、恵まれた女であって「処女受胎」の奇跡により、イエスを産んだ。イエスはアロン家最後の男子であり、「大祭司」を名乗る資格があった。母子の使命は、人の罪を人が負い、その血で罪をあがなうことであった。だが、その手段はいつ示されるのか。「智」を用いずにそれは成されねばならない。 女が十字架に架かることはできない。男が自分の成したことをべらべらしゃべることはない。そのような男はペテン師と相場が決まっているのだから。してみると、失礼ながら、「ヨハネによる福音書」のイエスとされる者はペテン師である。それは著者の「われわれ」が「智」を用いて考えたことなのである。御利益(ごりやく)などは何もない。 |
||||||||||||||||||||
| ①「律法とイエス」 「罪」のあがないは「アロン家」の嗣業(しぎょう)である。イエスが「罪」を口にするには、アロン家の者でなくてはならない。だが、彼はユダ族でヨセフの子、ダビデの子孫として知られていた。だから、彼にはローマ軍を追い払う「王者」を期待した。イエスが「あなたの罪はゆるされた」と言うことは民衆を失望させた。そして、大祭司たちには「律法違反の者」と認定された。 |
||||||||||||||||||||
| ②「罪」を負わせたものは | ||||||||||||||||||||
| 【旧約】「旧約」では代々のアロン家において獣(けもの)が使われた。これは人が使われたことが成就したので、旧約となったのである。しかし、ユダヤ人には受け入れられない。 | ||||||||||||||||||||
| 【新約】「処女受胎」で生まれたイエスが、「苦杯」を耐え忍び、罪をその身に負った。そして、ムチ打たれ、十字架に架けられ、体内に注入された「罪」のあがないのとりなしをした。このアロン家最後の大祭司が人の罪を負い、その血によって「罪」のあがないのとりなしは、一回で完了した。すなわち獣の場合のように、毎年する必要はなくなった。これが「新約」である。そして、この新約は、ユダヤ人ではなく、クレオパの信仰により、異邦人すなわち「世界の人々」のものとなったのである。 | ||||||||||||||||||||
| ③「処女受胎(1)」 「母の血筋が子に」・・・・イエスがアロン家の者の根拠 | ||||||||||||||||||||
| ヘロデの世に、アロン家に災難が降ってかかった。すなわち、老ヘロデ王による大祭司一族の殺害である。ヘロデは改宗のユダヤ人であったが、若い頃にローマ軍による「ハスモン家」の皆殺しに加担している。その功によりヘロデはユダヤ人の王になれたのである。 ハスモン家は「王」の身分であったが、その階位を「大祭司」としていた。始祖のマタティヤが祭司の身分であったからである。権力を手にした彼の子は、主家の階位である「大祭司」を僭称(せんしょう)したのである。そしてその王朝の名を「ハスモン」としていた。 ヘロデは、その老いた時に、大祭司がまだいることを知った。アロン家である。この情報は漏れて、アロン家で大祭司の身分を持つ父は、娘のマリヤを生かそうと考えた。マリヤは「恵まれた」女であった。必ずやアロン家のためになることをやってのけるだろうと父は考えた。そこで急遽、宮に出入りしていたユダ族の青年ヨセフとの婚約を調(ととの)え、念を入れてエマオから遥か遠方のナザレに疎開させたのである。 そして、付き人にはアロン家の至宝である「聖書」全巻を「婚礼調度品」として運ばせたのである。しかし、ユダ族との結婚すれば、自分の命は助かるが、自分の産む子はアロン家の者ではなくなる。その思いが少女の負担となり、壮絶な祈りの日々が延々と続くことになった。ヨセフもただ先祖の神に祈るしかなかった。 そうしたある日、「おめでとう恵まれた女よ」の声が少女に臨んだのである。現れた御使(みつかい)による受胎告知、そしてその果実「処女受胎」こそは、生まれる子がアロン家の者であることの証(あか)しなのだ。アロン家のあったエマオで伯母(おば)のエリザベツに会った少女が歌った、「わたしを幸いな女と言うでしょう」こそは、マリヤさまには望外の、「アロン家の子」誕生を思っての感謝を示して余りある。 「ルカによる福音書」1章 望外の感謝 1-48この卑しい女をさえ、心にかけてくださいました。今からのち代々の人々は、わたしをさいわいな女と言うでしょう。1-49力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったからです。 「卑しい女」は、マリヤさまが主に対してへりくだっておられる言葉である。マリヤさまの身分はアロン家の姫である。普通に考えたら「処女受胎」は姦淫の証拠に他ならず、公開の「石打の刑」が臨むのであり、その恐ろしさに気絶してしまうのである。「処女受胎」などあってはならぬのである。この点でもマリヤさまがいかに恵まれた女であられたかが分かるのである。 |
||||||||||||||||||||
| ④その手段は「 |
||||||||||||||||||||
| 「人が罪を負う」手段は「苦杯」としてゲッセマネの園で実現した。しかも、それは「アロン家の使命」を担うイエスに対してであり、イエスにその霊的能力がなければ実現しなかったのである。イエスが洗礼を受けた時の天からの声、「わたしの心にかなう者である」はイエスにその資格があることの宣言である。 イエスの宣教は、結果として「苦杯」に向かうことにあったのであり、途中の「教え」は前座にすぎなかった。だが、聖書の読者のほとんどは、「苦杯」の場面は読み飛ばすか、十字架を目前に思う「イエスの弱音」にその解釈をとどめる。 「ルカによる福音書」3章 ①「わたしの心にかなう者」とは 3-21さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて、3-22聖霊がはとのような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。 この言葉の真の意味がわかれば、すべての人は、気絶して、そのまま息が絶えるであろうほどの恐ろしい言葉である。人の霊的汚物、「狂気」が自分の体内に注ぎ込まれれば、その「おぞましさ」はいかほどであろう。だが、普通の人には、「人の霊的汚物」をその身に受け取る能力はないので、安心したらよい。 「ルカによる福音書」22章 ②「苦しみを受ける」とは 22-15イエスは彼らに言われた、「わたしは苦しみを受ける前に、あなたがたとこの過越の食事をしようと、切に望んでいた。22-16あなたがたに言って置くが、神の国で過越が成就する時までは、わたしは二度と、この過越の食事をすることはない」。 「苦しみ」とは、十字架ではない。十字架刑は成り行きで決まっていったものであり、人の営みによるもので、神とは無関係である。だが、それが「信仰」によって「つなぎあわされ」、「苦杯と十字架」となって、光を放(はな)つようになる。「苦しみ」は、イエスが人の罪をその身に負うことの「おぞましさ」を意味する。霊的苦痛は、肉体的苦痛をはるかにしのぐ。 「ルカによる福音書」22章 ③「この杯をわたしから」とは 22-40いつもの場所に着いてから、彼らに言われた、「誘惑に陥らないように祈りなさい」。22-41そしてご自分は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、祈って言われた、22-42「父よ、みこころならば、どうぞ、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの思いではなく、みこころが成るようにしてください」。22-43そのとき、御使が天からあらわれてイエスを力づけた。22-44イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりのように地に落ちた。 イエスが唯一(ゆいいつ)弱音(よわね)をはかれた情景、これこそが「苦杯」である。ありきたりの読者は、これこそはキリスト教の根幹であることに気付かず、「イエスも人だ。架けられる十字架を思っておののいたのだ」としたり顔で人に教える。 |
||||||||||||||||||||
| ⑤ムチ打ちの刑 多量出血をともなうムチ打ち刑は、木にかけたイエスの落命を早めるために作用した。生命力のある者は、昼は灼熱、夜は酷寒の裸を木の上にさらし続ける。息絶えるまで何日もさらされるゆえに恐ろしい「見せしめ」刑なのである。 この場合は、ピラトが「イエスを許そうとした」温情があだになったのである。ムチの先に鉄片の付いたもので裸体を打てば肉ははがされ、肉体はボロボロになって、血まみれになる。そのイエスの哀れな姿を見ればいかに殺気立つユダヤ人でも思い直すであろうと。だがそれは甘かった、ユダヤ人はイエスを殺せとその本音を叫ぶ始末となった。 |
||||||||||||||||||||
| ⑥「イエスの死が十字架で」とは イエスの刑が、「斬首」とか「石打」でなく、木に架けられる「見せしめ」であったのは、結果として、人々がイエスを仰ぎ見ることのできるためである。旧約聖書「民数記」にあるように「イエスを仰いで見て生きる」ためである。 「民数記」21章 「へびを仰いで見て」とは 21-8そこで主はモーセに言われた、「火のへびを造って、それをさおの上に掛けなさい。すべてのかまれた者が仰いで、それを見るならば生きるであろう」。21-9モーセは青銅で一つのへびを造り、それをさおの上に掛けて置いた。すべてへびにかまれた者はその青銅のへびを仰いで見て生きた。 |
||||||||||||||||||||
| ⑦「処女受胎(2)」 死後三日目に遺体が消え、その後出現したイエスとは | ||||||||||||||||||||
| 「ルカによる福音書」24章 「イエスが彼らの中にお立ちに」とは これこそはマリヤさまでなくてはならない。イエスと母のマリヤさまとは、「性」に原因する違いのほかはまったく同じ姿かたち、所作(しょさ)なのである。その場に、カペナウムを朝早くたち、従者の操縦する軍用馬車で、その日の午後遅く宿に着いたルカが遭遇した。彼は仰天して叫んだ「イエスが生きていた」。 24-36こう話していると、イエスが彼らの中にお立ちになった。[そして「やすかれ」と言われた。]24-37彼らは恐れ驚いて、霊を見ているのだと思った。24-38そこでイエスが言われた、「なぜおじ惑っているのか。どうして心に疑いを起すのか。24-39わたしの手や足を見なさい。まさしくわたしなのだ。さわって見なさい。霊には肉や骨はないが、あなたがたが見るとおり、わたしにはあるのだ」。[24-40こう言って、手と足とをお見せになった。]24-41彼らは喜びのあまり、まだ信じられないで不思議に思っていると、イエスが「ここに何か食物があるか」と言われた。24-42彼らが焼いた魚の一きれをさしあげると、24-43イエスはそれを取って、みんなの前で食べられた。 「ルカによる福音書」24章 「聖書を悟らせる」とは マリヤさまは聖書(旧約聖書のこと)に精通しておられた。そして、老ヘロデによるアロン家の滅亡から生き延びたマリヤさまは、「処女受胎」を受けて、アロン家の「罪のあがない」に対する使命を悟られたのであり、それが実現したことを話されたのである。 24-44それから彼らに対して言われた、「わたしが以前あなたがたと一緒にいた時分に話して聞かせた言葉は、こうであった。すなわち、モーセの律法と預言書と詩篇とに、わたしについて書いてあることは、必ずことごとく成就する」。24-45そこでイエスは、聖書を悟らせるために彼らの心を開いて、24-46言われた、「こう、しるしてある。キリストは苦しみを受けて、三日目に死人の中からよみがえる。 |
||||||||||||||||||||
| ⑧イエスの昇天 それは、マリヤさまが、イエスとなられた男装を解き、女に戻られたことの情景である。その手伝いをしたのはベタニヤ近くに住むマルタとマリヤの姉妹であろう。ちなみに、「ヨハネによる福音書」には姉妹の兄弟としてラザロが登場するが、「小説(しょうせつ)」上の人物であり、ウソである。。 「ルカによる福音書」24章 「祝福しておられるうちに」とは 24-50それから、イエスは彼らをベタニヤの近くまで連れて行き、手をあげて彼らを祝福された。24-51祝福しておられるうちに、彼らを離れて、[天にあげられた。]24-52彼らは[イエスを拝し、]非常な喜びをもってエルサレムに帰り、24-53絶えず宮にいて、神をほめたたえていた。2022/5/7、5/11 |
||||||||||||||||||||
| (5)「イエスの死には意味がある」そう考えたのは異邦人 | ||||||||||||||||||||
| イエスはローマ総督の裁定によって、「過越の祭」の恩赦に与(あずか)ったバラバために用意された十字架に架けられた。投獄され、その罪状書きが公示され、処刑に及ぶという手順はカットされた。ピラト自身にとっても不本意な、「わけのわからない」時空があったのではないだろうか。イエスの態度は、常の死刑囚とはまったく違っていた。彼には自分の無罪を叫ぶ代わりに、手足に釘を打ち込まれ、木が立てられて、手足に打たれた釘に裂かれた肉から、ムチ打たれた残りの血が流れ出ていくことにむしろ「やすらぎ」があるようだった。その不思議な光景が展開される最中にピラトの伝令は、方々のローマ軍駐屯地に飛んだ。その中にはカペナウムの駐屯地もあった。その夜に到着した伝令は、ピラトの書簡を読み上げたあとで、その印象を言ったのだった。「十字架を安らぎとした者を初めて見ました」と。その言葉を印象深く聞いた将校がいた。それがクレオパだった。 彼は、ルカをエルサレムに派遣した。そして、三日目の午後に宿に着き、イエスの一行から何かを聞こうと面会を求めた。そして、「イエスだ。生きていた」と驚愕したその相手こそは、マリヤさまだった。イエスの死の謎解きは二人の対面の実現から始まった。マリヤさまはギリシャ語が、ルカはアラム語がいくらか話せたので話は盛り上がった。ギリシャ語はローマ帝国の公用語であり、アラム語は土着のユダヤ人の話し言葉だったのだ。 そして、ルカの報告を受けたクレオパが加わって、アンテオケで最初の「罪のゆるし」の集会が持たれた。最初はクレオパの知人や貴族、解放奴隷たちであったが、そのうち一般市民も対象になった。この「福音」に与った人々はユダヤ人ではなく異邦人だったのである。 そして福音は西に向かった。一行の先頭には十字架の模型を掲げる者がいた。ローマの極刑を象徴する十字架を掲げる人々の行進が目立たないはずがなかった。そしてその一行の組織はピラミッド型をしていたのである。 パウロの相手は各都市のユダヤ人居住区の人々であったのであり、異邦人ではない。異邦人には律法はわからないからプライドの高いパウロの相手ではない。(宿の)エルサレム教会も同様である。 |
||||||||||||||||||||
| (6)教会の「異端」対策 ピラミッド型組織から離脱して自らの組織を作ろうとするものが「異端」である。ローマ帝国の広大な版図が分割統治された時代の影響もあって、東の版図であったエジプトのアレキサンドリヤは自分たちの「智」が「女と漁師」のローマの風下に立つことを拒んだ。そして「ルカによる福音書」をもじって、自らの智を用いた「ヨハネによる福音書」を著し、それを福音書とし、エジプトでは「ルカによる福音書」を廃し、マリヤさまを「イエスの母」に封印した。最大の異端である。 これにより、アロン家による「罪のあがない」という律法の成就は、「愛」を連発する哲学書あるいはウソをまじめに書いた小説にしてしまった。この影響が今も強く残っており、何の御利益もない「智」がはびこっている。この取説は、その「異端」を明らかにし、聖書を神の賜物とする者どもの「智」が「痴」であることをわからせ、カトリック教会に帰るようにうながす。また、カトリック教会内部での「智」化に警鐘を鳴らす。 |
||||||||||||||||||||
| ミチオ書(2)皇妃ガラ・プラキディア (13)キリスト教会の保護 | ||||||||||||||||||||
| ミチオ書(14)異端者アルナルド (5)十字軍の収穫 | ||||||||||||||||||||
| (7)「宗教ルネサンス」 「ルカによる福音書」を深読みする能力は、「勉強」だけでは養えない、さまざまな人生体験に基づいて、教えられなければならないだろう。自分の考えすなわち「智」では、これがカトリック教会の成り立ちにつて書かれたものだということにはならないのだ。聖母子信仰の「み心にかなう人々」、その聖母子の向こうに霊の統合者「父なる神」が垣間見えるのであって、直接言葉を交わすなどありえないことである。 神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」こそはカトリック教会の「力(ちから)」である。それは「処女受胎」に端を発している。すなわちそれが「イエスはアロン家の子」であることを証(あか)しし、「苦杯と十字架」に至って、アロン家を永遠としたのである。すなわち、人が人の罪を負い、その血によってあがなわれることが実現したのである。すなわち、「狂気解消」によって、自らの力では制御できない「奥深くから湧きあがり苦しめる状態」から開放され、自分を取り戻すことができるのである。 |
||||||||||||||||||||
| (8)「人間ルネサンス」 「ヨハネによる福音書」を用いてマリヤさまを「イエスの母」に封じた者たちは、「智の統合者」サタンを「神」とか「主」などと呼び、直接対話をしているのだが自らそれに気付くことはない。そして愛を気安く口にするが、サタンの知るところではない。また祈りと称して気楽な「部分最適」を唱える。「総和」を考えるのは、「仕事」になりそうで、面倒だ。不都合なことは知らんふりするに限る。 人の「智」の統括者はサタンであることに気付かなければいけない。「智」を用いて祈る先に立っている者はサタンである。神の名を連呼して「愛」の祈りをしてもそれは神ではなくサタンにしているのである。神はわたしたちを見守っていてくださるというのも「智」という大言壮語の成せる業(わざ)である。サタンのあざ笑う「祈り」である。 神は実に聖母子の、すなわち女と男それぞれに託されたアロン家の使命を全うされたお二人による「罪のあがない」の向こうに垣間(かいま)見えるだけである。 |
||||||||||||||||||||
| (9)部分最適の総和は絶滅 「すべてのひとから飢餓をなくす」、「健康寿命100歳まで」それらの総和は絶滅なのである。カトリック教会は総和を考えるべきであり、軽々に部分最適を唱えてはならぬものである。 |
||||||||||||||||||||
| (10)「見聞を広めよ」のイタリヤとスペイン | ||||||||||||||||||||
| この10年間、考えもしなかったことが、さりげなく実現した。これらの海外旅行もそのひとつ。無事旅行を終えると、「見聞を広めよ」ということなのだと思った。「取説」に関わっていなかったら、おそらくなかったことだろう。 | ||||||||||||||||||||
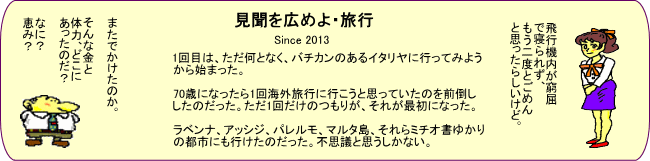 |
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| (11)取説の先には宣教 | ||||||||||||||||||||
| カトリック教会はいかにして成り存続しているのか、それの初めが「ルカによる福音書」に記(しる)されている。わたしはそれに気付くのに12年かかった。そして、それはこの「取説」作成という労働の日々の中で次第に高みに導かれてのことであり、いつの間にか74歳を迎えていた。普通に考えればこの先はない。わたしがいなくなればこの「取説」も次第に風化していくだろう。 唯一それを避ける手段は、宣教を目的とした修道会の新設である。それでこそ「取説」は宣教の武器ともなり、その役割をカトリック教会3000年に向かって働き続けてくれるだろう。 そしてその組織の上にあるのは教皇のみでなければならない。新設修道会が何かの組織の下になれば宣教の効果は発揮されず目的は崩れ去る。「取説」の指摘が現実のキリスト教世界に与えるであろう影響が大きすぎるからであり、穏便にことを運ぼうとすると、この取説が「迷惑」な存在となるのは「世の常(つね)」である。 |
||||||||||||||||||||
| (12)神は人を女と男とに造られた | ||||||||||||||||||||
| それは男女両性にはそれぞれの存在目的を与えるためである。イエスは「苦杯と十字架」による「狂気という名の罪のあがない」の手段を確立した。その成立環境は土着のユダヤ人に律法が息づいているユダヤ地方とエルサレムにあった。律法によれば罪に関与したイエスは「アロン家」の者である必要があった。 母のマリヤさまはその時、ユダ族の青年ヨセフと婚約中だったから、夫婦生活が始まれば生まれ出る子は「ユダ族」である。だが「処女受胎」という奇跡が起こり、イエスはアロン家の者となった。だが世間的には、イエスはユダ族の者に違いなかった。 「処女受胎」はまた、母子の性に起因する違い以外は、その聖書知識、所作に至るまで同じであったが、マリヤさまは顔を隠しておられたので、それに気づく者は家族以外にはいなかった。それがが、復活のイエスの出現をうながしたのである。 男が「人の罪を負い、十字架の血であがなう」ことを成し遂げ、女がそれを人々に教えた。つまりそれぞれの役割を果たされたという意味で、聖母子は一体(いったい)だったのである。 聖母子によるそれがカトリック教会誕生に結びつくのは、カペナウムの将校クレオパとルカの活動があったからである。イエスが百卒長をほめたのは実にクレオパの功績を讃える言葉だったのである。 カトリック教会の聖職者は男女共に独身である。それはグレゴリウス七世の教会改革によって定まったのである。それでも神父と修道女にはそれぞれの役割があるのである。 |
||||||||||||||||||||
| 普通の人々にとっては、夫婦生活を円満とするには、互いに「あなたはわたしのもう半分」と思えたら、幸せというべきである。そして、カトリック教会のミサに参列する機会に恵まれたら、「み心にかなう人々」に数えられ、平和があるであろう。どのような社会環境にあるとしても、時代を超えて。 | ||||||||||||||||||||
| 戻る | ||||||||||||||||||||
| トップ・ページ | ||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||
| 2016年のイタリヤ旅行「バチカン」 | ||||||||||||||||||||
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2022/2/10、2/14、2/15、2/16、2/18、2/23、3/6、4/8、4/18、5/3、5/4、5/7、5/11 |
||||||||||||||||||||
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
||||||||||||||||||||
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
||||||||||||||||||||
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 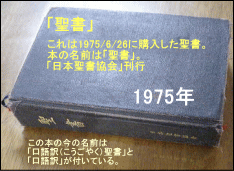 |
||||||||||||||||||||
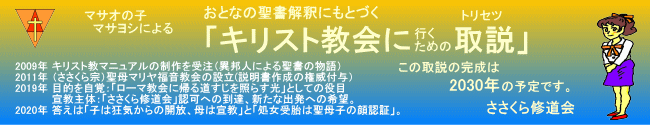 |
||||||||||||||||||||