 |
| (1)キリスト教は霊的に肉体を救済 聖霊降臨は、キリスト教を霊的救済、すなわち狂気からの開放の、個々人に及ぶ御利益(ごりやく)として特徴付ける。全体としてひとつでありながら、個人個人にまで、細胞のようにその生命が及んでいるのである。その頭(かしら)はイエス・キリストである。それを具体化する地上の実態がローマ教会(地域名ではなくローマ帝国のこと)であり、ペテロは初代教皇である。そして、毎週行われるミサは、連綿と続けられ、世々の信者が集い、その霊的信仰を強めあうことは、聖霊降臨の果実と認められる。 聖母子、使徒たち、テオピロことクレオパ、ルカ、アンテオケの集会において、順次聖霊降臨が記されあるいはそれと強く推測されることは、一連の流れが人の知恵ではなく、主なる神からのものであることの証拠とされるべきものである。いわば神のタイムスタンプである。 そして、聖母子により、「苦杯と十字架」による、個々人の「狂気」からのあがないが実現した。それは人が人として、神に生きることのできる唯一の、持続性のあるもので、それを維持するシステムがカトリック教会のミサでなければならないであろう。そして、それを証するものが聖書であるが、それはキリスト教思想の集合体であり、不用意にそれを読む者は、誤認する危険があることを認識すべきである。 聖書を誤用から プロテスタントと総称されるものは、その統一思想は、反教皇、そして初代教皇ペテロのローマ教会の象徴たる反聖母子、聖母マリヤを矮小化させ、イエス・キリストにその役割を転化し、自らの知恵を語り、「神には何でもできる」など、かえって神を侮辱(ぶじょく)する大言壮語の数々によって、せっかくの「狂気のあがない」を無効化している。 そういうことを総合的に踏まえ、聖霊降臨の順番について、その足跡をたどり、カトリック教会のミサが今後とも続いていくことを、カトリック教会の信徒でない今、客観的な立場から、主なる神に祈る。そして、「カトリック教会に帰ろう」というスローガンに接続したい。 (2)「罪のゆるし」の原点 「罪のゆるし」の概念はユダヤ教から来ている。 この時代の「罪」は、イエスのあがなわれた「罪」とはその意味が異なり、むしろ「狂気」とした方が現代人にはとらえやすい。それは内在ししかも自らは消しがたいものであり、かろうじて「理性」と呼ばれるもので覆い隠している。 ユダヤ教は、バビロン捕囚からエルサレムに帰還した人びとが、ペルシャ帝国の自治州として存続するための、王国を目指さない意思表示でもあった。その目的のために、彼らは自治のための文書をペルシャ王に提出した。その「書かれたもの」がユダヤ教聖書の発端となった。編纂(へんさん)のたびに改良を重ね、「創世記」、「出エジプト記」・・・・と文書が成立していった。特に、「出エジプト記」、「レビ記」、「民数記」、「申命記」の四書には律法書の別名がある。それは、四書には、さまざまなエピソードの間に「律法」が挿入されていることによる。いわゆる「十戒(じっかい)」の他に膨大なおきてが挿入され、ユダヤ人にとって最も重要な文書であるとされる。その中には、有名無実のものも多くあるが、それを全部守ろうとするのが新約聖書のパリサイびとである。 その律法は、罪のゆるしの祭ができるのは、モーセの兄のアロンの子孫である「アロン家」のみであり、その中から選ばれた大祭司と定めている。それはユダヤ人全体の罪、あるいは個々人の罪のゆるしが、家畜の血と引きかえになされるものであった。裕福な者は牛などを奉納し、その牛に罪を負わせ、血を流して、罪をゆるしてもらうのである。そして、肉は祭司たちのものになった。 だが、問題もあった。家畜を奉納できない者は罪がゆるされず、律法どおりの石打の刑にあったりする。また、家畜が人の罪を負うことができるだろうか、という疑問である。 その問題解決をテーマとし、実際に解決の道を拓かれたのが、聖母子である。その過程で聖霊降臨が起こったのは、それが人の知恵で成されているのではなく、見えざる力の働きの順番であることを示すためである。だから、聖霊降臨にはステージを示す段階が認められるのである。その第一段階が御使による「受胎告知」とナザレ村の少女マリヤによるその受託である。 少女は老女の対極であり、共に男女の性交では妊娠が成立しなかったとしなければ、「処女受胎」そのものがあざける者たちによって汚(けが)される続けていることは、レオナルド・ダ・ビンチの汚い絵にも表れている。 (3)ローマ教会こそ「聖霊降臨」のゴール ローマ教会はその聖霊降臨の最終段階であり、ミサとして具現されている。その過程を聖書から読み解こうとするのが、このページのテーマである。 そのために、ここでは時間を少しずつ戻すことにしたい。まず、ローマ教会の成立である。ローマ教会のトップは教皇である。4世紀中ごろまで、ローマ帝国はキリスト教を禁じていた。だが水面下では、キリスト教は拡大を続けていたが、表立っての活動ができなかったために、思想が乱立することになった。 そして、ローマ皇帝コンスタンティヌスによりキリスト教容認の勅令が発布され、新たな展開となった。そして皇帝主導で、キリスト教思想の統合者がローマ司教(教皇)と定められた。 |
| (4)「聖霊降臨」の順番を聖書から 聖霊降臨の順番を読み取ろうとする聖書の成立は、やはりコンスタンティヌス帝の貢献による。すなわち、聖書は、皇帝の権力の下(もと)、キリスト教思想のさまざまな文書を統合あるいは廃棄して成立させたものである。 聖書は、キリスト教思想を伝える手段であると同時に、キリスト教のシンボルでもあるが、当初は教会の「権威の象徴」そのものであった。その成立時期からして、聖書はラテン語で書かれていた。聖書の目的は宣教であり、万民の読物とは想定されていなかった。利用者はラテン語の読める聖職者や学者に限られていた。 時代が進み、現在では、教育水準が高まり、人びとの識字率が上がった。また、印刷技術や流通が進化し、現代語、あるいは自国語に翻訳された聖書は、万民が手にできるまでになった。だが、何の予備知識もなく、あるいは案内者を持たずに、それを読めば危険である。読者は「哲学者」に導かれ、「信仰」の道をはずし、何の御利益(ごりやく)を得ることなく、「御言(みことば)と共に生きる」ことにより、言葉の海を彷徨(ほうこう)したあげく、信仰の果実を得ないまま、すなわち「苦杯と十字架」により神と共に生きる悦びを実感しないまま、その生涯を終えることになる。 そのためにこそ、思想の解説書などではなく、議論を提起しない「取扱説明書」が必要であると認識し、これが書かれ続ける。 だから、聖書から聖霊降臨の順番を読み取ろうとするにおいても、その能力が必要なのであるが、わたしの場合は、その学識を超えたところからの啓示といったもので、示されたものを書きとめようとする。学問による学識の成果としてのそれではない。 |
| (5)聖書は「旧約聖書と新約聖書」 キリスト教の諸文書は新約聖書である。ユダヤ教の諸文書をキリスト教が使う場合、旧約聖書と読んで区別している。しかし、キリスト教の立場から聖書というと、その両方をさす。ただし、プロテスタントの旧約聖書は、カトリックの諸文書からいくつか省かれている。 その中のひとつに「マカバイの書上」があるが、これはイエスの時代の直前100年ぐらいの「戦記」であり、アロン家以外の大祭司が存在したことが学べる。 新約聖書の文章には、旧約聖書が引用されているので、聖書はふたつでひとつでもあるとも言える。 旧約聖書はバビロン捕囚から帰還した「ユダヤ人」によって書かれたもので、口述伝承などをふまえ、具体的には紀元前1250年ごろの「出エジプト」からバビロン・ペルシャ捕囚を終え、エルサレムに帰還した紀元前400年ぐらいまでを記述した文書の束(たば)であり、神の選民たるユダヤ人の宝であり続ける。預言書の多くは、南王国ユダの王に対するものであり、バビロンの脅威がその背景にある。また、帰還の発端となったもの、帰還後のエルサレム再建に取り組む人々を励ますものもある。 一方、新約聖書はイエスの誕生から磔刑(たっけい)までを記した「福音書」四つと、「使徒行伝」、「書簡」諸文書、黙示書からなり、聖書として成立した4世紀までの文書である。その中で、「ルカによる福音書」、「使徒行伝」、パウロ書簡は即時報道を元としている。それは、聖書にまとめる作業の中で、さまざまな思想が混ぜられからであり、文章の不連続でそれとわかる。聖書を「神の賜物」として絶対視すれば、混乱するはずであるが、プロテスタント的読みかたでは、都合の良い部分のつまみ食いなので、その影響は少ない。 これらを総合して、聖母子による聖霊降臨の順番を組み立てなければならない。 |
| (6)新約聖書の即時報道部分 新約聖書の中で、即時報道が含まれている文書が、二つのルカ文書である。「ルカによる福音書」と「使徒行伝」の二つである。その記者ルカと献呈相手のテオピロの二人が、「ルカによる福音書」のエピソード「カペナウムの百卒長と危篤(きとく)の僕(しもべ)」だとわかった時に、その文書の即時性の根拠になる。二人が福音書の渦中の人物であるとわかれば、二人の行動も容易に推測されるようになる。たとえば「処女受胎」の証拠である。ルカはその証拠を見た可能性が想起されるに至るのである。 「ルカによる福音書」のオリジナルであろう文書も、そのまま読んでは意味が通らないこともあるのである。たとえば、エマオ村に向かう二人のエピソードとそのうちの一人の名がクレオパと記(しる)されていることである。また違ったイエスとの対話である。これらは突飛(とっぴ)な記事であり、単なるほほえましいエピソードとして済まされている。しかし、二人、エマオ村がエルサレムに近い山里と思われることをキーワードとすれば、ふたりはテオピロとルカであり、テオピロの本名がクレオパであること、エマオ村はザカリヤの家のあったユダの山里の町であることと一致する。 各文書が成立したことの意味は、それらの文書がオリジナルではなく、さまざまな思想、都合の挿入が認められるということである。だから、通読すれば、オリジナル文書の目的からそれたものを認識させられることになる。 そのことを踏まえ、成立当時は「巻物」に写本された。巻物には、文章の挿入や誤まってページが入れ替わりを防止する機能が自ずからあったのである。だが、それを最初のオリジナルに戻すことは成(な)されない。正しいオリジナルの文章を誤まって抜いてしまう恐れがあるからである。 「マタイによる福音書」13章 13-24また、ほかの譬を彼らに示して言われた、「天国は、良い種を自分の畑にまいておいた人のようなものである。13-25人々が眠っている間に敵がきて、麦の中に毒麦をまいて立ち去った。13-26芽がはえ出て実を結ぶと、同時に毒麦もあらわれてきた。13-27僕たちがきて、家の主人に言った、『ご主人様、畑におまきになったのは、良い種ではありませんでしたか。どうして毒麦がはえてきたのですか』。13-28主人は言った、『それは敵のしわざだ』。すると僕たちが言った『では行って、それを抜き集めましょうか』。13-29彼は言った、『いや、毒麦を集めようとして、麦も一緒に抜くかも知れない。13-30収穫まで、両方とも育つままにしておけ。収穫の時になったら、刈る者に、まず毒麦を集めて束にして焼き、麦の方は集めて倉に入れてくれ、と言いつけよう』」。 さて、狂気があがなわれて、肉体と霊魂とが共鳴し合う状態となった人こそは、神の国にいると言えるだろう。それこそが聖書の目的であったはずである。 そしてその証明は「作り話」の上には成り立たない。すなわち、それがもたらされた報道は、それを証明しうる人物による即時報道でなければならないのだ。そして、その人物の存在が聖書から読み取れたとは、何度も指摘してきた。そして、その報道文書は「ルカによる福音書」だとも。だが、何度も言うように、その存在は「智」や「学識」を持ってしては気づくことがなかった。それは信仰と「啓示」によらねばならなかった。 自らの益のための文書 ここで言う、そのための「聖書の読み方」とは、自分たちの「益」がらみでそれを読まないということである。プロテスタントは、「聖書は神の賜物」とするから失格である。相反する記事で満ちている文書を聖とすれば、そこには「解決」はない。彼らは自分たちの「益」の手段を聖書に置き、(1)反教皇、(2)智の探求(信者それぞれの聖句を持つことを推奨)におき、信者を聖母子から遠ざけ、カトリック教会を暗に敵と思わせ、集会の都度自分の考えをメッセージと称して語り、それを自分の仕事とする。 だから、彼らはいつまでたっても「聖霊降臨」の意味に到達しないであろう。それは彼らの益に反することだからである。すなわち、人びとに教皇を想起させないための、聖母子の神聖の否定である。 また聖霊そのものは聖書中に多用されている。聖霊をイエスのアイテムのように扱っている文章がある。それらは、主なる神からの証(あかし)でも何でもなく、人が考えたものであり、主の前には効果はなく、無効である。ただ、宣教と言う仕事を厭(いと)う哲学者のための「智」の産物にすぎない。彼らの目的は、人びとの「救い」ではなく、「智」で彼らの上に立とうとすることである。 「ヨハネによる福音書」は「ルカによる福音書」よりも哲学的に上であろうとするのである。しかし、その実態はウソに満ちている、あるいは作り話、他の3福音書のエピソードを崩したものである。イエスにも哲学者の言葉をだらだらしゃべらせており、神に対する畏(おそ)れも謙遜もあったものではない。 「ヨハネによる福音書」3章 3-34神がおつかわしになったかたは、神の言葉を語る。神は聖霊を限りなく賜うからである。3-35父は御子を愛して、万物をその手にお与えになった。 「ヨハネによる福音書」20章 20-22そう言って、彼らに息を吹きかけて仰せになった、「聖霊を受けよ。20-23あなたがたがゆるす罪は、だれの罪でもゆるされ、あなたがたがゆるさずにおく罪は、そのまま残るであろう」。 この二つを見ても、哲学者の考えた「智」の賜物であることがわかる。だから、これらの聖霊には何の証拠能力もない。「罪のあがない」というキリスト教の「一丁目一番地」から遠く離れている。はっきり言ってキリスト教思想とは言えない。そのことを軽く指摘してから、聖霊降臨の順番に戻る。 |
| (7)聖霊降臨は「ローマ教会誕生」の証拠能力 |
| 聖書は、キリスト教の禁教が解かれた4世紀に成立したが、時を同じくしてキリスト教思想の統合者がローマ司教と定められた。禁教下でもキリスト教は拡大を続けていたが、宣教の道具として文書を使った「組織」があった。その文書は300年という歳月の中で「オリジナル」性はそこなわれたが、ルカ文書とパウロ書簡から成る。 「智」を自認するアレキサンドリヤ司教はおもしろくなかったであろう。だから、それらを哲学的なものにアレンジした。聖母子を退け、神の子イエス・キリストを前面に出し、イエスをべらべらしゃべる哲学者にし、母マリヤの口を封じて普通の女にした。そして、「マグダラ」と呼ばれた女を聖母に替えた。そしてアレキサンドリヤ教会の司教区の文書とした。「ヨハネによる福音書」は、ローマ教会では読まれたはずのない文書である。 だが、4世紀に至り、ローマ皇帝の権威の下(もと)に生まれた教皇と聖書とをもって、キリスト教の新たなスタートとし、21世紀の今も存続を続けているのがローマ・カトリック教会である。このローマは「ローマ帝国」のことであり、「世界」のことである。その総本山の場所は、イタリヤのローマであり、今はバチカン市国として、世界のカトリック教会を統括している。 カトリック教会で毎週行われるミサ、信徒の集う礼拝式こそは聖霊降臨の果実であり、この記事の結論とも言える。カトリック教会は、ローマ帝国世界に誕生したが、その後、帝国は東西に分割統治された。一方の西ローマ帝国は長持ちせず、アルプスを越えて南下する蛮族に滅ぼされた。そのため、ローマ教会も防御におわれ、存続上のさまざまな試練を受けた。それに比べると東ローマ帝国はイスラムの侵攻にさらされながらも、オスマン・トルコが台頭するまで存続した。 カトリック教会という名称は、その後ローマ教会から離脱した宗派と区別するための、いわば識別子(しきべつし)である。離脱の理由は、自らの利のためである。いわゆる「正教会」やプロテスタント(総称であり教会名ではない)と区別するための「カトリック」である。カトリックそのものに意味づけすることには無益である。偽者(にせもの)とは、初代教皇はペテロ、聖母子、聖母マリヤ、聖職者は独身、などのキーワードで容易に識別できる。 「正教」の頭には地域名がつく。たとえば、ギリシャ正教である。そのルーツは、東ローマ帝国のカトリック教会である。かつて首都であったコンスタンティノープルの城壁の中に置かれた御用教会となって、ローマ教会と対峙するようになった。ローマ教会が教会改革ひとつとして「聖職者の独身」を敢行すると、あっさり袂(たもと)を分かってしまった。彼らは「妻帯禁止」を拒(こば)み、肉欲を満たし、聖職者の世襲を維持した。だが、コンスタンティノープルがイスラムの洗礼を受け、イスタンブールになると、それまでの宮廷気分は吹き飛んだ。世界大戦でオスマントルコが敗北側になり、政教分離の「共和国」になると、ギリシャの名前を冠してギリシャ正教を名乗り、「ギリシャ人ならわが教会」としたのである。 だからカトリック教会とは何の関係もない。イコン(聖母子画)は、ローマ帝国が東西に分割統治されたころの皇帝によるものである。くどくど述べているプロテスタントもまた、500年前に起こったカトリック教会からの離脱を発端とするが、「正教」とは異質であるから、項目を改めよう。 依然として、わたしは、「ルカによる福音書」に記された聖霊降臨の順番が、福音の成就と、その宣教にかかわり、その先にローマ教会の誕生があったことについて述べている。 |
| (8)ローマ教会2000年の試練、異端と離脱 宗教改革と呼ばれた、カトリック教会からの離脱運動を誘導した元もとの原因は、聖職者の「叙任権」闘争である。それは「神聖ローマ帝国の皇帝」と「ドイツ王」を兼務した人物であり、それが尾を引き、反ローマ教皇のドイツ領主たちに及んだ。司祭であったマルチン・ルターが門に張り出した、免罪符などの「質問文」が評判になると、彼らはルターを支援・保護した。 ルターのカトリック教会離脱というより、いられなくなったのだが、他の反教皇勢力にも支持され、教会からの離反が瞬(またた)く間(ま)にヨーロッパ中に広まった。 そして、離反者たちは、カトリック離脱の「錦(にしき)の御旗(みはた)」として聖書をかかげた。「ローマ・カトリック教会に唯々諾々(いいだくだく)として従うのをやめ、聖書を読んで真実の信仰を求めよう」と宣伝した。それは聖書が読める扇動者たちの言い分であって、一般のカトリック信者にとっては迷惑な話だった。ところが、領主たちは領民を力ずくでカトリック教会に行けなくしてしまった。 だが、実際には、それは「あさはかさ」の何ものでもなく、人びとを「カトリックの持つ」信仰からそらせて、「智」の哲学者へと誘導することになったのである。ドイツ王と諸侯の勢力が消えたあとでも、その運動は拡大したので、その運動は総称して「プロテスタント」と呼ばれた。プロテスタントには聖書以外の継続性はない。むしろ分裂のDNAがあるので、それを繰り返して細分化を続けた。バブテスト派、長老派、ペンテコステ派などが軒(のき)を連(つら)ねた。それはプロテスタントの持つ分裂のDNAの仕業(しわざ)にほかならなかった。 このプロテスタントたちは聖母マリヤを退け、イエス・キリストに聖母の役割を兼ねさせた。 彼らは新約聖書を吟味し、プロテスタント的「解決」を見出(みいだ)したかというと、そんな「労働」はしなかった。聖書は神からの賜物であるから、各自自身が、自分的解決を見出すべきだ、そのような無責任な論理を蔓延(まんえん)させ続けているのである。だがそれこそは信者を哲学者へいざなう門である。信者は信仰という「信じること」からそれて「智」に向かい、哲学者へと導かれていることに気づかない。そして用いる聖書の文書は、「ヨハネによる福音書」と「詩篇」にほぼ限定されるのである。そして自分が「智」に目ざめたことを誇るようになる。 だが、その「ヨハネによる福音書」を著したのは、エジプトのアレキサンドリヤにあった教会の「わたしたち」であった。実際に、生前のイエスや母マリヤ、そして弟子たちを何も知らない時代の者たちである。 「ヨハネによる福音書」意味不明の「わたしたち」 3-11よくよく言っておく。わたしたち(4)は自分の知っていることを語り、また自分の見たことをあかししているのに、あなたがたはわたしたち(5)のあかしを受けいれない。 21-24これらの事についてあかしをし、またこれらの事を書いたのは、この弟子である。そして彼のあかしが真実であることを、わたしたち(11)は知っている。21-25イエスのなさったことは、このほかにもまだ数多くある。もしいちいち書きつけるならば、世界もその書かれた文書を収めきれないであろうと思う。 また、彼らは自らの「ヨハネによる福音書」を他の福音書と同時代の者と思わせるような工夫をした。そのため、架空の人物をつくった。たとえば有名な「ラザロ」を「ヨハネによる福音書」のハイライトに使い、「伝道者」ピリポを「使徒行伝」に混入した。ちらっと「伝道者」を冠して、その人物の正体(しょうたい)、架空の人物であることがわかるようにした。 聖書には、そういった自分たちの都合を土台に福音書を組み上げた文書がある。そういった予備知識なしに、「神からの賜物」として聖書を読めば、その都合に誘導され、混乱するのは当然である。 混乱しない人は、自分に都合の良い言葉を、つまみ食いしているからである。まさに、都合の悪いことは読まないといった具合に、そういった面倒に巻き込まれるのを避けている。 ローマ・カトリック教会は聖職者の妻帯(さいたい)を禁じているが、それ以外のもの、地域名「正教」やプロテスタントは妻帯している。カトリックは教会改革の一環としてそれを断行したが、そのとたん東方ローマ教会はローマ・カトリック教会と袂をわかち、地域名・正教へと未来への舵を切った。 マルチン・ルターは聖職者であったが、カトリック教会を出奔(しゅっぽん)した後に妻帯した。プロテスタントの牧師たちも妻帯する。 「聖書」妻帯に対するパウロの勧告 プロテスタントの教師は読み飛ばす。 「コリントびとへの第一の手紙」7章 カトリックの聖職者の心意気 未婚の男子は主のことに心をくばって、どうかして主を喜ばせようとするが、7-33結婚している男子はこの世のことに心をくばって、どうかして妻を喜ばせようとして、その心が分かれるのである。 カトリックのシスターたち 7-34未婚の婦人とおとめとは、主のことに心をくばって、身も魂もきよくなろうとするが、結婚した婦人はこの世のことに心をくばって、どうかして夫を喜ばせようとする。 7-35わたしがこう言うのは、あなたがたの利益になると思うからであって、あなたがたを束縛するためではない。そうではなく、正しい生活を送って、余念なく主に奉仕させたいからである。 「主に奉仕する」ということはどういうことなのか、地域名「正教」も牧師も考えたことはないであろう。それは、イエス・キリストを拝み倒すことでも、慇懃にへりくだることでもない。それは、人をミサに受け入れ、その人が神と共に生きていることを、その置かれた境遇にかかわらず実感し、さらなる1週間を心強く歩めるように導くことである。そのために、教会は宣教という労働もまた疎(うと)んじてはならないのである。彼らは、囲い込み宗教であり、すべて人のためではなく、自分たちの都合で、「主に奉仕する」のである。人のことは考えていない。妻帯もしかりである。 |
| (9)ローマ教会の聖母子とペテロ ローマ教会が、無知あるいは、ただ何となく聖母子、また聖母マリヤをあがめ、ペテロを初代教皇としたのか、それでよく2000年も続いたものだ。 漠としたものではあったが、そのような疑問を持った。そしてその疑問の答なり根拠を求めようとしたわたしに、はからずも思い浮かんだもの、イメージ、啓示といったものが、このページのタイトル、「聖霊降臨の順番」につながった。 そのためには、聖書の文書には、読者に確証を与えるもの、証拠といったものが必要であるとも思うに至った。そうでなければ、それらの文書は、単なる「智」の産物でしかない。魂を揺さぶり、からみついた狂気からあがない、それによって歪(ひず)んだ肉体が正常化され、霊魂と肉体とが共鳴しあうに至る、信仰に生きている実感と悦びとを味わい得ないであろう。それこそは聖書から読み取る、信仰の賜物、答えでなくてはならない。 聖書の唯一の答とは そしてその答えは、イエスの「苦杯と十字架」に信仰をおく、「狂気のあがない」なのである。これこそが、人が人として、神と共に、あるいは神の中に自分を生きる秘訣なのである。 復活はそのあがないが「いつまでも」、つまり世々に「今、現在」であるためであり、昇天はイエスが「永遠の大祭司」であることの証である。イエスが律法の下にお生まれになったのであれば、罪のあがない、「あがない」とりもなおさず「ゆるし」、に関わるには、イエスはアロン家の者でなければならない。イエスがアロン家の者である保証はあるのかが聖書に問われる。 その答えこそは、イエスが処女受胎によってマリヤから生まれたことである。処女受胎の目的はイザヤ書の成就などではなく、イエスが母のみの血を引き継いだことなのである。イエスの母マリヤの素性のわかる記述は、祭司ザカリヤの妻エリザベツとの関係である。「エリザベツはアロン家の娘のひとりで」、また「マリヤの親戚であるエリザベツ」の記述から、マリヤがアロン家の直系であることがうかがわれる。「アロン家」への言及は、新約聖書中、「ルカによる福音書」のみであるが、ルカがそういったことを知っていて書いたとは思われない。彼はその解き証(ときあかし)を「違ったイエス」から聞いたのである。 「ルカによる福音書」1章 1-5ユダヤの王ヘロデの世に、アビヤの組の祭司で名をザカリヤという者がいた。その妻はアロン家の娘のひとりで、名をエリザベツと言った。1-6ふたりとも神のみまえに正しい人であって、主の戒めと定めとを、みな落度なく行っていた。1-7ところが、エリザベツは不妊の女であったため、彼らには子がなく、そしてふたりともすでに年老いていた。 中略 1-34そこでマリヤは御使に言った、「どうしてそんなことがあり得ましょうか。わたしにはまだ夫がありませんのに」。1-35御使が答えて言った、「聖霊があなたに望み、いと高き者の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と、となえられるでしょう。1-36あなたの親族エリザベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女といわれていたのに、はや六ヵ月になっています。1-37神には何でもできないことはありません」。 この文章は、証拠に基づいており、それゆえに「聖句」と呼ばれるにふさわしいのである。そして、この聖句がローマ・カトリック教会の礎(いしずえ)なのである。聖句が礎ならば、その上に立つ教会が2000年続いていることは偶然とは言えないであろう。 復活による、時空を超えた十字架 個々人がその狂気にあるとき、その聖母子信仰と共に、「苦杯と十字架」に思いをいたし、自らの狂気を杯に移すとき、イエスに新たな苦悩が増す。それこそは、自分の狂気がイエスの体内に注がれたのだ。 その自覚をもとに次の場面に目を転じる。イエスにムチ加えられ肉片が飛び散り、出血多量に目がかすむ様子が見える。そして、その場面に入る。そして、バラバの十字架を負い、ゴルゴダへの石畳を裸足(はだし)で歩むイエスについて行く。 イエスは出血のため、木材の重さに耐えられず、倒れる。思わず、走りよって彼を助けようとする自分を見る。人びとのあざける声が聞こえる。「ダビデの子よ。どうした」。 仰向けの裸体のイエスが木に載せられ、手足に釘が打ち込まれる。そして、それが地面に立てられる。イエスの足は傾いた棚の上に置かれている。その足台のために体重が一気に手足の釘にはかからない。その足台の目的は、手足の肉が一気に裂かれて、身体が木から落ちるのを防ぎ、徐々に裂かれるようにするためである。そのため、残酷な苦痛が長引く。生命力があればあるほど、その激痛を生きなければならない。 肉と釘の境目から血がしたたり出ている。人はその光景を仰ぎ見る。おお、イエスの顔は何とおだやかであることか。おお、十字架はイエスには苦痛ではないのか。 イエスから流れ出る血は、人の狂気を帯びた悪血である。イエスには、それが苦痛を上回る快感であるかのようだ。それこそはイエスが、神から出た者であり、神格を備えていることの印(しるし)なのであろう。 「ルカによる福音書」3章 3-21さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、天が開けて、3-22聖霊がはとのような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。 そしてついに、出血多量のイエスの息が絶える。そのとたん、人自(ひとみずか)らの狂気がふっと消える。狂気があがなわれたのである。 キリスト教初期においては、神父が信者からの告悔を聞き、イエス・キリストにとりなした。 そして、神父は信者に言った、「子よ、あなたの罪は赦された」。 これこそは「証拠」に基づく、キリスト教の奥義である。信徒にこれ以外を教えることは悪から来るとされたであろう。だから、むしろ積極的に「聖書」を読むことは禁じられたのである。レオナルド・ダ・ビンチは、聖書からではなく、自らの知恵で、カトリック教会と聖母子をあざ笑った。自分に絵画の注文をくれなかったからである。また、グーテンベルクは、聖書を読めばカトリック信徒の目が開かれると予見した。果たしてそうか、聖書はプロテスタントの偶像となり、全体の意味を考えず、部分読みして、自らの知恵を付言して、聖書の恵みを無効にしている。そしてそのおぞましさを省(かえり)みない。 今展開した場面こそは、順を追って起こった聖霊降臨、神のタイムスタンプ、「個々人の狂気のあがない」の完成形なのである。イエスの「あなたの罪はゆるされた」が、時を超え、場所を越えて、狂気に苦しむ信仰者から完全に取り除き、歪んでいた肉体を正常化するのである。そして、それはイエスの復活によって時空を越え、昇天によって地域を越えるのである。 また、「個々人の狂気のあがない」は、人の知恵によらないゆえに、「完全」でなければならない。聖霊降臨の順番もまた、どの部分も完全でなければならない。だから、聖霊降臨のそれぞれのパーツは、主なる神のご意志が働いている証であり、何かが成し遂げられるようとしたのである。イエスの磔刑(たっけい)直後、ルカはテオピロに命じられてエルサレムに到着し、巡礼者の宿に入り、イエスの母マリヤに面会を求めたが、そこには「違ったイエス」がいて、弟子たちを教えていた。そこから彼の聞書きと見聞が始まったのである。そして数ヵ月後、テオピロへの報告書ができあがった。「ルカによる福音書」の基になった文書である。そこに書かれた記事は、神の完全を証するものであるはずなのだ。 聖書は、それを伝えんがためのものであり、その果実がローマ教会のミサであるとは、何度指摘しても指摘足りない悦びである。聖書全体は「ルカによる福音書」に帰すのである。 ローマ教会の成立とミサの存続をもって、主のタイムスタンプとも言える聖霊降臨は完了したとも言える。聖霊降臨は三段階を踏んでイエス・キリストの成就に至り、当初の目的を終えたのである。ローマ・カトリック教会は、ローマ帝国時代には、帝国世界の普遍教会であり、帝国解体後は万人の普遍教会となったのである。 そういう意味では、地域名を冠した「正教」は、「ユダヤ人を囲い込むことが目的」のユダヤ教の域を出ず、聖霊降臨を無効にしている。プロテスタントは聖書を神からの賜物とし、中身を疑うどころか盲信し、相反する記事においては、自分に都合の良い記事を「聖」とする。 |
| 前置きが長くなったがそろそろ本題に入ろう。キリスト教を特徴付ける「聖霊降臨」について、その記述と順番が確認できるのは「ルカによる福音書」のみである。 (1)聖霊降臨の第一段階、マリヤさまの場合 最初にそれは、ナザレ村の少女マリヤに起こる。その場面は、「受胎告知」である。なぜ「少女」かと言うと、エリザベツが「老婆」だからである。ふたりとも、性交によっては、その胎に子供を宿さないということであり、その受胎はいかにも聖書的である。マリヤの年齢は大人となる12歳前と推察される。 大天才レオナルド・ダ・ビンチはこの点の考察を怠りというか、聖書を読めなかったためというか、明らかな不倫の証拠として、聖母子を堕母子とし、絵に反映させたのである。 「ルカによる福音書」1章 「聖霊があなたに臨み」 1-34そこでマリヤは御使に言った、「どうしてそんなことがあり得ましょうか。わたしにはまだ夫がありませんのに」。1-35御使が答えて言った、「聖霊があなたに臨み、いと高き者の力があなたをおおうでしょう。それゆえに、生まれ出る子は聖なるものであり、神の子と、となえられるでしょう。1-36あなたの親族エリザベツも老年ながら子を宿しています。不妊の女といわれていたのに、はや六ヵ月になっています。 「聖霊があなたに臨み」これが聖霊降臨の可能性である。そして、それが起こるのは、マリヤさまが御使からおばあちゃんの妊娠を聞かされ、受胎告知の言葉を受け入れてこそである。マリヤさまが拒否されていれば聖霊降臨はなかったのである。そして確かに拒否は可能だったであろう。だが、マリヤさまは「受胎告知」をお受けになった。その時、マリヤさまの心は「神の国」にあり、肉体の五官はその準備を開始したのである。すなわち、少女からおとなの胎に成長した。 1-29この言葉にマリヤはひどく胸騒ぎがして、このあいさつはなんの事であろうかと、思いめぐらしていた。1-30すると御使が言った、「恐れるな、マリヤよ、あなたは神から恵みをいただいているのです。1-31見よ、あなたはみごもって男の子を産むでしょう。その子をイエスと名づけなさい。 このように、「受胎告知」は未来形である。マリヤさまは拒否できたのである。 1-38そこでマリヤが言った、「わたしは主のはしためです。お言葉どおりこの身に成りますように」。そして御使は彼女から離れて行った。 「御使は彼女から離れて行った」とは、傍目(はため)にも恐ろしい場面ではある。 御使の言葉の確認「エリザベツの妊娠6ヶ月」 1-39そのころ、マリヤは立って、大急ぎで山里へむかいユダの町に行き、1-40ザカリヤの家にはいってエリザベツにあいさつした。 「ユダの山里の町」とは具体的には「エマオ村」である。「ルカによる福音書」の最後の章に置かれたエピソードで二人の弟子がその村に歩いて行く道々、違ったイエスと対話するのである。エルサレムから7マイルほど離れたその村こそ、祭司ザカリヤとエリザベツの「町」である。 そういうわけで、ナザレとユダの山里の町とは直線距離で100kmぐらい離れている。マリヤさまがひとりで行ける距離ではない。自分の身に起こった「受胎告知」と妊娠とは、ヨセフに打ち明けていなければならない。そしてヨセフはマリヤの言葉を信じていなければならない。そしてヨセフは、是が非でもその御使の言葉とやらを確認する必要があった。 1-56マリヤは、エリザベツのところに三ヶ月ほど滞在してから、家に帰った。 マリヤはヨセフのためにもエリザベツが産む子の性別を確かめる必要があった。1ヶ月程度のタイムラグは、旅の仕度(したく)、実家ベツレヘムでの婚礼のためのゆえであろう。後日、マリヤの妊娠がヨセフのゆえだとするためには、婚礼は不可欠である。エマオ村とベツレヘムはエルサレムをはさんで同じぐらいの距離である。 だから二人は、まずヨセフの実家に帰り、婚礼を済ませてから、エリザベツの所に行ったのである。ナザレでは二人がヨセフの実家に滞在していると思ったであろう。 |
| エマオ村のヒント |
| エマオ村、ユダの山里の町「福音書地図」 |
| (2)聖霊降臨の第二段階、イエスの場合 |
| 二番目の聖霊降臨はイエスに起こる。イエスの年齢はおよそ30歳。 |
| イエスは荒野に導かれ悪魔の誘惑を受けるエピソードがあるが、それがイエスに課されたテストであろう。そしてそれに合格したら、父なる神にほめてもらえることになる。ところが聖書を読むと、イエスに臨んだ聖霊降臨と誘惑は、想定される逆の順番で書かれている。 (1)イエスはヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。 (2)すると、天から聖霊がイエスに下り、「わたしの心にかなう者である」という声がした。 (3)イエスは聖霊に満ちてヨルダンから帰ると、荒野を四十日ひきまわされて、悪魔試みにあわれた。 (4)御霊の力に満ちあふれてガリラヤに帰り、諸会堂で教え始められた。 この順番はおかしいと思うのである。イエスの聖霊降臨は、マリヤが受胎告知を受諾した時のように、男女の区別があるものの、まずこの世の「誘惑」が臨み、それを退ける力が試されるのが筋というものである。 だから、この順番だったろうと思うのである。順番は、写本の時などに入れ替わった可能性がある。 (1)(3)イエスは (2)(1)イエスはヨルダン川でヨハネから洗礼を受けられた。 (3)(2)すると、天から聖霊がイエスに下り、「わたしの心にかなう者である」という声がした。 (4)(4)御霊の力に満ちあふれてガリラヤに帰り、諸会堂で教え始められた。 「ルカによる福音書」3章 3-23イエスが宣教をはじめられたのは、年およそ三十歳の時であって、人々の考えによれば、ヨセフの子であった。 ヨセフはヘリの子、3-24それから、さかのぼって、マタテ、レビ、メルキ、ヤンナイ、ヨセフ、・・・・。 (1)4-1さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川から帰り、4-2荒野を四十日のあいだ御霊にひきまわされて、悪魔の試みにあわれた。そのあいだ何も食べず、その日数がつきると、空腹になられた。 4-3そこで悪魔が言った、「もしあなたが神の子であるなら、この石に、パンになれと命じてごらんなさい」。4-4イエスは答えて言われた、「『人はパンだけで生きるものではない』と書いてある」。 4-5それから、悪魔はイエスを高い所へ連れて行き、またたくまに世界のすべての国々を見せて4-6言った、「これらの国々の権威と栄華とをみんな、あなたにあげましょう。それらはわたしに任せられていて、だれでも好きな人にあげてよいのですから。4-7それで、もしあなたがわたしの前にひざまずくなら、これを全部あなたのものにしてあげましょう」。4-8イエスは答えて言われた、「『主なるあなたの神を拝し、ただ神にのみ仕えよ』と書いてある」。 4-9それから悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、宮の頂上に立たせて言った、「もしあなたが神の子であるなら、ここから下へ飛びおりてごらんなさい。4-10『神はあなたのために、御使たちに命じてあなたを守らせるであろう』とあり、4-11また、『あなたの足が石に打ちつけられないように、彼らはあなたを手でささえるであろう』とも書いてあります。4-12イエスは答えて言われた、「『主なるあなたの神を試みてはならない』と言われている」。4-13悪魔はあらゆる試みをしつくして、一時イエスを離れた。 (2)3-21さて、民衆がみなバプテスマを受けたとき、イエスもバプテスマを受けて祈っておられると、(3)天が開けて、3-22聖霊がはとのような姿をとってイエスの上に下り、そして天から声がした、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」。 (4)4-14それからイエスは御霊の力に満ちあふれてガリラヤへ帰られると、そのうわさがその地方全体にひろまった。4-15イエスは諸会堂で教え、みんなの者から尊敬をお受けになった。 だが、こんな俗っぽいことで神がイエスをほめるだろうか、とわたしは思うのである。イエスがその資質を評価されるのは、たとえば人のことを自分のことのように、それも人並み以上に取り込む能力であり、そうした相手を慰めずにはおかぬ霊魂の持ち主であることだろう。やもめの一人息子の葬列の母のようすにイエスが目を留められたエピソードである。それは「百卒長と病気の僕(しもべ)」のエピソードのすぐ下にある。あるいはこの「葬列のやもめ」のエピソードの評判をカペナウムの百卒長テオピロは聞いていたのかもしれない。 「ルカによる福音書」7章 7-12町の門に近づかれると、ちょうど、あるやもめにとってひとりむすこであった者が死んだので、葬りに出すところであった。大ぜいの町の人たちが、その母につきそっていた。7-13主はこの婦人を見て深い同情を寄せられ、「泣かないでいなさい」と言われた。7-14そして近寄って棺に手をかけられると、かついでいる者たちが立ち止まったので、「若者よ、さあ、起きなさい」と言われた。7-15すると、死人が起き上がって物を言い出した。イエスは彼をその母にお渡しになった。 やもめと死んだ一人息子、その母はおそらくワーワー泣いてはいないのだ。だが、足元はおぼつかない。婦人は深い悲しみを抱きつつも、自分と息子がなぐさめられることを神に祈っていたのだ。イエスはその母の霊魂を感じ取られたのだ。そしてそれが深い同情となったのだ。これこそが、イエスが人の「狂気」をその身に負うことのできる能力の雛形(ひながた)なのだ。イエスは人なので、歳をとっていく。老いの先には死がある。いつまでも、人と関わるわけにはいかないのだ。そして、そのままでは万民に関わることはできないのだ。 これがやがて「苦杯」につながっていくのだ。いつまでも、どこででも、だれにでも、その狂気を自分のものとし、ゆるしを与えるためには、どうしたらよい?だが、その未来は父の神の権能の下(もと)にある。人の「智」をもって未来を推し量り、知恵を持って計画することは、神の御前にはおろかなことであり、水泡に帰してしまうのだ。 |
| (3)聖霊降臨の第三段階、宿の弟子たち |
| 主人テオピロの命(めい)を受け、ユダヤ人の長老を伴い、ルカは巡礼者の宿のひとつマルコの母の家に着いた。そして長老の取次ぎでイエスの母マリヤと面会した。現れた人物を見たルカは息が止まるほどに驚いた。その人物は処刑されたはずのイエスだった。ルカは共にカペナウムいたイエスを知っていたからである。しかし、ほどなくそれが女性であることがわかった。まさにイエスの母だったが、男装していた。だから彼女はイエスとして使徒たちに接していたのだった。どうしてそんな格好をしているのだとルカの疑問はふくらんだ。 その後、ルカと「違ったイエス」とは意気投合するところがあった。それは、彼がイエスにほめられたカペナウムの百卒長からつかわされた者であり、イエスのすべてを知りたいと願ったその望みのゆえにマリヤさまは心を動かされたからであり、ルカにしてみれば思い切ったことをしてのける男装の彼女に心を動かされたからである。 そしてルカはなぜあなたとイエスはかくも生き写しなのかと問うたのである。それはその酷似のゆえに、弟子たちは彼女をイエスとして接しているからである。 弟子たちの喪失感は大きかったはずである。イエスはヨセフの子でダビデの子孫であるがゆえに、人々も期待し、弟子たちも「出世する」夢を見たのである。 もし、この違ったイエスが弟子たちの前に現れなければ弟子たちは目標を失い、妻帯者のペテロなどは帰郷してしまったであろう。 驚いたことに、この「違ったイエス」は生前のイエスがユダ族ではないとその秘密を明かしたのである。では誰の子なのか。 イエスが生存中、弟子たちはイエスの母の顔をよく知らなかった。彼女は一行に奉仕する女性たちの中にいたが、かぶりものをしてその顔を目立たなくしておられた。使徒や弟子たちにとって女性たちは奉仕者という労働者にすぎず、誰も関心を払うことはなかったので、そのひとりにすぎなかったマリヤさまの顔など思いもしなかった。 だからイエスを失って頭を抱え込む彼らの前に男装したマリヤさまが現れたときには「ゆうれい」と思って恐れ狼狽したのである。そして、やがて彼らはそれが若さが残る女であり、イエスの母だと気づく。だが、その違ったイエスの所作といい、言葉遣いといい、律法の知識といい、パンを割くようすといい、まさにイエスに違いなかった。 彼は立身出世の望みがはかないものであることを理解した。イエスはユダヤの王になろうと一度だって口にされたことはなかった。自分たちが早合点しただけだが、イエスはそれをとがめようとはされなかった。 ペテロがイエスを「キリスト」と告白したことがあるが、それとて、ヘロデが王になるまで、ユダヤは大祭司が治めていたから、キリストもまた王の別名として使ったのだった。 しかし今、「違ったイエス」は罪(狂気)の赦しについて語っているのだった。それは今までとはまったく違った、個々人の、それぞれのもので、自分の力ではどうにもならない、心の重圧といったもの、狂気と表現するしかない状況からの開放である。生前イエスが口にした「あなたの罪はゆるされた」という「ゆるし」の場面が、個々人に、時代を超えて展開されるのである。そのためにこそイエスの復活はあったのである。 弟子たちから絶望という狂気が消え去り、巡礼者の宿に「神の国」が出現していた。それを証(あかし)するものが聖霊降臨であり、三番目となる。 さらにルカは母マリヤから「処女受胎」にまつわる話を聞いた。イエスの誕生から12歳ごろまでの話である。ペテロと他の女性たちも一緒に聞いていた。ペテロはなおさら熱心に聞き入り、このイエスに従おうとしていた。 そしてルカは、エリザベツのことを聞くためにユダの山里の町、エマオ村に出かけた。また羊飼いの騒動を確かめるためにベツレヘムにも出かけた。二ヶ所とも今いるエルサレムから10キロ・メートルそこそこの近距離にあり、ペテロも女性たちも、もちろんマリヤさまも、みんな一緒に出かけた。ピクニックであった。 ルカは「処女受胎」の結果オーライこそは、「違ったイエス」の働きのためであったことを悟ったのである。それこそは異邦人すなわち「世の人々」への「罪のゆるし」の伝道への道をつなぐものなのだ。 かつて、ヨセフ一家が神殿詣でをした際にシメオン老が口にした言葉に思いをはせた。シメオンが霊感を揺さぶられたのは、聖母子の酷似なのであった。彼が目前の母子の行く末(ゆくすえ)など知る由もなかったが、神をほめたたえて口にしたその言葉は30年後の今、確かに成就したのである。 「ルカによる福音書」2章 シメオン老の賛歌 「2-30わたしの目が今あなたの救を見たのですから。 2-31この救いはあなたが万民のまえにお備えになったもので、 2-32異邦人を照らす啓示の光、 み民イスラエルの栄光であります」。 が、展開されようとしているのである。 そして、弟子たちに聖霊降臨が起こった。 「使徒行伝」2章 2-1五旬節の日がきて、みんなの者が一緒に集まっていると、2-2突然、激しい風が吹いてきたような音が天から起こってきて、一同がすわっていた家いっぱいに響きわたった。2-3また、舌のようなものが、炎のように別れて現れ、ひとりびとりの上にとどまった。2-4すると、一同は聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに、いろいろの他国の言葉で語り出した。 「いろいろの他国の言葉」とは、一民族宗教にすぎない「ユダヤ教」を超えた、「普遍」宗教誕生を象徴したものであろう。この使徒たちへの聖霊降臨をもって、あからさまなものはなくなるのである。時代は次のステージ、異邦人への宣教とローマ教会誕生へと移っていくのである。そしてパウロとエルサレム教会とは、このことを知らない。 |
| (4)聖霊降臨の第四段階、アンテオケの人々 |
| ルカによる聖母と女性たち、また使徒や弟子たちへの聞き書きが終わり、順序正しく、簡潔にまとめられた、テオピロへの報告書が完成した。文書はギリシャ語で書かれていたが、ルカはアラム語で皆に読み聞かせた。そして、主人、カペナウムの百卒長テオピロのもとに帰った。3ヶ月が過ぎていた。 テオピロはルカに、聖母と女性たち、ペテロたち聖母を慕う使徒や弟子たちをアンテオケの自宅に招きたい旨伝えてもらいたいと言って再びエルサレムに送り出した。テオピロはルカを解放奴隷としローマの市民権を買い与えていた。そして、彼の部下をつけた。 再び、エルサレムの宿に戻ったルカは、聖母にテオピロの伝言を伝えた。マリヤさまもまた、自分のユダヤ人に対する役目が終わったことを思っておられた。一行は軍港カイザリヤから海路アンテオケに向かった。アンテオケでは、テオピロことクレオパが一行を出迎えた。そして、クレオパは家の者や招いた友人とともに、集会とパーティを催した。最初にルカの文書が読まれ、続いて聖母たちが証言した。アラム語はギリシャ語に同時通訳された。会場には、神聖な空気がただよった。肉体的な美を競う、ギリシャの薫り高いローマ帝国第二の都市に霊的な神の言葉が響き、参列者の霊魂を打った。 聖母はこの最初の集会の間のみ男装をされた。すなわち、違ったイエスがそこにいた。性が違い、手足に釘の傷跡が無いほかは、それは確かにイエスなのだった。集会を重ねるうちに、参加者から「狂気」が消えあるいは薄らいで、神の国が出現していた。精神構造の変化は、日常の言動、立ち居振る舞いにも作用せずにはおかず、彼らは「クリスチャン」と呼ばれるようになった。 違ったイエスの言葉が会場に響き、人々が全身全霊でそれを聞こうとする時、クレオパとルカとは「お互いの心が内に燃えた」のであった。これが聖霊降臨の第四段階となった。 |
| (5)聖霊降臨の第五段階、ローマ教会にて完結 |
| パウロのユダヤ人居住区の人々へのイエス・キリストは成功したとは言えなかった。彼は律法による義から信仰による義を説いたが、その証(あかし)としての割礼無用にこだわった。これは異邦人への宣教の拡大を意識していたのかもしれないが、かえってユダヤ人の反発を買うことになった。ユダヤ人というのは律法そのものなのである。 律法とは、捕囚後に編纂(へんさん)された文書のうち、「出エジプト記」、「レビ記」、「民数記(みんすうき)」、「申命記(しんめいき)」の四書のことである。エジプトから脱出した物語の中に、律法すなわち神から与えられた掟(おきて)が書いてある。それは人が決めたものではないゆえに神聖なものとされた。「殺せ」と書いてあれば、人々は躊躇(ちゅうちょ)無く、公衆の面前で、その違反者を石で打って殺した。また掟の中でもっとも重要なものは、アロン家とレビびとの扱いに関するものである。アロン家は祭壇の運営を務め、大祭司として、「罪のゆるし」を乞う祭を行う権能を有する唯一の家柄とし、その期間は永代に及ぶ。また、民のさまざまな奉納物の一部は、アロン家とレビびとの所有となり、神事以外の職業には従事せず、軍務にも服しないことも規定されている。 だが、これは人の都合で形骸化(けいがいか)したものも多い。たとえば聖母子の時代、ヘロデはローマ軍の後ろ盾(だて)で大祭司一族を掃討し、ユダヤの王となったが、彼の滅ぼしたのはマタティヤ一族が名のっていた大祭司であり、神事ではなく実質ユダヤ人の王だったのである。マタティヤ一族はレビびとであり、軍役の義務はなかったが、アンテオケのギリシャ系王朝の圧迫に武力で抗し、自治権を勝ち取ったのである。イエスから100年ほど前のことである。だから、マタティヤ一族が主筋の大祭司を名のったのは律法違反である。マタティヤ家とアロン家とは関係ない。 ヘロデはマタティヤ一族を掃討したが、その時、幼子までも徹底して殺した。これがマタイ書のヘロデによる幼児虐殺のアイデアである。そして、「大祭司」職にアレルギーを持つヘロデは、アロン家の一族も滅ぼそうと考えた。それが、マリヤさまとユダ族との婚姻の主因となったと筆者は考えたのである。 パウロの宣教をうかがう最後の記述は「使徒行伝」であり、パウロのローマでの様子でしめくくられている。夢にまで見たローマでの宣教であったが、彼のイエス・キリスト宣教は、ユダヤ人に受け入れられなかった。すなわちユダヤ人居住区にキリスト教会が建つことはなかったのである。 一方、クレオパが主導し、ローマの貴族たち、解放奴隷たち、市民たちを招いて開いた集会は成功した。集会では、賛美があり、文書が朗読され、違ったイエスと女性たち、ペテロたちが証言した。そしてアラム語は参加者がわかる言葉に同時通訳された。聖母子思想は、特に貴婦人たちの支持を受けた。貴族の館では、解放奴隷たちが、奴隷たちにその話をした。文書が写本されて貴族に配られた。その中にはパウロの文書もあった。聖母子のキリスト教思想は奴隷たちの間に急速に拡大した。 だが、その思想が人々の間に拡大すると、政治利用する者が現れる。その名前でテロを起こし、人々を扇動(せんどう)した。治安維持が当局の手に余ることになり、ついに「禁教」の勅令が発布されるまでになった。ローマには、ギリシャから持ち込んだ「ローマの神々」があったが、占領や属州にした人々の宗教には寛容であり、彼らの神を拝む自由はあった。だが、キリスト教の信奉者は、民族や国家を超えていた。その拡大は予想できないと思われた。だからこそキリスト教は皇帝にとって危険な思想と思われたのであった。 そして300年が過ぎた。「キリスト教の禁教」は依然として有効であった。それというのも、誰もそれを取り消す新たな勅令を発布しなかったからだった。水面下ではキリスト教が着実に勢力を伸ばしていた。禁教のゆえに公の集会が開けず、そのため「キリスト教」とは名ばかりで、さまざまな思想のグループがあった。しかし、「苦杯と十字架」による狂気からのあがない、それを基(もとい)とする勤勉、主従関係などの実践は、ローマ市民に蔓延(まんえん)するモラル低下と廃頽(はいたい)の中に輝いていた。 4世紀、コンスタンティヌスがローマ皇帝となった。彼がどういういきさつでキリスト教に目をつけたのかは定かでないが、聖母子思想のキリスト教徒の生活態度に接する機会があったのであろう。それは人が頭で考えたものでも、実践までに修行を要するというものでもなく、信じればただちに実現する、いわば現世ご利益(ごりやく)の宗教と思われた。 ローマの神々は皇帝や貴族のためのものであり、市民にご利益のあるものとは言えなかった。聖母子信仰は、ローマの各階層に着実にその信徒を確保していた。そこに、ローマ市民が範(はん)とすべきものがあると思われた。禁教を解いても彼らが政治利用される恐れはないというよりもかえって彼らが政治の安定に寄与するのではないかと思われた。 すなわち、キリスト教容認の新たな勅令が発布された。それはミラノでコンスタンティヌス帝が口にした瞬間から有効になったのである。キリスト教は陽(ひ)のあたる所で公に活動ができるようになり、聖母子の聖堂が建設された。 コンスタンティヌス帝主導のもとに会議が開かれ、キリスト教思想の代表はローマ司教と定められた。教皇である。皇帝はキリスト教に関し、教皇だけと話をするのである。哲学者は議論を喜ぶが、皇帝はそんな無益なことはしない。政(まつりごと)には、無駄話は時間の浪費が無能につながる。 また、さまざまな思想文書の統合と廃棄が求められた。コンスタンティヌス帝の権力の下に、新約聖書の文書確定作業が進められた。それらは巻物に写本された。原本となるものであるから、挿入や引き抜き、ページの入れ替わりなどの事故を防ぐためである。そして、選定からはずされた文書、各自が自宅に持っているものもすべて廃棄・焼却処分となった。それには厳罰がともなった。こうして「新約聖書」が誕生した。それはラテン語で書かれており、特別な人にしか読めなかった。また、予備知識無しには読んでも信仰的に理解するすることはむずかしい。 「新約聖書」はルカ文書による聖母子信仰に帰する。しかし、相反するようなものや哲学的、大言壮語の文書も排除せずに容認された。聖母子は諸思想の上に輝くべきものであるはずなのだ。エジプトのアレキサンドリヤ教会は「智」を誇っていた。641年にエジプトがアラーの神兵に蹂躙されるまでのことであった。その智はイスラムの奴隷となり、兵士を治療するための医療技術の向上、新兵器の開発、軍艦の建造に使役(しえき)された。ローマ軍の技術を凌駕するに至ったイスラム軍は北アフリカを席巻(せっけん)、ジプラルタル海峡を渡り、スペイン南部を侵(おか)し、およそ800年間先住民との戦争に明け暮れた。やがてキリスト教の勢力が増し、グラナダ開城でその幕を閉じた。 アレキサンドリヤ教会は、その「智」を誇示し、女や漁師の証言にたよる「無知」を見下(みくだ)した。それが「ヨハネによる福音書」、「ヨハネの黙示録」などのヨハネ諸文書である。また、架空のラザロを登場させ「ヨハネによる福音書」に緊張感をもたらし、ラザロの復活や水をブドウ酒になどのウソで読者の好奇心をあおり、漁師にかえてギリシャ語の弟子を配置し、ピリポをその主人公に仕立てた。また、イエスをべらべらしゃべりまくる哲学者にした。また聖母を並みの女に仕立てるための工夫をこらし、聖母に忠実な女性、マグダラのマリヤを聖母の上に置いた。 この書には「苦杯」は書かれておらず、「罪のゆるし」の発想はない。また処女受胎を認めないため、ローマ教会に至る原動力となった、「違ったイエス」のこともわからずにいる。また、エピソードについては、他の3福音書のものを「わざと」くずしてある。 「使徒行伝」には、架空の人物ステパノを登場させたし、伝道者ピリポに超人的なエピソード「宦官(かんがん)の受洗」を与えた。これらはヨハネ文書とルカ文書との歴史的時空の一致をねらったものであろう。単独ではなく、福音書混入させた思想としては、再臨思想がある。それは「ダニエル書」を起源とする終末思想なのであるが、「処女受胎」を無効にせんがための天からの降臨である。ダニエルはハレー彗星を見たのである。その時には空の雲よりもはるか遠くに白く尾を引く異象が見られたがその先端の核は「人の子」のように見られた。 「マタイによる福音書」24章 24-30そのとき、人の子のしるしが天に現れるであろう。またそのとき、地のすべての民族は嘆き、そして力と大いなる栄光とをもって、人の子が天の雲に乗って来るのを、人々は見るであろう。 およそ、ばかげた話ではあるが、人々は「大言壮語」や「大嘘」こそ信じやすいものである。しかし、それらは知的好奇心を満たすだけで、信仰的ご利益(ごりやく)とは無縁である。だからすぐに忘れ去られる。アレキサンドリヤ教会にしてもまじめに宣教という「労働」をするつもりはまったく無い。自分たちはローマ教会の上に立つ存在であることが人々にわかればそれでよいのである。自分たちには知的議論の日々というものがあるのであり、決して暇ではない。 しかし、ペテロを初代教皇においたローマ教会は聖母子を離れなかった。教会は階層制(ヒエラルキ:Wikipedia(ドイツ語:Hierarchie,ヒエラルヒー,英語:hierarchy,ハイアラーキ)で運営され、その体裁を崩すことなく続けられた。 これと間逆がプロテスタントである。この500年間、その教会を発展・維持した教会はひとつもない。泡のように現れてはたちまち消えていった。思想も牧師に属し、死ねばそこで途絶えた。「プロテスタント」という表題だけが一人歩きしているのである。彼らの唯一の一致は「反教皇」、「反聖母子」である。そのため、イエスはいつもあなたと共にいる。いつもあなたを見守っている。あなたを背負っているなどと、神聖を貶(おとし)めることを平気で口にするのである。 今では欲すれば誰でも「新約聖書」を手にすることができる。しかし、「狂気のあがない」が実現した歴史的背景を知るには、日本では、口語訳聖書の他に、バルバロ神父訳の聖書との差分、とくに「マカベヤ書上」を読む必要がある。 また、使徒行伝の続きとして、帝国の解体からイタリヤの分裂と戦国時代を経て再統一までを10人の人物で簡潔に2000年の歴史を表したミチオ書がある。原本の新書本に、その書の人物ゆかりの都市の旅行記、歴代教皇の名前にリンクした歴史年表からなる。 ローマ帝国教会、略してローマ教会、現在ではカトリック教会、地域に依存しない唯一の普遍教会である。唯一聖職者は独身と定められた教会ある。「聖職者独身制」は教会改革の一環として定められた歴史的由緒あるものである。それは聖書の命令でもある。プロテスタントはこの命令を含め都合の悪い部分は読み飛ばす。教会組織は階層制である。トップは教皇であり、教皇はキリスト教思想の統合者であり、その地位は4世紀のコンスタンティヌス帝の御世に定まったのである。 カトリック教会のミサは単純である。パンとブドウ酒による聖体拝領がメインである。聖母子、聖母マリヤが敬慕され、プロテスタントは聖母信仰を省みない。聖母=教皇を連想させるから、信徒がカトリック教会になびくのを恐れるのである。それで、聖母の代わりにイエス・キリストを置き、キリストはいつもあなたのそばにいてあなたのことを思っているなどと言うのである。イエス・キリストは、苦杯と十字架によって、信徒の「狂気」をあがなう、大祭司なのである。狂気はいつでも湧き起こる。その都度わたしたちはイエス・キリストのあがないを求めるのである。そして、その都度、わたしたちは神の国に生き直すことができるのである。「イエス・キリストはあなたの罪のために十字架に架かられました。だからイエス・キリストを信じるだけでよいのです」であれば、イエスはわたしたち個々人にとっての大祭司ではないのである。これがプロテスタントの誤認であり、「あがない」の実感がないのである。「わたしは信仰の薄い者です」などと信徒に言わせてしまうのである。カトリックのミサは単純簡潔であるが、それこそがキリスト教の完成形なのであり、2000年間連綿と続いている原動力なのである。 処女受胎を文盲(ぶんもう)の民衆に信じさせるなど、カトリック教会は「あくどいことを教えている」と、ちょっとした知識人は軽蔑した。1455年、印刷機を発明し、42行聖書を世に送ったグーテンベルクは、「これで人々は真実を知り、カトリック教会の欺瞞を知る」と思った。しかし、それは彼もまた聖書が天からの贈り物であり、イエス・キリストの真実が書いてあると思ったゆえなのであろう。しかし、何度も言うように、聖書は字が読めたからといって、書かれた内容を理解し、「互いの心が内に燃えた」の境地に達することは、ほぼ不可能である。今でこそインターネットが援けになる場合があるが、「智」の海をただようだけの危険もある。へたをすると難破(なんぱ)する。航行の羅針盤と免許を持つ確かなガイドが必要なのである。 聖母子を毛嫌いし、民衆はだまされていると公言した、レオナルド・ダ・ビンチは聖母子をことさらに不細工に描いたが、彼は、聖書が読めず、キリスト教の「キの字」も知らなかったのである。絵画もその仕上げに日数をかけ、ただ飯を食う時間稼ぎをし、それに気づかれてたたきだされたので、彼の完成作品は少ない。その最後はフランスであったが、性病、今で言うエイズのような自画像があるが、その数年後に孤独に息を引き取ったのである。自分を神よりも上だと錯覚するのは、「自分は選ばれた存在」を自認する人の常であり、その最後は往々にして惨(みじ)めである。 ここに説明書を超えた「取り扱い説明書」が求められた。それは自らの「智」からではなく、疑問に対する答として、瞬間的に湧き上がり、書き留めると消えた。そして、処女受胎の顔認証ができた者としてルカが浮かび、彼の文書が証拠に基づくものであることを確信した。そして、その書はカペナウムの主従であり、テオピロとルカであり、最後にエマオ村へのエピソードを置き、その一人の名はクレオパ、これはテオピロの本名であると考えられ、「違ったイエス」の教えを聞いて、二人のお互いの心が内に燃えたのであった。キリスト教会の「取説」は、これを証する。すなわち、聖書は聖母子に帰し、それは「ルカによる福音書」によるのである。あとの文書は、すべてキリスト教世界の広がりであり、参照である。イエスの言葉は、「苦杯と十字架」のあがないを体現した者にこそ有効に作用するのである。 この説明書は、インタ-ネット環境におかれ、日本人による日本人のためのものを、が、その目的であったが、普遍的な部分が我知らず書きとめていたら、それは日本語の枠をこえたものになる。世界中の人が読めるはずだが、それは「たまたま」、偶然に、見たものに過ぎず、宣教には寄与しないであろう。マンガを入れたり、文章を簡潔にしたりして、完成までには、もう少し工夫できると思うが、それでもどれだけ効果があるかは見通せない。 宣教には、その根拠たる教会組織が必要だが、キリスト教思想の統合者は教皇なのであり、修道会の創設を願い出るのが筋のような気がする。それで「ささくら修道会」となんだかそれらしい名前を各々のページに置いた。「いつまでも存続するものは」組織であり、わたしたちはその繰り返しのひとコマを演じるのである。 というわけで、聖霊降臨の順番の話をしていたのだったが、(ささくら修道会としてのだが)、カトリック教会においては、明示的は聖霊降臨は必要なくなった。「苦杯と十字架」による「狂気のあがない」がしっかりと根付き、個々人において神の国が出現し、ミサに集うことで、また聖餐にあずかることで、霊的な働きが、各人の個性の中に強められる。聖霊降臨は、「あがない」によって、その人が神の国にいる状態の時に起こるから、カトリック教会の信徒においては、ミサに参加することが聖霊降臨と一致する。 ここに、聖霊降臨の順番は完結し、それは2000年間連綿と続いているのである。 |
 |
| 戻る |
| 「聖霊降臨の順番」 |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2021/1/22 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 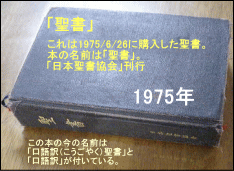 |
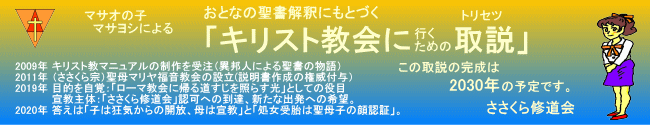 |