 |
| 自費出版:400部、2024/6/18、この本はひとりの孫娘のために書いた。 原稿の脱稿後は、イエス、マリヤと呼び捨てには出来なくなった。 |
| 本書は、イエスさまによる、世々の個々人に内在する「狂気」の消去という信仰の |
| 神父の告悔の信徒に言う 「子よ、あなたの罪は赦された」 こそは、イエスさまに臨んだ苦杯と十字架による罪の贖い。 |
| 1.十字架の御利益 この「十字架」は「苦杯」とセットでなければならない。すなわち、イエスさまは |
| ユダ族ヨセフの子と認知されていたイエスさまの十字架事件が挫折で終わらず、「み民イスラエルの栄光」となるためには、30年の時を遡(さかのぼ)り、イエスさまがアロン家の者であるための「処女受胎」の奇跡を聞かねばならない。それを語れる者は母マリヤさま以外にはない。 そのマリヤさまがイエスさまの落命から三日目に現れた「復活のイエス」であることは幾たびも指摘してきたところである。それは時を同じくして、イエスの一行が投宿していた「巡礼者の宿」を訪問したルカの「顔認証」により、その性による違いの他は「全く同じ」ということが「処女受胎」以外には有り得ないと思われたからである。ルカはローマ軍の関係者として、マリヤさまご一家と同じカペナウムの町にいた。なおかつイエスさまが、ゲリラ主導者の一人として捕えられ、エルサレムまで引かれていって斬首されたヨセフの子としてマークされていた、生前のイエスさまの顔をよく知ってたからである。 「処女受胎」が導くもの、それはイエスがヨセフのユダ族ではなく、マリヤさまのアロン家を継いでいるということである。マリヤさまの家柄については、マリヤさまの親族エリザベツが「アロン家の娘のひとり」と書かれていることの意味を思う必要がある。そのアロン家こそは、律法の要(かなめ)であり、「罪のあがない」を司式する大祭司の規定が書かれており、その業務は代々アロン家に属し、キリスト教の聖書に「旧約聖書」が含まれるのは、実にこの一点「大祭司」の規定の故である。エリザベツの実家のヒントが示すのは、マリヤさまもまた「アロン家本家(ほんけ)」におられたということである。ユダヤの律法は、マリヤさまの身分取りも直さずイエスの身分を示すものである。すなわち、イエスは罪のゆるしを口にしてユダヤ人から睨(にら)まれ、あろうことか、ローマ総督裁可の十字架に露と消えたが、それには深い意味があったのである。 ちなみにパウロは自らの律法の知識を誇ったが、「処女受胎」とアロン家に考え及ばなかったために、イエスの大祭司を導くのに「創世記」のメルキゼデクを持ち出している。アブラハムの時代であり、律法の生まれるはるか昔、ヘブル人(びと)の時代である。パウロは生前のイエスの顔を知らないし、マリヤさまの素顔を見ても何も感じなかったであろう。眼病で視力も落ちていて、母子の顔を同時に見てもルカの驚愕からは程遠かったのである。 さらに言えば、イエスが無条件に大祭司とされるためには、マリヤさまがアロン家の最後の姫さまでなければならない。どうして最後なのか、その事情は話が長くなるし、ここでのテーマではない。 大祭司の仕事は、「罪のあがない」のとりなしであり、「人の罪を獣に移し」その獣の罪をあがなう形で代々のアロン家で行われていた。すなわち獣の「血」を用いてその罪が清められるようにとりなしたのである。しかし、それはあくまで象徴的なものであって、人の罪は人が負うのでなければ、人の罪を「消去」することはできなかったのである。その「人が人の罪を負う」ということは、身の毛のよだつ恐ろしことであり、その恐怖に耐え得る者が待たれたのである。 そして恵まれた女であるマリヤさまが先にお生まれになり、そのマリヤさまから「処女受胎」を通してイエスさまがお生まれになったのである。この女が先にそして男がのシーケンスもまた奇跡である。女が十字架に架けられることはない。男が自分の「成果」を吹聴あるいは宣教することはない。 イエスの親戚であるヨハネがヨルダンに現れ、個々人の「罪」を洗うというパフォーマンスをした。それは「神殿」ではなく、「水のある場所」で行われた。その「個々人」と「場所」を選ばぬところが画期的であり、民衆の心のわだかまりや鬱憤(うっぷん)を晴らすものとなった。 「個々人罪を洗う」という「洗礼者」ヨハネの評判がユダヤ全土に満ちた時、マリヤさまはイエスに「時が来た」と促(うなが)された。そしてイエスが洗礼を受けた時、天から声があって、「あなたはわたしの愛する子、わたしの心にかなう者である」と鳴り響いた。「わたしの心にかなう者」それこそは、イエスに人の罪が負えることの認証であり、恐ろしい言葉なのである。ボーっと読めば、イエスに祝福の言葉がかけられたぐらいにしか思えないであろう。 話が進んで、イエスがゲッセマネの園で「父の杯(さかずき)」に苦しまれた様子を見ていたのは、一同が投宿していた宿の息子である。弟子たちは過越の「メニュー」の御馳走をたらふく食べ、ワインを飲んでいたので、眠りこけるだろうから、マリヤさまはあえて宿の息子にイエスに同行するよう頼まれたのである。果たしてイエスに異変が起こったのをマルコが目(ま)の当たりにし、マリヤさまに報告したのである。「始まった」とマリヤさまは思われた。そしてイエスのために、全身全霊で祈られた。「処女受胎」至る前の「アロン家」のための壮絶な祈りの日々に増して。 これ以降は、十字架への道のりが詳しく書かれている。だが、人の罪の「あがない」のために「苦杯」が十字架に続いていることを知る者はいない。「ヨハネによる福音書」を好んで読む者にはおよそ無縁である。 |
| 1.御利益とは 「ごりやく」とは神仏を信じ、礼拝の態度に応(こた)えるかたちで、人智を超えた利益(りえき)が伴うことを言う。それは心身の充実であったり、収益の増加であったり、「家内安全(かないあんぜん)」、「交通安全」、「世界平和」であったりするであろう。御利益の祈願は人それぞれであり、その緩(ゆる)さのゆえに日本(んほん)では「いわしの頭も信心から」と言われたりする。 キリスト教の「ごりやく」とは何であろうか。それがキリスト教を信仰する原点とならねばならぬ。もちろんそれには国民性もあり、「みんながしているからわたしも」と、もちろんそれでもかまわない。それに「ごりやく」が伴えばなお結構ということである。 |
| 2.キリスト教の場合、その「ある」と「なし」 (1)御利益があるのは、「ルカによる福音書」のマリヤさまを信じる人々である。カトリック教会は本来聖母マリヤさまの教会であるが、「智」のプロテスタント化し、「イエスの母」に封じ、マリヤさまが忘れられる傾向にあるのではないか。それは杞憂(きゆう)に過ぎないだろうか、あまりに当たり前だから口にしないのだろうか、忘れていなければ結構である。 (2)御利益がないのは、「ヨハネによる福音書」が「イエスの母」としか書かぬ、その書の欺瞞(ぎまん)に気付かず、「言葉」を愛するように導かれた人々の場合である。あたかも「ヨハネによる福音書」が「ルカによる福音書」を読みぬいた上で著された至高のものでもあるかのように誘導された犠牲者である。 「ヨハネによる福音書」の目的は、反「ルカによる福音書」であり具体的には、反教皇、それゆえの反聖母マリヤなのである。キリスト教の御利益などにはまったく関心が無く、「智」を自負する、「西方」のローマとは統治者の違う「東方」のアレキサンドリヤの司教たちの著したものである。ローマ帝国は何度も東西に分かれて統治された経緯からもエジプトのアレキサンドリヤには「東方の者」という「地域」意識が強かったのである。 また、その智に汚染され、「神よ、神よ」とか「愛」を連呼する者もこれに等しい。その「智」の呼びかけの向こうにいるのは神ではなくサタンである。サタンは「智」の統合者だからである。神は聖母子を信じる者にこそ、その向こうに垣間見ることができるのである。その気付きも、また御利益である。 |
| わたしにも「ヨハネによる福音書」の時代 1986年の暮れ、わたしはDDR(東ドイツ)のライプチヒに出張した。 |
| 3.聖母子の御利益 |
| キリスト教の御利益それは神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」に集約される。「罪」の意味は幅広いが、この場合は「狂気」、すなわち自分の力(ちから)では制御できないさまざまな「こころのありよう」であり、それこそが人の不幸の原因である。それが解消できることが「あがない」であり、罪が除かれて自由になるのである。その状態こそは活力の原動力が生じているのであり、「生まれ変わった」ような日々が始まるのである。 そのヒントはすべて「ルカによる福音書」にある。ここに杯(さかずき)があるとする。それは霊的なもので、形状は不明である。ただそれは、父がイエスに差し出されたもので、イエスが苦しみ、忌避(きひ)された「もの」が満たされている。そのイエスの口にされた「杯(さかずき)」こそは「苦杯(くはい)」であり、キリスト教の核心である。だが、「智」というメガネをかけた目で福音書を読む者には、その苦杯の重大さが隠されて、見ても見えないのである。それこそは人の罪を「獣(けもの)」ではなく、人(イエス)が負うことの具現だったのである。ちなみにその時杯に満たされた罪は「イエス自身の罪」である。 そしてそれは、処女受胎が成った時、マリヤさまが自覚されたもので、「アロン家最後の男子」に与えられた使命である。だが、人の霊的汚物を自分の体内に流し込むなど、並みの人間にはできることではない。さすがのイエスも忌避されるほどの、身の毛もよだつ、「おぞましい」ことだったである。だから、それに比べれば、十字架による身体のダメージなど大したことではなかったであろうと思うのである。 イエスが「罪」に関わることのできる大祭司であるためには、彼がアロン家(け)最後(さいご)の者でなくてはならぬ。複数のアロン家の男子が存在していたのでは、マリヤさまの「処女受胎」は意味を持たないし、イエスが大祭司になれる必然性はない。だから彼が唯一(ゆいいつ)のアロン家の者であるためには、マリヤさまもまたアロン家最後の姫でなくてはならぬ。そこにはマリヤさまがアロン家の滅亡からただ一人逃れられたという背景がなくてはならぬ。それが、ユダ族のヨセフとの婚姻につながっていくのである。 「ルカによる福音書」22章 苦杯のありさま 22-40いつもの場所に着いてから、彼らに言われた、「誘惑に陥らないように祈りなさい」。22-41そしてご自分は、石を投げてとどくほど離れたところへ退き、ひざまずいて、祈って言われた、22-42「父よ、みこころならば、どうぞ、この杯をわたしから取りのけてください。しかし、わたしの思いではなく、みこころが成るようにしてください」。22-43そのとき、御使が天からあらわれてイエスを力づけた。22-44イエスは苦しみもだえて、ますます切に祈られた。そして、その汗が血のしたたりのように地に落ちた。 これまで軽く読み飛ばされてきたであろう、このエピソードこそは聖母子誕生の核心なのである。イエスが人の罪(霊的汚物)を体内に流し込まれるありさまの描写であり、どんなにかおぞましかったことであろう。このイエスの体内に注入された「罪」を清算するための「十字架」は、イエスさまにとっては、どんなにか清々(すがすが)しいことであったことだろう。それは大願成就(たいがんじょうじゅ)の安堵感がもたらすものであり、その快感が肉体の苦痛を緩和してあまりあったと拝察する。 それを目撃したローマ兵は、驚嘆したことであろう。四方に飛んだ伝令者もその光景に触れていた。それを聞いたテオピロは、「イエスの死の意味」それを知ろうと思ったのである。 ついでに言うと、ゲッセマネの園でのイエスの苦しみの目撃者は、宿の息子のマルコである。その夜、マリヤさまが彼に、イエスたちについて行くことを望まれたのである。そして彼はイエスの苦しむ様子(ようす)を目撃し、それをマリヤさまに報告したのである。 「マルコによる福音書」14章 宿屋の息子マルコ 14-50弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。14-51ときに、ある若者が身に亜麻布をまとって、イエスのあとについて行ったが、人々が彼をつかまえようとしたので、14-52その亜麻布を捨てて、裸で逃げて行った。 |
| 4.出エジプトの律法からカトリック教会のミサまで |
| (1)ユダヤ人と罪 キリスト教思想の源流は古代ユダヤ人社会に息づいていた「律法」にあり、それには「罪」とその「あがない」に関する規定がある。そして「罪」のあがないに関してはアロン家代々の務めとされ、具体的には大祭司の装束を身に着けた者が、その行事を執(と)り行った。 実際、その規定が有効に機能したのは、出エジプトにおける荒野の40年間であったろう。幕屋の神殿の周りに、ヘブル人すなわちイスラエルの12部族が宿営した期間であり、民の離散を防いだのである。 だがそれは、世代交代に要した期間でもあった。エジプトを懐かしく思う者が死に絶え、若者は戦闘員として訓練された。モーセはエジプト王の親族として育てられ軍務に就いていた経験がある。モーセの死後、彼の薫陶(くんとう)を受けたヨシュアが、戦闘員を率いて南北を流れるヨルダンの西側に渡り、パレスチナに侵攻した。そして、十二部族への占領地の配分が完了すると、幕屋の神殿とアロン家は忘れられた。 それが思い出されるのは、バビロン捕囚が終わって荒廃したエルサレムに人々が戻った時である。その人々は居留地でのあだ名「ユダヤ人」を名乗ったが、実質それはユダ族とベニヤミン族だけであった。そこで残りの10部族にも、「ユダヤ人」への合流が求められた。そして、12部族統合の象徴として、ユダヤ人の「神殿」が求められたのである。 それに併(あわ)せて、アロン家が思い出された。アロン家は「罪」に関われるお家柄として機能し始めた。アロン家はレビ人の棟梁の格式があったが、それはある意味忘れられていて、祭司たちがはびこっていた。彼らにとってはアロン家は鬱陶(うっとう)しい存在以外の何者でもなかった。 ユダヤ人はペルシャ王に、自分たちが宗教集団として存続する、自治州の認可を願い出たのである。その嘆願書に添付されたのが「律法書」であり、旧約聖書の原点である。ペルシャ自治州としてのユダヤ人の言語は、ペルシャと同じ「アラム語」であった。 |
| (2)ペルシャ文明のユダヤ地区にギリシャの風 |
| だが歴史は激しく動いていた。アレキサンダーがペルシャを滅ぼしたのである。だが大王は若死にしてしまった。彼の妻子は暗殺されたため、将軍たちは実力に応じて遺領を割譲した。そして、歴史にその名を残した都市がパレスチナの「アンテオケ」とエジプトの「アレキサンドリヤ」である。前者はギリシャ的(てき)エロス、後者はギリシャ的「智」を象徴した。 そのアンテオケの王が近くのユダヤ地域を「エロスのギリシャ」的(てき)風土(ふうど)に変えようと手を伸ばした。ユダヤのギリシャ化が展開された。 これに反発したのがレビ族のマタティヤ親子であり、武力蜂起し「対アンテオケ」の抵抗運動を展開した。長期間の抵抗運動を経て、ついにユダヤのギリシャ化をあきらめさせた。マタティヤの子らは「軍」の司令官の地位を保持したまま、レビ人は王にはなれないこともあって、「大祭司」を名乗った。 大祭司はアロン家の専権事項であるから、レビ族の祭司であったマタティヤ家には、「大祭司」を名乗る資格はなかった。レビ人は本来(ほんらい)軍務と税を免除された身分ではあったが、時代と共に、棟梁がアロン家であることに不満があった。 「王」に匹敵する実力を持ったマタティヤ家(け)は、実力で、棟梁の身分たる「大祭司」を名乗ったのである。これは律法に照らせば僭称(せんしょう)である。だが、誰も文句(もんく)を言う者はいなかった。民全体に、彼らの功績が認められていたからであろう。 だが、彼らは「マタティヤ家」ではなく「ハスモン家」を名乗り、ユダヤの「王」として君臨(くんりん)した。ユダヤは独立国を謳歌(おうか)した。それはローマ軍がパレスチナに侵攻を開始するまでの100年くらいの期間であった。 |
| (3)「神事」と「王たる者」、 |
| ユダヤに、ハスモン家とアロン家の大祭司が存在する時代が100年ほど続いた。ユダヤは事実上の独立国であったが、ローマ軍がギリシャを席巻(せっけん)し、パレスチナに侵攻すると、ユダヤは戦火に包まれた。ユダヤ人は「マタティヤの故事にならい」、各地で執拗(しつよう)に武力闘争を続けた。ついにローマ軍はユダヤ人の戦意の源(みなもと)がハスモン家の大祭司にあることを知った。軍は、改宗のユダヤ人の子であり、ローマに留学したこともあるヘロデを使って、ハスモン家を探らせた。そして、彼から得た情報を元に、一族を根絶(ねだ)やしにした。そしてヘロデの功績を認め、ユダヤ人の王とした。「改宗のユダヤ人(じん)が王に」、これはユダヤ人にとっては屈辱(くつじょく)以外の何物でもなかった。ヘロデは軍人としても有能であった。彼によってユダヤ人の武力闘争は沈静化した。 その30数年後、老いたヘロデは「大祭司」が残っていることを知った。それはアロン家であった。アロン家は神殿で神事しかしない家柄なのだが、ヘロデにはその区別はつかなかった。そこでアロン家も始末することになった。マリヤさまが10歳の頃である。 |
| (4)アロン家のマリヤさまの命運 |
| だがその計画は洩れた。アロン家の当主は恵まれた資質の少女、「この子が男であったら」と思うほどの子を殺してしまうことを惜(お)しんだ。そして、ベツレヘムからエルサレムに通い、神殿の大工(だいく)仕事もしていたヨセフに注目した。彼はただちに、ヨセフの父を祭司の町「エマオ」に呼び、マリヤさまとの婚姻を承諾させた。そして二人をエマオから嗣業地(しぎょうち)のナザレに疎開(そかい)させた。二人につけられた従者たちは、アロン家伝来(でんらい)の聖書、ヘブル語の巻物を運んだ。そしてアロン家一族は自決した。ここにアロン家はマリヤさまを残して滅んだ。 ヘロデの大祭司 この後の「大祭司」はアロン家の者ではない。ヘロデの息のかかった親(しん)ヘロデの祭司たちである。壮年となられたイエスの時代のカヤパらもそうである。 |
| (5)処女受胎の奇跡が呼ぶ使命 ナザレでのマリヤさまの嘆きははなはだ大きかった。嘆きの第一は、婚約者がユダ族であり、「もう、アロン家の子を産めない」、それであった。毎日、身体全体、子宮をも揺るがす、壮絶な祈りが捧げられた。許婚(いいなずけ)のヨセフと従者たちも、ただマリヤさまを見守り、祈るだけであった。そして、ヘロデが死に、アロン家自決の衝撃が収まったころ、マリヤさま12歳のころ、祈っておられたマリヤさまに、「おめでとう、恵まれた女よ」の声が臨んだのである。 12歳になられたマリヤさまは懐妊(かいにん)された。それを知ったヨセフは、結婚の手続きを急いだ。結婚披露のためナザレを出て実家のベツレヘムに向かった。その途中、彼らはマリヤさまの育たれたエマオの町に立ち寄った。そして、同じアロン家の女であるエリザベツを訪(たず)ねられたのである。マリヤさまはエリザベツにことの次第を打ち明けられた。「アロン家に男子が生まれるですって!?」、エリザベツは驚嘆し、マリヤさまを祝福した。そしてマリヤさまもまた、自身の身に起こったことを感謝して言葉にされた。エリザベツは、「アロン家の者」がマリヤさまに与えられることの神意を思った。 「ルカによる福音書」1章 1-46するとマリヤは言った、「わたしの魂は主をあがめ、 1-47わたしの霊は救主なる神をたたえます。 1-48この卑しい女をさえ、心にかけてくださいました。 今からのち代々の人々は、わたしをさいわいな女と言うでしょう。 1-49力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったからです。 エリザベツ自身も老齢ながら妊娠していたからでもあり、マリヤさまに起こった「処女受胎」を信じた。しかし。その秘密は漏れてはならぬことだった。ヨセフの子でなければ、かえって「神を冒涜(ぼうとく)する者」として、ユダヤ人は母子ともに殺してしまうであろう。こうして、まず洗礼者となるヨハネがエマオで生まれ、ベツレヘムでイエスがお生まれになったのである。イエスが十字架の露(つゆ)と消えるまで、彼はユダ族であり、あのヨセフの子であり、ダビデの子孫と思われていたのである。 |
| (6)水で「罪」を洗う者、洗礼者ヨハネ そして30年の歳月が流れた。まず、ヨハネが荒野からヨルダン川に現れ、人の罪を川の水で洗った。ヨハネの母はアロン家の娘のひとりである。その彼が「罪」を語るのは大目にみられた。 そして、ヨハネの名が全土に知れ渡ったころ、イエスが現れた。イエスがヨハネの洗礼を受けられた時、天から声があって「わたしの心にかなう者である」と聞こえた。その情景の目撃者は母のマリヤさまでなくてはなるまい。「心にかなう」の真意は、「人の罪を負える」ということである。その手段は未(ま)だわからないが何と恐ろしくおぞましい言葉であろう。人の霊的汚物が、犠牲となる者の心にからみつくのである。並みの者なら、霊的おぞましさに、発狂(はっきょう)してしまうであろう。 |
| (7)タイム・リミットの「 イエスはその年の「過越の祭」に向かって「アロン家」の仕事をスタートされた。弟子を持ったのは「宣教」のためである。弟子たちは、ユダ族のイエスの弟子になったのであり、イエスがダビデの位に就いたら与えられるであろう「栄誉」を夢見たのである。彼らが「誰が一番偉いか」を議論していたのは、大臣のイスをめぐる「夢」を描いていたからである。 一方(いっぽう)、イエスは無防備ともいえる、「あなたの罪はゆるされた」を口にした。だが、ヨハネと違ってイエスはユダ族である。祭司以外は口にしてはならない「罪」を口にしたことで、律法違反の疑惑が生じたのである。そのような異端者は「死罪」に定められなければならない。イエスは「死」に向かって行進することになったのである。それを理解しておられたのはマリヤさまのみ。マリヤさまは顔を隠し、奉仕の女たちに混じって奉仕しておられた。マリヤさまは、イエスがカペナウムで働いた賃金から、生活費を除いて蓄えられていたのである。この日々のためである。 |
| (8)苦杯、イエスに臨む霊的汚物の注入 そしてついにその時が来た。人が人の罪を負う瞬間が。それを目撃したのは宿屋の息子のマルコである。夜になれば女がエルサレムの城壁の門を出入することは禁止されていた。そこでマリヤさまはマルコにイエスから目を離さないように頼まれたのである。宿屋を経営しているのはレビ人の女主人であり、マリヤさまは彼女の主筋にあたられるのである。一行が投宿したのは「巡礼者」の宿とするのが妥当である。宿なら、多人数の過越の食事(羊の焼肉がメイン)も問題ない。 夜が更(ふ)けていったがマリヤさまと女性たちは寝ずに起きていた。そして、夜更(よふ)け頃、裸のマルコが帰ってきた。続いて弟子たちも帰ってきた。宿に緊張が走った。マリヤさまはマルコからイエスのようすを詳しくお聞きになった。イエスの異様な苦しみが語られた。 それこそは「人が人の罪を負った瞬間」であり、アロン家の者に臨んだとマリヤさまは思われたのである。イエスの心に人の「罪」、言い換えると霊的汚物がからみついた。その不快感はおよそ人智を超えたおぞましいものであったろう。イエスから「聖霊」が隠され、「霊力」が失せた。「アロン家」の最後の男子であり、大祭司の資格を持つイエスに「苦杯」が成就したのである。 (9)イエスがあがないをとりなすステップへ イエスの受けた「苦杯」は次のステップを要求した。それは「血」すなわち「命(いのち)」そのものによってあがなわれねばならず、時をおかず実行される必要がある。それはイエスの命をもってあがなわれるということなのだ。具体的にはイエスの死刑の執行である。 園(その)で捕(と)らえられたイエスの罪状は、自分を神の子としたことだった。神を冒涜したという、ユダヤ人ならではの罪状である。しかし、未明に開かれたその宗教裁判では、イエスの死罪が確定したものの、実行されなかった。彼らはエルサレム市民にも人気の高いイエスを自らの手で殺せば、暴動が起こるのは必須(ひっす)で、エルサレムが大混乱になると恐れたのである。 そこで彼らはその役を普段は軽蔑しているローマ総督に押し付けようとたくらんだ。朝早くではあったが、ローマ総督の館にイエスを連れて行き、「死刑にされるべき者を捕(つか)まえた」と訴え出た。総督ピラトは、ユダヤ人たちが早朝の裁判を要求したので、どんな重罪人(じゅうざいにん)を連れてきたのかと思ったが、囚人を見た彼は腹が立った。どう見てもイエスが訴状通りの凶暴犯には見えない。「これはイエスと呼ばれている男ではないか。ユダヤ人の奴らはわたしにこの男を殺させようとしているのだ」。 |
| イエスの出身地がガリラヤであると聞いたピラトは、祭りのために上京していたヘロデ(二代目)にイエスを引き渡した。ヘロデもまたユダヤ人のたくらみとピラトの魂胆(こんたん)を見抜いた。皆の前でおどけて見せ、イエスに王の上着を着せて、ピラトに送り返した。ピラトはがっかりした。 だが、何とかイエスを放免しようと試みた。(1)まず、彼の身体にムチを打たせた。身体がボロボロになったイエスを見れば、いかに頑固(がんこ)なユダヤ人でも、イエスを哀れに思うに違いない。ピラトの考えは甘かった。ユダヤ人たちは哀れむどころか「イエスを十字架につけよ」と本音(ほんね)を叫んだのである。だが誰知ろう、「十字架」それこそは、イエスの望むところだったのである。 (2)だが、ピラトは次の一手として「祭りの恩赦(おんしゃ)」をイエスに適用すると宣告した。しかしそれこそはユダヤ人の思う壺であった。ユダヤ人は叫んだ、「バラバを許せ。イエスを十字架につけよ」。それはイエスを投獄せずに即処刑できる極めて効率的な始末の仕方である。 「十字架」という残酷刑は、「見せしめ」の目的を持っている。だから、祭の当日に架けられる三人の罪状はエルサレム市内に公示されているのである。諸国から祭のために上京しているユダヤ人たちにも見せるためである。だから、ユダヤ人たちはバラバが中央の十字架に架けられることを知っていたのである。 ローマの法廷としては、本来ならイエスはまず投獄され、その罪状が公示される必要がある。イエスが十字架刑に相当するようなローマに対する扇動があったといった政治犯としてである。 だが、ピラトは根(こん)が尽き果てた。バラバの十字架にイエスを架けることになってしまった。ピラトにとっては予想外の展開であり、ユダヤ人にとっては思う壺(つぼ)となった。「過越」当日の活動は日没と共に停止され、安息日へと続く。活動の解除は三日目の日の出(朝)になる。 かくしてイエスは刑場に引かれて行った。だが、ムチ打ちによる肉体のダメージと出血で、刑場までの歩みもままならない状態であった。2022/6/23、6/24 |
| マリヤさまと奉仕の女性たちは、イエスの裁判を見守り、刑場までの歩みも見守った。ピラトが懸念した「騒動」は起こらなかった。イエスは「驚くべき平安」を保っていた。彼の表情は何と穏やかであることだろう。それが十字架にかけられる者の態度とは信じられない。十字架のイエスには平安があった。霊的汚物が悪血(おけつ)と共に流れ出ていく快感は何ともいえない。肉体が引き裂かれる苦痛は、霊的快感によって相殺されているのである。「獣」ではなく「アロン家の者」たる自分が人の「罪」を負い、流す血によって、命である血によって、「罪のあがない」が実現する、その使命の達成感もあったであろう。「母よ、あとはおまかせする」。そして、ムチのダメージのためにイエスは三時間ほどで息絶えた。事は成った。 イエスの死はエルサレム市民にとっては挫折を意味した。ヘロデにとってかわるユダヤ人の王となる資質をお持ちだったイエスがローマ総督の裁定で処刑された。ユダヤ人の望みは消えた。 |
| (10)イエスの死がスタート・ライン 「イエス処刑」の伝令が四方に飛んだ。カペナウムの兵営にもその日の遅くに早馬がついた。そして集まった将校に伝令が読まれた。そのあと伝令者は自分の感想を述べた。それは囚人の態度であった。世の常の囚人とは異なり、その表情にはむしろ「安心」が見られ、十字架に至るまでも「従順」であった。それは何かの達成感ゆえであろうと思われたと言うのである。その言葉を聞いた者のひとりにクレオパがいた。そして思った、「イエスの死の意味」それが知りたいと。 |
| 彼はルカにそれを伝えた。翌日は安息日でありユダヤ人は旅行できない。イエスの処刑から三日目の朝、ルカは主人の友人である長老を伴い、部下の操縦する馬車でエルサレムに向かった。そしてその日の午後にかの「巡礼者の宿」に着いたのである。イエスの母に面会したいと女主人に伝え、二階の広間にあがると弟子たちがいた。その弟子たちに話をしていた「男」が振り向いたのを見たルカは絶句した、「イエスだ!?イエスが生きていた。これは一体??」。 |
| (11)「顔認証」が導く「処女受胎」 この時のルカの驚きが、世に「処女受胎」を現すのである。イエスはカペナウムではローマ軍にマークされていた。あのヨセフの子だからであった。だからルカはイエスの顔を良く知っていたのである。しかし、その母の顔を見るのは今が始めてであった。「処女受胎」それこそはイエスがアロン家の者であることを証(あかし)できたのである。 |
| まさに神意、ユダヤ人の「律法」の中に、異邦人が介入した一瞬であった。そして、ルカの報告はクレオパの「機は熟した」とするところとなり、マリヤさまの異邦人への伝道が実現していくのである。それこそは、ローマ教会すなわちカトリック教会の初めであり、神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」に集約され、ミサが連綿と続いてきたのである。2000年に亘(わた)るミサの継続、それもまた奇跡であろう。 マリヤさまとクレオパの一行はアンテオケから出発し、ローマへへと向かったが、彼らを先導したのは「十字架」であった。「十字架の先導する一行(いっこう)」、極刑のシンボルを掲げたパフォーマンスは、ローマ市民に特段の宣伝効果を発揮した。 (12)「禁教」は扇動者の政治利用が原因 だが弊害もあった。十字架はテロリストたちにも利用され政治不安の元凶ともなった。これがキリスト教の禁止の原因になるのである。 (13)教会はピラミッド型組織 信徒が増えるにしたがって形成される教会組織は、クレオパが軍人であったことから、自(おの)ずとピラミッド型になった。しかし、エジプトのアレキサンドリヤは、ローマ教会の風下に立つことを嫌った。それは、ローマの版図(はんと)が東西に分割統治されていたことと、アレキサンドリヤがギリシャ系王朝の都であったことに起因する。彼らの多くは「ギリシャ」を意識する哲学者であった。だから、ローマ教会のあがめる「女と漁師」にがまんならなかったのである。 それは、彼らが「苦杯と十字架」による「罪という名の狂気」のあがないが、「知恵」や「哲学」によらないことを理解できなかったからである。また、「ギリシャ哲学」の誇(ほこ)りのゆえに、「苦杯と十字架」の受け入れを忌避(きひ)したのである。アロン家の「旧」と「新」、「獣」と「人」を理解するなど思いのほかである。 (14)「ヨハネによる福音書」は「イエスの母」と 彼らの反ローマ感情は、「ヨハネによる福音書」を著すことで、「ルカによる福音書」を根拠としたローマの上に立ったと溜飲(りゅういん)を下げたのである。彼らは、マリヤさまを「イエスの母」に留(とど)めてその名を封印した。そして、念には念を、「マリヤ」という名は、マグダラの女とラザロの妹のものとし、詳しいエピソードを創作した。その二人の女はしっかりしている一方(いっぽう)、「イエスの母」は弟子に引き取られるなど「頼りない女」にしたのである。「ヨハネによる福音書」しか読み聞かされることがなくなったエジプトの人々は、聖母子のイメージを、エジプトの女神であったイシス母子に重ねたのである。 (15)ローマ司教(教皇)と新約聖書 その後、四世紀に至ってコンスタンティヌスが皇帝となり、「禁教」そのものを解いたためにキリスト教も表立って活動できることになった。また、キリスト教思想の統合者はローマ司教と定められ、キリスト教思想の文書は整理・統合され「新約聖書」となった。それ以外の文書は皇帝による厳罰を伴う焼却処分となった。「新約聖書」が単独峰なのはそのゆえである。この時、「ヨハネによる福音書」が加えられ、また使徒行伝には「伝道師」ピリポとそれを誘導するステパノが挿入された。文書の選考委員には「エジプトの哲学者」たちもいたからである。 (16)東都コンスタンティノープル コンスタンティヌス帝の死後、キリスト教がローマ神に代わって国教となった。そして、帝国の版図はまたも分割統治されることになって、東の都はギリシャの漁村ビザンチウムに造成した城塞都市「コンスタンティノープル」になった。ローマから司教が派遣されたが、アレキサンドリヤからも哲学者たちがやってきた。ローマからの司教たちは「ギリシャ哲学」にひれ伏した。コンスタンティノープルは「ヨハネによる福音書」の教義に染まるのであるが、それには御利益(ごりやく)はなく、言葉の彷徨(ほうこう)があるのみである。だが、ミサでもない「壮麗な儀式」に重点をおくご用教会となったので、人々には別にどうのこうのと言う理由はなかったのである。 (17)ほっかむりの名前の無い女 そういうわけで、「東」の聖母子は、ほっかむりの女が「イエスの母」であり、名前は無く、不気味である。ただその特徴的なコスチュームは、それが東の女であることを象徴している。シチリヤの聖堂もベネチヤのそれも、その同じコスチュームの肖像があり、反教皇を象徴している。「東」は反教皇の元祖であり、権力者のご用教会でいてくれるから、反教皇の権力者が便利に使うのである。 つまり、「東」のそれは、キリスト教の御利益(ごりやく)を個々人に及ぼすためではなく、権力者自身のために、反教皇の道具として使われたのである。 キリスト教の真髄は、アロン家の聖母子のもたらした「人の罪」を「人(ひと)すなわちアロン家の者」がその身に負い、流した血によってあがなわれたことにある。その御利益はいつの世の個々人に及ぶ。すなわち、自らは消去できない狂気、「心の汚物」を消去できること、そして「み心にかなう人」となって「平和がある」に至るその御利益のことであり、それが神父の言う「子よ、あなたの罪はゆるされた」なのである。その教義の守護者が教皇である。 |
| (18)ミサ それは、カトリック教会が連綿と続けてきたミサにあり、それに集うことが「愚直な信徒」に与えられる一週間の恵みである。ミサでのパン(とぶどう酒)はイエスの身体を記念するものであり、それが哲学ではなく実在したアロン家の母子と弟子たちの「証言」によることを子孫に伝えるのである。旧約では「過越の祭」であろうか。それは「出エジプト」が実際にあった出来事であることを子々孫々に伝えるものである。ミサは、「哲学者」の作り話を警戒せよということでもある。 |
| (19)取説が叫ぶ カトリック教会が「愚直さ」と「マリヤさま」とを忘れ、哲学に向かえば、次の3000年を待たずに崩壊への道をたどるであろう。自分の考えを恥ずかしげもなくべらべらしゃべる哲学者がのさばれば、それは早まるであろう。わたしが何とはなしに「キリスト教の説明書」作成に着手し、10年を超える歳月の中で「カトリックの取説」への道を辿(たど)っているのは理由のないことではないと思う。この「取説」は石ころの叫びである。その石ころは「思うがままに」書くことをゆるされていると自認している。2022/4/18、6/24 |
| 次へ |
 |
| 2016年のイタリヤ旅行「バチカン」 |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2022/5/12、5/19、5/25、6/22、6/24 2024/8/17 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 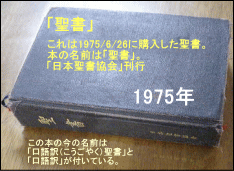 |
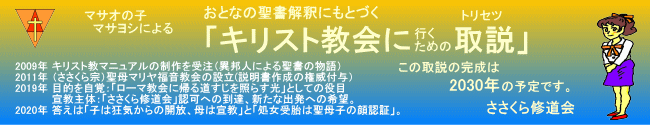 |