| 1.序文 「苦杯と十字架」による「狂気」という名の罪の「解消(あがない)」を、今を生きる人々に実現したことこそは、キリスト教の根幹である。それはアロン家最後の姫君に臨んだ「処女受胎」が、マリヤさまにアロン家の最後にふさわしい「人が人の罪を負う」を自覚させ、女子(じょし)にはできないその「仕事」を、自らの胎から生まれ出た男子(だんし)に託されたのである。しかもそれは「智」を用いて子を導いてはならなかったのである。ただ、成り行きと結果を見届け、それが成った場合には、証言に基づく「宣教」を行うことが、マリヤさまに引き継がれる「仕事」となったのである。 「創世記」1章 1-27神は自分のかたちに人を創造された。すなわち、神のかたちに創造し、男と女とに創造された。 この人とはイエス・キリストとマリヤさまであろう。お二人(ふたり)で、俗人が生まれながらに内在の「狂気」をあがなう道を、律法のうちに、拓かれたからである。俗人とは2章以降の男女である。 カトリック教会の神父の告悔(こっかい)の信徒に言う、「子よ、あなたの罪はゆるされた」こそは、キリスト教の御利益(ごりやく)だったのである。「だった」というのは、それがアレキサンドリヤの「智」に毒されて疎(うと)んじられ「過去形」となっているのではないかとの危惧(きぐ)があるからである。 |
| 2.満月の園での出来事 満月が照らす夜の園でイエスが苦しまれた様子が書かれている。その時イメージされた「杯(さかずき)」こそは、人の「罪」の受け皿であり、アロン家の大祭司イエスはそれを飲み干さねばならぬ。それこそはイエスに人の罪が流し込まれる手段であり、イエスが人の罪を負ったことになるのである。その苦しさは、おぞましく、耐え難いものであったであろう。 それまでアロン家の大祭司は代々「獣」に「人」の罪を移していた。しかし、本来「獣」に「人」の罪を負わせるのには無理があった。イエスはアロン家最後の大祭司として、自らに人の罪が流し込まれるおぞましさに耐えたのである。 |
| 3.最初の杯にはイエス自身の罪 この最初の「杯」には誰の「罪」であろう。それこそはイエス自身の「罪」でなければならない。この最初の「杯」に入れられたのがイエス自身の罪であることが重要である。イエスは生まれながらに罪はなかった、とするのは誤りである。罪がないということは人と関わる能力がないことを意味するからである。なぜなら、罪は人との関わりの中で生まれるものだからである。 そして罪を負ったイエスは、時をおかずに屠(ほふ)られる必要がある。 |
| 4.ユダヤ人の イエスはイスカリオテのユダの先導でユダヤ人に捕らえられ、宗教裁判にかけられて「有罪」となった。祭司で無い者が「罪」のあがないに関する言動をしたという「律法違反」の罪であり、その量刑は死刑である。だが、ユダヤ人は自らは手を下さず、ローマの十字架に架ける策を練った。 多くのユダヤ人でにぎわう「過越の祭」で、三人に十字架を執行する旨の布告がされていたが、バラバが中央の十字架に架けられることになっていた。ユダヤ人はその祭には「恩赦(おんしゃ)」が認められることを知っていたので、バラバに恩赦を求め、その十字架にイエスを架けることを目論(もくろ)んだのである。もしイエスが自分たちの訴えている「自分を神とし皇帝を否定する者」として死刑の量刑が下ったとしても、公示のために「投獄」されてしまっては一大事である。イエスが王にと期待するユダヤ市民たちが黙っていないだろうからである。エルサレムは大混乱に陥るだろう。彼らにとってイエスはユダ族であり、またダビデ王の子孫と信じているからである。 |
| 5.ローマ人ピラト総督 総督のピラトはユダヤ人たちの訴えで裁判の席についたものの、イエスがそのような悪人であるとは思えず、ムチで打ったのを初めとして、三度も許そうとした。しかしユダヤ人たちの「叫び」が勝った。ピラトはバラバを許し、イエスとあとの二人をユダヤ人に渡した。「好きにしろ」というわけである。ルカは総督ピラトがイエスを殺したのでは「ない」という立場をとっている。イエスを十字架に架けたのはユダヤ人なのだ。そしてそのユダヤ人はイエスが何者かを知らないのだ。 「ルカによる福音書」23章 アロン家の悲願「獣から人へ」 23-32さて、イエスと共に刑を受けるために、ほかにふたりの犯罪人も引かれていった。23-33されこうべと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも、ひとりは右に、ひとりは左に、十字架につけた。23-34そのとき、イエスは言われた、「父よ、彼らをおゆるしください。彼らは何をしているのか、わからずにいるのです」。 この「彼ら」とはユダヤ人(祭司たちのこと)である。 こうして、ユダヤ人はバラバのものだった十字架に、自身の罪を負ったイエスを架けた。ルカは「彼ら」と記して暗にイエスを十字架に架けたのはローマ人ではないことを示した。 |
| 6.十字架の情景 自身の「罪」を自らに負う、それが成ってこそイエスは「罪なき者」になるのだ。自らの体内から汚血(おけつ)が滲(し)み出ていく、その爽快感は、「苦杯」をあおった時のおぞましさに倍加する。十字架に架かったイエスを見上げたものは、その光景に絶句した。そこに見られたものは、言語を絶する苦痛にあえぎもだえる者の姿ではなく、何かを成し遂げた者の見せるおだやかで満ち足りた表情であったからだ。 その時、全地は暗くなったと書いてある。イエスにまつわる三度目の天の異象であり、これもマリヤさまの記憶であるとともに、その異象はかの百卒長主従のカペナウムでも目撃されたはずである。皆既日食であろう。ゴルゴダの丘に立つ三本の十字架のシルエットは、想像するだけでも「神々しく」そして胸をうつ。 「ルカによる福音書」23章 真昼の闇に立つ十字架のシルエット 23-44時はもう昼の十二時ごろであったが、太陽は光を失い、全地は暗くなって、三時に及んだ。23-45そして聖所の幕がまん中から裂けた。23-46そのとき、イエスは声高く叫んで言われた、「父よ、わたしの霊をみ手にゆだねます」。こう言ってついに息を引きとられた。23-47百卒長はこの有様を見て、神をあがめ、「ほんとうに、この人は正しい人であった」と言った。 「聖所の幕」とは神殿の至聖所(しせいじょ)の前にあるもので、その幕の中に入れる者は大祭司だけである。その幕が「まん中から裂けた」と表現されているのは、まさに大祭司イエスがそこに入ったことを意味している。イエスが死に場所をエルサレムとしたのは贖罪の儀式は大祭司が神殿で行われなければないからである。 このゴルゴダの丘にはローマ軍はいない。神をあがめたのは、カペナウムの百卒長である。この神々しく荘重な場面に、ルカは主人クレオパを登場させたのである。 |
| 7.イエスの「墓」の考察 「ルカによる福音書」23章 23-48この光景を見に集まってきた群衆も、これらの出来事を見て、みな胸を打ちながら帰って行った。23-49すべてイエスを知っていた者や、ガリラヤから従ってきた女たちも、遠い所に立って、これらのことを見ていた。23-50ここに、ヨセフという議員がいたが、善良で正しい人であった。23-51この人はユダヤの町アリマタヤの出身で、神の国を待ち望んでいた。彼は議会の議決や行動には賛成していなかった。 23-52この人がピラトのところへ行って、イエスのからだの引取り方を願い出て、23-53それを取りおろして亜麻布に包み、まだだれも葬ったことのない、岩を掘って造った墓に納めた。 23-54この日は準備の日であって、安息日が始まりかけていた。23-55イエスと一緒にガリラヤからきた女たちは、あとについてきて、その墓を見、またイエスのからだが納められる様子を見とどけた。23-56そして帰って、香料と香油とを用意した。それからおきてに従って安息日を休んだ。 「墓」は無縁仏のものでない限りは所有者がいるであろう。無断で使うことは許されない。では、その「岩を掘って」とはいかなる理由でそこにあったのか。 そのヒントは「人の子」の再臨思想があるであろう。当時その「人の子が来て世を改める」という思想は、巨大彗星の再臨を思わなければならない。それが今のハレー彗星だとして、75年周期で太陽に接近するそれは、核が有機物質であるから毎回蒸発して白い尾を天に刷(は)く。今ではハレー彗星が来ても肉眼で見えるかどうかの大きさであるが、2000年前なら、26回前であるから、彗星と地球と太陽との位置関係によっては、相当巨大な核が見えたに違いない。天の雲の先端の部分、その核の中に、影が見え、それが人にも見えたであろう。それが「ダニエル書」由来の「人の子」である。今回は、その人の子が全地を改めために来るのである。 信仰者は、その最後をエルサレムで迎えようとしたのである。だが、運がよければ神の御慈悲にあずかれるかも知れない。そう考えて岩を掘って「室」を造ったのである。いわばシェルターであり、共用施設であり、複数造ったとするのが自然であろう。それの入り口は人が身をかがめて入れる狭いものだったから、シェルターの機能にも合致する。 だから、それは誰かの許可を得ることなしに一時利用できたのである。それはそうとしても、岩の穴は「園」にあり、樹木で隠されていて、その存在を皆が知っているわけではなかった。いわば「会員」が知っていたのである。アリマタヤのヨセフはその「会員」であったとしたい。 |
| イエスの墓は「シェルター」 |
| この日は「過越」であって、日没(1日目)から次の安息日(2日目)を経て、翌朝の日の出(3日目)までは、一切の「労働」が禁止されている。それが「おきてに従って安息日を休んだ」なのである。 |
| 過越と除酵祭の関係 |
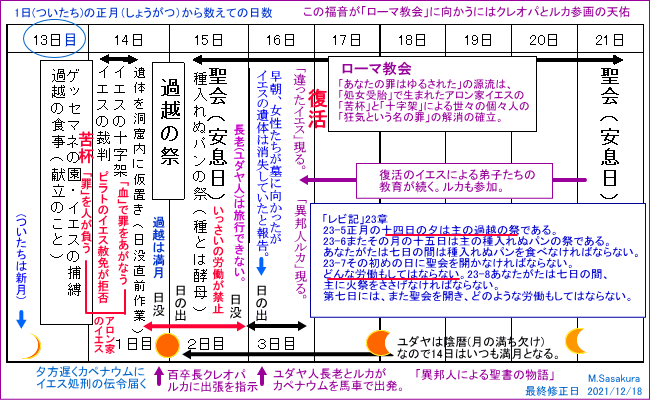 |
| まさに、イエスは果たすべきアロン家の使命を成し遂げ、永遠の安息に入られたのである。だが、これは福音書に書かれたことからの展開であり、その「成就」をご確認されたのはマリやさまお一人(ひとり)である。世間はユダ族のヨセフの子、イエスは死んでしまったのである。民衆の「イエスが王に」の期待は消えてしまったのである。使徒たちの失望はいかばかりであっただろうか。 |
| ピラト総督の伝令が四方のローマ軍駐屯地に飛んでいた。ユダヤ人以外には安息日は関係ない。その日の夜遅く早馬がカペナウムにも到着した。そしてイエスの十字架事件が伝えられた。イエスを実際に十字架に架けたのはユダヤ人だが、騒動が起こらぬようにとのお達しであった、そして最後は「エルサレムは平穏である」と結んであった。 将校たちがそれを聞いたが、最後に伝令者は自分の感想を述べた。「今度の十字架では驚くべき光景を目にした。太陽が光を失って全地が暗くなって、三本の十字架のシルエットが浮かび上がった。真ん中の男の顔は終始穏やかであり叫び声をあげたりはしなかった。それどころかとりなしの言葉を口にした。それにつられたのか、他のふたりもおとなしかった。十字架が見せしめになっていないなんて初めてだ」と言った。 それをクレオパは心して聞いていた。そして、ルカに指示して、その伝令者を自宅に呼び食事と寝床とを与えた。ルカには安息日明けにユダヤ人の長老と共にエルサレムに行くようにと言った。イエスの死の意味を知らねばならぬと思ったのである。はからずも異邦人のこの決断が、イエスがアロン家の大祭司であったことを世の人々が知るきっかけとなるのである。 |
| 「処女受胎」こそはイエスが滅んだはずのアロン家に生まれた唯一の者であり、それゆえに生まれながらに大祭司の身分を持っていた。そのイエスが、公生涯に先立ち、洗礼の儀式を受けられたところ天から声があった。「わたしの心にかなう者である」と。そしてイエスは神の国を説きながら、人々の悩みを癒しながら、過越の祭りに間に合うような日程でエルサレムを目指された。代々のアロン家の大祭司は、人の罪を獣に移し、その獣をほふって得た血で、嘆願者の罪を贖(あがな)う儀式を執り行った。だが、イエスの場合、その子がアロン家の者となることはあり得ない。彼は「ユダ族」と世間には認知されているからである。 |
| ここに「獣」から「人」への必然が生まれた。それは「苦杯」という形で実現し、最初に注がれた「罪」はイエス自身のものであった。すなわち、それが実現すればイエス自身の「罪」が贖われるのである。「イエスは最初から罪のない者としてお生まれになった」とするのは誤りである。「罪」は人と人との関係を結ぶ中で生まれる。「罪がない」とすれば、その人は人との関係が持てない者ということになる。人を教えたり、癒しのとりなしをするなど不可能なのである。それを知るには、ある幼女の記録が参考になるであろう。 |
| 三本の十字架を遠くから見つめられたマリやさまは、全地が暗くなるという異象の中で、大祭司が自身の罪を負い、木に架けられて流した血で贖われたことを確認された。あとは嘆願者が自身の罪をイエスの杯に注ぎ込めば、十字架のイエスを仰ぎ見て、「あなたはわたしと共にパラダイスにいる」との声を聞き、イエスのこときれるのを確認した時、ふっと消えるようになる。今その道が拓かれたのだ。そしてアロン家はその役目を終え「永遠の安息」にはいったのだ。わたしはそれを人々に知らせねばならぬ。だが、どのようにして。 |
| 「ルカによる福音書」3章 3-1皇帝テベリオ在位の第十五年、ポンテオ・ピラトがユダヤの総督、ヘロデがガリラヤの領主、その兄弟ピリポがイツリヤ・テラコニテ地方の領主、ルサニヤがアビレネの領主、3-2アンナスとカヤパとが大祭司であったとき、神の言が荒野でザカリヤの子ヨハネに臨んだ。 大祭司が二人並び立つことはない。律法は崩れている。 ちなみにアンナスやカヤパは、アロン家の者ではない。アロン家が滅んだ後、祭司たちの互選によるものであろう。律法はある意味無視されていたのである。彼らはアロン家の生き残りがいることを知らない。 |
| 戻る |
| 取説作成の休止 |
 |
| 「まつりさま」 |
| その間「マリヤさま」を書いて出版を目指す。このサイト構築の13年間の集大成になるだろう。タイムリミットは1年に設定した。この母子の背後にはマリヤさまのお姿。 |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会・「取説」担当 笹倉正義 2022/9/18、9/19、10/6 |
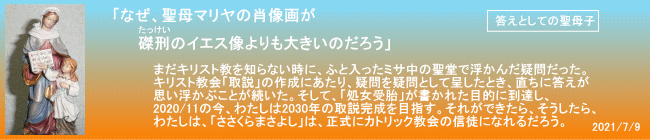 |
| 「答としての聖母子」 |
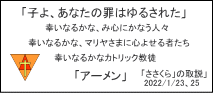 |
| 「恵まれた」とは「幸運な」ではなく、「資質の豊かな」である。 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 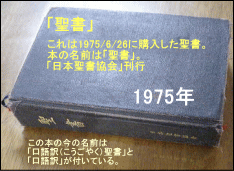 |
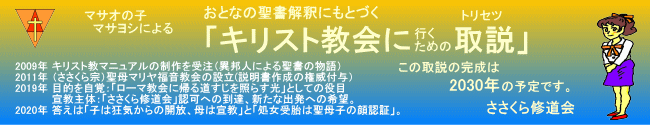 |