| 13.聖母子は「アロン家」を昇華 |
| 「アロン家」は、律法により、唯一「罪のゆるし」に関わることができた家柄である。マリヤさまはそのアロン家の最後の姫である。「緊急避難」として他部族の青年との婚約を調(ととの)え、念を入れて、エマオからナザレに疎開された。 だがアロン家の子が産めないという苦悩が少女をおおった。彼女の壮絶な祈りの日々が続き、婚約者のヨセフも先祖の神に祈り続けた。そうしたある日、マリヤは「おめでとう、恵まれた女よ」という「声」を聞くのである。少女は妊娠し男子を産んだ。「処女受胎」は姦淫の疑惑を招かずにはおかない。ヨセフは急遽、マリヤを連れて実家のベツレヘムに戻り、結婚式の宴を催した。その道すがら、祭司の町エマオに寄り、エリザベツに会った。エリザベツはマリヤとヨセフを信じた。そしてアロン家の血脈が密かに続く希望を喜んだ。そしてマリヤは、エリザベツに信じてもらえた喜びと、自身にあふれる悦びを歌った。 「ルカによる福音書」1章 1-43主の母上がわたしのところにきてくださるとは、なんという光栄でしょう。1-44ごらんなさい。あなたのあいさつの声がわたしの耳にはいったとき、子供が胎内で喜びおどりました。1-45主のお語りになったことが必ず成就すると信じた女は、なんとさいわいなことでしょう」。 マリヤさまは「アロン家」であり、エリザベツは祭司に嫁(か)しているので、身分としてはマリヤさまの方が上なのである。まだ婚約中だからである。 1-48この卑しい女をさえ、心にかけてくださいました。今からのち代々の人々は、わたしをさいわいな女と言うでしょう。1-49力あるかたが、わたしに大きな事をしてくださったからです。 処女受胎は秘されているとしても、それが明らかになれば、姦淫の疑惑にさらされる。それは12歳の少女の負担にならないはずはない。しかし、アロン家の子が産めるという途方もない悦びのために、それを受諾した時に、すでに恐怖は吹き飛んでいるのである。 老齢のエリザベツと少女のマリヤさまに相次いで臨んだ妊娠は、共に人智を超えたものであった。時代は皇帝アウグストとヘロデ1世が共に晩年の頃である。 その30年後、同い年(おないどし)生まれのヨハネが世に現れ、人々の「罪」を水で洗った。それは、ユダヤ人個々に「罪」の意識を具体的に思い起こさせた。それまでは、神殿の行事としてのものであって、集まった人々の罪を一括して、用意した獣(牛や羊などの家畜)を屠(ほふ)って、その血で罪を洗い流したのである。個々人のものもあったが、それは「罪」の量刑減免の衆知としての目的があったであろう。だが、ヨハネの場合は「罪人(つみびと)」とされた取税人や売春婦(罪の女)にもおよび、彼らを洗ってやったのである。ヨハネの宗教的行為は、大祭司の耳にも入るところとなったが、ヨハネは祭司の息子であったから、その行為は大目に見られるところとなったが、ヘロデ2世に別件の「侮辱罪」で捕らえられ、獄死した。 そして、それを真似たものか、イエスなる人物が宗教活動を始めた。彼が衆目を集めたのは、彼の言葉に「権威」があるとの評判のためである。彼が人の罪を洗うことはなかったが、「あなたの罪はゆるされた」という言葉を口にした。イエスはユダ族と認識されていたので、民衆は彼がヘロデに代わって「王」となることを望んだが、大祭司はイエスを「律法違反」と認定した。そしてイエスは死に定められ、あろうことか、異邦人の十字架の露と消えたのである。ユダ族のイエスは民衆の期待に沿うことなく、意味不明の「罪」にかかわったために命を落とす羽目になったのである。 「すべては終わった」、との失望がエルサレムに満ちた。 しかし、イエスの十字架と同時進行している二つの動きがあった。伝令がエルサレムの兵営から地方のローマ軍駐屯地に飛んだ。特にガリラヤ地方はもともと反ローマ意識の強い土地柄である。そのガリラヤのカペナウムにも軍の駐屯地があった。その夜おそく、騎馬の伝令が到着し、イエスの処刑が伝えられた。それを聞いた将校のひとりにクレオパがいた。彼は(しもべ)のルカにイエスの「死の意味」を調査するように命じた。ルカは、ユダヤ人の長老をともなうため、翌日の安息日の明ける三日目の朝に、馬車を飛ばしてエルサレムに向かったのである。 もうひとつは、イエス一行の投宿している「巡礼者の宿」での動きであった。三日目の朝、イエスの遺体が仮置き去れた「洞窟(人の子に備えたシェルター)」に向かったが、蓋(ふた)は転がされて、中は空(から)であった。遺体が消えたのは「安息日」の最中(さなか)であったことになる。 その日の午後、宿の二階の広間では、弟子たちがたむろしていた。彼らが「大臣」になる夢は消え去った。故郷にどの面下(つらさ)げて帰れようか。はずかしい。その暗く沈む広間の戸口に人影が立った。一同は何気なくその人物に目を向けたが、突如総立ちになった。「イエスだ」。それは紛(まぎ)れもなく、奉仕の女性たちを従えたイエスその人だった。だが、その人が近づくと、それは女性であると知れた。イエスの母にまぎれもなかった。だが、誰も何も言わなかった。そして、そのイエスは静かに語り始めた。その話のポイントは、宿の息子のマルコがもたらした「園でのイエスの苦しみ」と「ムチ」と「十字架」とに集中した。それは、「罪のあがない」に言及された。そしてそれは「聖書」から引用された。聖書はヘブル語で書かれていたが、彼女はそれを読み上げ、アラム語に翻訳して解説した。 だが、それはイエスの罪状が関係して、イエスの「律法違反」を拭(ぬぐ)い去るにはインパクトに欠けた。その時、マリヤさまへの来訪者が告げられた。まもなく戸口にユダヤ人の長老が現れた。彼はマリヤさまに驚きながらも、伴ってきた異邦人との面会を求めた。そしてルカが女主人に案内されて広間に入ってきた。その時、長髪の男装の人が振り向いた。その顔を見たルカは仰天した、「イエスだ」。こうしてまたしても、「イエスが生きている」との驚きがあったのである。ルカもまたそれが、男装の女性、イエスの母であることがわかった。ルカの関心は、眼前の女性とカペナウムで知っていたイエスとの「酷似」に集中した。 マリヤさまは長老立会いのもとでルカと歓談された。長老はルカの主人はイエスに信仰をほめられた人物であると紹介した。マリヤさまはその軍人クレオパが資産家であること、目の前のルカがその死を惜しまれるほどの人物であることを思われた。ふたりがアラム語とギリシャ語とを交えて、時にはヘブル語も交えながら話すのを、弟子たちはあっけにとられて見守った。 そして話は、ついに30年前に起こった「処女受胎」に及び、マリヤさまがアロン家の者であること、イエスもまたアロン家の者であることが語られた。その証拠はまさに、「顔認証」にあった。それであれば、イエスには「罪のあがない」に関わることができ、「あなたの罪はゆるされた」とのとりなしは「律法違反」ではなかったのである。しかし、その誤認があればこそ、「苦杯」と「十字架」とにより、「罪の解決の手段が成った」のである。それは人の罪の「一括のあがない」ではなく、個々人に作用するものであり、信じる者にすべてに及ぶのである。 しかしながら「罪」という言葉からは、「人が生まれながらに持っているもの」との結びつきがあいまいである。それは「狂気」いう名の罪とすると具体にイメージできるだろう。狂気こそは程度の差はあれ、人が生まれながらに持つものである。それは自分で制御できるものでないゆえに狂気であり、心ある者は、その発動におびえるのである。ひとたびそれに囚(とら)われると、その結末は不幸であることが多い。聖母子は、その不幸の芽を摘むこと、すなわち狂気をあがなうこと、に関与されたのである。すなわち聖母子こそは、律法によるアロン家最後の者であり、「罪」に関わる独占権があるのである。その権利の発動は、律法の生きているユダヤ人社会の中で、すなわちエルサレムの神殿の存在する時空でなければならなかった。エルサレムはそれを成し遂げ、その役目を終え、西暦70年に地上から消えた。だが、復活のイエスが「永遠の」大祭司と信じられたことにより、アロン家もまた永遠となったのである。 地上のアロン家は、「出エジプト」の荒野で定められた律法によるものであり、民族統合の象徴としての神殿の行事を司(つかさど)る唯一の家柄(いえがら)である。砂漠では移動可能な「幕屋」であることはやむを得なかったが、それに従事したのがレビ人(びと)であった。アロン家もレビ人ではあったが、律法によりその棟梁(とうりょう)としての地位を与えられたのである。アロン家が最もその機能を発揮したのはむしろこの荒野の40年であろう。すなわち12部族が荒野で霧散しなかったのはこの幕屋の賜物(たまもの)であろう。ヨシュアの指揮の下に部族がパレスチナに散ってからはアロン家の存在は忘れられた。それが思い出されたのは、南王国の人々が、バビロン捕囚から荒廃したエルサレムに戻った時である。その人々とは、ユダ族とベニヤミン族それにアロン家とレビ人とのリーダーたちである。 彼らは、王国の再興ではなく、宗教によって律(りっ)せられた自治州の認可を得るため、「律法」を作成し、ペルシャ王に提出したのである。それが「書かれたもの」であり、厳格に守られるべきものとなったのである。律法に権威があるのはそのためなのである。 その後、律法は「聖書」に発展することになった。物語が作成され、律法はその中に分割して置かれた。律法だけでは民衆は聞く耳持たないだろうが、物語なら聞くだろう。すなわち物語は「創世記」、「出エジプト記」、「レビ記」、「民数記」、「申命記」として出来上がった。その物語には、捕囚時代のバビロンの知識が組み込まれた。バベルの塔、大洪水などはバビロンの伝説である。 ささやかな神殿が出来上がると、アロン家とレビ人との出番がきた。すなわち、部族統合の要(かなめ)となることである。北王国の子孫10部族に「ユダヤ人」への合流を呼びかけたのである。「ユダヤ人」とは、捕囚の人々がバビロンで呼ばれていたニックネームである。「ユダヤ人」の自治州はペルシャ王の認めるところとなり、エルサレムの神殿を核としてあらたな歴史を刻み始めたのである。ユダヤ人社会は律法に律せられて成り立つ社会である。ここに、「アロン家」の「罪」にかかわる神事の存在感が現れることになった。だから、ユダヤ人と言っても、帝国内の町々に分散した人々は、神殿にはなじみが薄くて当然である。神殿は土着のユダヤ人にこそ「信仰を生きる」喜びの実感を与えたのである。 「ルカによる福音書」2章 2-41さて、イエスの両親は、過越の祭には毎年エルサレムへ上っていた。2-42イエスが十二歳になった時も、慣例にしたがって祭のために上京した。 イエスは、誰知ろう「アロン家」最後の者である。このイエス12歳の時にも大祭司はいたが、それはアロン家の者ではない。むしろヘロデ1世の息がかかった者の家系であろう。 アロン家の「仕事」のメインは、「罪」のあがないのとりなしである。しかしその方法は、神殿に参集した人々の罪を一括して「獣」、牛とか羊といった家畜に移して屠(ほふ)り、その血で罪を清めたのである。 血は命であり、命と引きかえに「罪」の清めを願ったのである。 「レビ記」17章 17-11肉の命は血にあるからである。あなたがたの魂のために祭壇の上で、あがないをするため、わたしはこれをあなたがたに与えた。血は命であるゆえに、あがなうことができるからである。 祭りの行事としては、罪の対象は「一括」であり、獣の血を用いることはやむをえない。個人の場合は、霊魂の救済ではなく、量刑の減免としてものであろう。 聖母子は、結果としてではあるが、個々人の「狂気」を杯に受けて身に負い、木に架けられてその血を流して清算する道を拓かれたのである。すなわち、信仰の嘆願者は自らの「狂気」を、イエスの杯に移し、目を転じて十字架のイエスを仰ぎ見るのである。イエスが息を引き取る瞬間、嘆願者は自らの狂気がふっと消えたことを実感する。これはすべての人にできることではなく、神父が代行し、「子よ、あなたの罪は許された」と宣言するのである。 プロテスタントにはこの概念はないし、プロテスタント化した神父にもないであろう。彼らは、聖母子の成し遂げたことにではなく、エジプトのアレキサンドリヤの「智」とアウグスティヌスの「愛」などにうつつをぬかし、智という名の「痴」をさまようのである。彼らの主は「サタン」であると知らずに。智の統合者はサタンであり、それは人の概念による。 イエスが苦しまれている霊的な杯(さかずき)をイメージする。そしてその杯に自らに取り付いて離れない「狂気」を注入するのである。それは感情の制御ではなく、救いを求める信仰による。するとイエスの苦しみがさらに増し、汗が血のように滴っているのが見えるだろう。次に目を十字架にかけられたイエスを「仰ぎ」見る。それは重ねて信仰によるのである。釘で打ち付けられ、木に固定され、あるいは体重によりじりじりと裂かれ続ける両手と両足の傷から、汗のように血がしたたり落ちる。十字架刑は体力と持久力のある者とってはその苦しみが続きつづけるのである。イエスの落命が数時間であるのは異例であるが、それはピラトが許そうと思ってムチ打たせたからである。ムチはイエスの肉をはぎ、ぼろぼろにしたのである。 |
| 次へ |
 |
| 2016年のイタリヤ旅行「バチカン」 |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2022/1/9 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 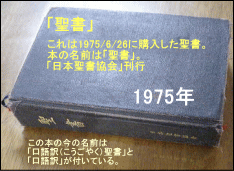 |
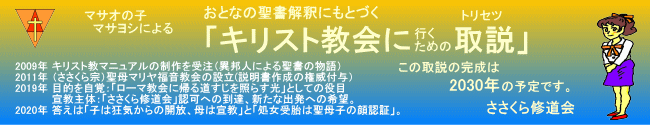 |