| 権力者から、キリスト者として最初に迫害を受けた者、それは言わずと知れたイエスさまである。彼は、マリヤさまの子であるがゆえに、家長(かちょう)であったヨセフからダビデの家系である。処女受胎は、誰も知らない。また、母マリヤさま(親族のエリザベツはアロン家の娘のひとり)からはアロン家の系統を受け継いだのである。 ダビデの系統は、地上の権力の資格者(ユダヤ人社会でのみ通用)である。アロン家のそれは、大祭司の系統である。イエスは復活し、その後昇天して、天の父の右に座しておられるので、永遠の大祭司なのである。西暦にリセットがないのは、このゆえである。 天の父と人の子 ここではまず、イエスさまの父の神に対する絶対的従順について、物語っておく必要があるだろう。「迫害」のビッグバンであり、純粋なユダヤ社会の中、常とは異なる時空があったのだから。 過越の祭の前夜、「過越」の食事のあった、渡される夜、イエスさまはいつもの場所、ゲッセマネの園で祈られた。このとき、天の父と、「人の子」イエスさまとのドラマが始まった。 獣ではなく人(大祭司)に 個々人の狂気(罪)を負わせる この時の時空には常ならぬ事態があった。イエスさまは、父から差し出された(霊的な)杯(さかずき)を認識された。しかし、イエスさまは、苦しみもだえて、それを忌避された。しかし、ついにはそれを受諾し、血のような汗をしたたらせて、飲み干された。 修正(2024/9/1) 最初の杯にはイエスさまご自身の「罪」が注入されたとする。罪そのものは社会的に不可欠なものであるが、同時にそれは主なる神を忘れさせるようにも作用する。その罪が変じて「狂気」となった時にさまざまな「狂い」を生じさせる。罪は見えないので「あがなう」手段はない。しかし、杯に満たされたものを飲み干し、それが身体に「顕在化(けんざいか)」するなら、その者、アロン家の大祭司は生贄(いけにえ)となる。そしてそれを石打ではなく木に掛けて屠(ほふ)れば、「あがない」の神事は成る。 死刑ありき、イエスさまの裁判 そして、イエスさまは逮捕された。ここから、 議長は、イエスさまの言葉尻をとらえ、有罪を宣告した。死罪である。議会は、偽預言者を町中(まちなか)に引き出し、その罪状を布告して、石打の刑にできた。ローマの総督も、これには目をつぶる。しかし、彼らはそうはしなかった。一般のユダヤ人の多くは、イエスさまを預言者と信じて、尊敬し、あがめている。その彼を罪人として公衆の面前に引き出せば、民衆の間に対立が生じ、へたをすると暴動が起き、エルサレムは混乱状態になる。この時のエルサレムの社会には、政治的不満がうずまいていたからである。 そこで彼らは、イエスさまをローマの権威で死刑にしてもらおうと、総督ピラトに告発した。時刻はまだ午前10時にもなっていない。町がまだ目をさまさないうちに、イエスさまの身柄を議会から総督の官邸へと護送しなければならない。ピラトは、「今、何時だと思っている!」と、腹がたったと思うが、ユダヤ人たちは、ねちねちと訴え続けた。こんな時間帯に連れてくる罪人とは、いったいどんな極悪人(ごくあくにん)だろうか。ちょっと、興味をそそられながら、ピラトはその人物を見た。そして、驚いた。彼は、多くの死刑宣告された罪人を見てきた。ほとんどの者は、ピラトを見るなり、自分の「無実」を必死で訴えるのが常だった。しかし、今、自分の目の前に引き据えられている人物は、命乞いどころか、ピラトが、かつて経験したことのない、底知れぬ威厳のようなものをたたえていた。「この女かと見まがう者に、わたしが死刑を宣告するのか」。 この時、ピラトは、イエスさまがカペナウムの人であることを知った。当時、そのガリラヤ地方はヘロデ(二世)が統治していた。王は、過越しの祭りのために上京(じょうきょう)していた。そこでピラトはイエスさまをヘロデの邸宅に送り込んだ。 しかし、目鼻のきくヘロデは、イエスさまを罪に定めたくないため、軽くあしらって、彼をピラトに送り返した。イエスさまを有罪にすれば自分の手で処刑しなければならなくなる。ガリラヤへ連行するなど、もってのほかである。そんなことをしたら、暴動を誘発するようなものだ。 ヘロデは、先代のような全ユダヤの王ではないが、王の処遇がある。彼は、改宗(かいしゅう)のユダヤ人である。ユダヤ人には十二部族のほかにレビ人、改宗のユダヤ人がいる。そして、漁師のペテロのような土着の者と、各地に散らばっている離散のユダヤ人がいる。 ユダヤの地は、この100年近く、ハスモン家(大祭司を自称)が治め、独立国の態(てい)を保っていた。それをヘロデ(今のヘロデの先代)が、ローマとの謀略をもって一族を殺害、代わってユダヤの王となったいきさつがある。イエスさまは故郷では認められなかったかも知れないが、そこ以外の地方では、若き預言者と信じられていた。また、カペナウムの将校の信望も得ているとのことだ。 さわらぬ神にたたりなし、というものだ。ここでは、自分が阿呆(あほう)を演じよう、と彼は考えたのである。国民の不満は、いぜんくすぶっていた。暴動のきっかけさえあれば、その火の手はたちまち燃え上がるのだ。 刑の減免「とげの鞭打ち」 こうして、イエスさまは再び、ピラトの法廷に戻された。ローマの総督、ピラトは、ユダヤ人の策謀を見抜き、何とかイエスを許そうと考え、大衆の面前で、イエスに鞭(むち)を打たせた。しかし、この大衆は、議会の息のかかった連中だった。イエスの肉片や血潮が飛び散るのを見ても、哀れむどころか、かえって火に油を注いだようなものだった。「イエスを殺せ!」。 刑の減免「大祭の恩赦」 ピラトは次に、この大祭にともなう恩赦(おんしゃ)を彼に与えたいが、と提案した。それは大衆の思う壺で、「バラバを許せ」と叫ぶ。バラバは、ただの強盗ではなく、むしろ今のテロリストだったのであろう。ピラトとしては、一番許したくない奴(やつ)である。しかし民衆は、自分たちの神は皇帝のみ、とか叫ぶありさまで、これ以上騒動が大きくなるのを恐れたピラトは、ついに政治決着した。すなわち、バラバを許し、イエスさまを彼らユダヤ人の意のままにさせたのである。彼らはイエスさまにバラバに用意された「空いた十字架」を負(お)わせた。 ローマの法廷で有罪となったイエスさまは、自分の十字架を負い、刑場まで歩もうとするが、肉体の損傷と、大量出血で貧血を起こし、力が入らない。こうして、彼が人の罪を担うことの、外的な条件が成立した。内的なものは、ゲッセマネの園で果たされていた。 マルコの母の 彼が十字架に架(か)けられたのは10時ごろとされる。この変事を、イエスさまの母マリヤさまに最初にもたらしたのはマルコであろう。イエスの逮捕現場から裸で逃げ出した若者(わかもの)である。最後の晩餐があったのは、この青年の母の家「巡礼者の宿」である。 マリヤさまは、戻った使徒たちを許すどころのものではなく、いくつしみをもって、彼らの魂の嘆きを慰められた。「あの子は、 こうして、イエスさまは、十字架にさらされ、「すべては終わった」と言って息を引き取られた。これは、 「ルカによる福音書」の記者は、百卒長に、「まことに、この人は正しい人であった」、と言わせている。この将校こそは、テオピロ(実名はクレオパ)であり、記者はそれを報告書のまとめとしたのである。 これが最初の迫害である。ただ迫害は対ユダヤ人であり、イエスさまの十字架はアロン家の神事に不可欠のものであり、ピラト総督の恩赦による「空いた十字架」こそは、生贄を屠るためでなければならない。 人が神を迫害すること、それをイエスは、「父よ彼らをお許しください。彼らは自分たちが何をしているのかわからずにいるのですから」と、とりなし、罰を与えない配慮をしている。彼らユダヤ人の聖職者らはイエスをローマの十字架で処刑でき、預言者殺害の反感をローマに振れたし、万事うまくいったと思っている。しかし、主なる神の秩序の中で、ユダヤの究極の目的、すなわち狂気(罪)の解消(赦し)の道が拓かれようとしていることには思い及ばないのである。ああ、聖職者たちの何と暗いことであろう。イエスさまの処刑は、皇帝への報告書に記載される。世界の片隅の事件ではなくなるのである。 起こらなかった暴動と迫害 イエスさまは人々から、預言者であり、またダビデ王の再来として、ローマとヘロデの圧制からの解放を望まれいた。それというのも、ユダヤはローマ軍が来るまで、またヘロデがローマのバックアップを受けて、ユダヤの王として就位するまで、ハスモン家の治世の下で独立国だったのである。だから、ユダヤ人の不満は、暴動の温床としてくすぶり続けていた。 バラバもそういった解放運動の地下組織に属していた可能性がある。イエスさまもそのこと、自分が独立の先頭に立つ者とされることを危惧しておられた。即時報道としての記述が、もっとも信頼できる福音書は、「ルカによる福音書」のみであるが、義父ヨセフの記述はない。わずかに、母マリヤさまの影として書かれるにとどまっている。なぜか。ヨセフは、そういった地下組織のリーダーにまつりあげられ、ローマやヘロデと対立して、その結果落命した経緯(いきさつ)があるのでは、と推測される。だとしたら、ルカは報告書にその名を書くわけにはいかず、最小限にとどめる必要があったのだ。 「ルカによる福音書」13章 13-1ちょうどその時、ある人々がきて、ピラトがガリラヤ人たちの血を流し、それを彼らの犠牲の血に混ぜたことを、イエスに知らせた。ピラトが暴動鎮圧のためにガリラヤに出向いたことが簡潔に書かれている。民衆は大祭司統治による独立国家時代を忘れられないのである。 このことは、マリヤさまが最も心をくだかれたことと、わたしは思わざるを得ない。裸で帰ってきたマルコの第一報は、イエスさまの逮捕であった。遅れること3時間後にもたらされたペテロの第二報は、「有罪」であった。これが地下組織に伝われば、「盟主奪還」の原因となり、エルサレムに暴動の火の手が上がりかねない。また、それはたちまちユダヤ全土に飛び火していくだろう。 マリヤさまは、一種(いっしゅ)の名状しがたい威厳を呈して、皆の心をやわらげ、冷静を保つように指導されたのだ。そして、自身、他の女性たちとともに、イエスの刑場におもむかれた。刑場に立つ彼女の存在は、その場の緊張した雰囲気を大いにやわらげ、動揺を沈静化させた。 ---「処女受胎の意味」 マリヤと処女受胎のイエスは同じ容貌、目の光であった。二人の違いは性を原因とするものでありその役目が違った。この一致と違いとが処女懐妊の根本である。ひとりはあがない、もうひとりは伝道。 ローマもヘロデも厳重な警備体制を敷いていたが、ついに暴動は起きなかった。だからその後、弟子たち関係者は迫害を受けなかった。それどころか、彼らはその後も神殿に出入でき、また祈ることができたのである。そこはイエスさまの父の家なのである。 イエスさまが息を引き取られたとき、天地は暗くなり、地震が起こり、神殿の幕が真っ二(まっぷた)つに裂けたと書いてある。げに不思議な時空がそこに存在したのである。「天地は暗くなり」とは皆既日食のことであろう。また、「神殿の幕が真っ二つに裂けた」とは地震の大きさを示すものであろう。 「園、ユダの哀れ」 ここにきて、イスカリオテのユダの裏切りは何だったのだろうと思わざるを得ない。イエスさまを売り渡していくらかでも金を得ようとしたのでは、欲がなさすぎるのである。イエスさまは、王となって、側近である自分たちはその大臣にもなれるであろうと、使徒たちは胸算用していたのである。しかし、イエスさまの言葉に不安を感じていたユダは、ついに賭けに出たのである。いつもの園で深夜にお祈りをするイエスさまを、大祭司の手の者が捕縛しようとしたら、イエスさまはどうされるだろう。 その時こそ、彼は天の軍勢を呼び寄せるか、あるいは言葉の力をもって、彼らを撃退されるはずだ。だが、ユダは知らなかった。イエスさまは、ユダに引率された捕縛者が現れる前に、父の杯(さかずき)をあおって、 「エルサレムは平穏である」 イエスさまが息を引き取られたのは午後3時ごろとされる。十字架刑は、昼夜放置され、日射と夜の冷え、自重で肉が裂かれる痛み、言語に絶する苦痛を与え続けるものであり、見る者を戦慄(せんりつ)させずにはおかない。体力があればあるほど、その苦痛は長引き、何日も生きなくてはならない。だがイエスさまの場合、身体のダメージと失血で、その落命がピラトも驚くほど早かった。「それは、せめてものさいわいだ」と、彼は思った。そして、イエスさまの遺体引取りの嘆願にも快く応じた。 総督は、彼の弟子と思われる連中が新たに現れるのを見たとき、またまた驚かずにはいられなかった。彼らは石とか、武器のようなものは持っていなかった。しかも、その群れはとても静かであった。泣いているのはイエスの仲間ではなく、「泣き女」たちと呼ばれる者たちで、それは「哀歌」ではなく、むしろ議会側が勝利した歌だった。その静かな群れの中に、女性たちの姿が望まれ、とりわけ、彼女らの中心にいる女性には、皆が特別な敬意を抱いている様子が見て取れた。彼らは泣いてはおらず、静かに祈っているようであり、その情景に「絶望」という言葉はふさわしくないと思われた。やがて、彼らは、ピラトからさげわたされた、イエスの遺体とともに去っていった。 ピラトは、伝令を命じた。その最後には、「エルサレムは平穏である」という言葉を付け足すように命じた。140Kmばかり離れたカペナウムの兵営に早馬の伝令がもたらされたのは、その日の夜遅くなってからであった。そこにはイエスさま処刑の事実と罪状とが書かれていたが、最後に「エルサレムは平穏である」とあった。 その日はおかしなことがあった。正午ごろ全地が薄暗くなった。また、地面が揺れるのを感じた人々もいた。百卒長(ひゃくそつちょう)の一人(ひとり)が、その事実を、彼の僕(しもべ)に書き留めておくよう命じるのを忘れなかった。 ヘロデもまた、滞在中のエルサレムに何事も起こらなかったのが不思議に思えた。「総督の官邸や自分の邸宅の厳重な警備はいったい何だったのだ。あの預言者は結局その程度のものだったのか。やれやれ、これで、すべては終わった」。 自分とイエスさまとの、「すべては終わった」の意味が、どれほど違うのかは、ヘロデにわかろうはずもなかった。その意味では、彼だけではなく、マリヤさま以外、奉仕の女性たちと弟子たちとても同じであった。ただ、この事態を受けて、行動を起こした者が一人(ひとり)いた。その人物こそ、福音書にイエスにほめられたと書いてあるにもかかわらず、その名の記(しる)されないカペナウムの百卒長であった。 マリヤさまに見知らぬ訪問者 この変事から幾日もたたぬと思われる日に、イエスさまの母を尋ねて、一人(ひとり)の異邦人(いほうじん)がユダヤ人の長老と共にエルサレムに上(のぼ)ってきた。彼は主人の命(めい)を受け、はるばるカペナウムからやってきたのである。そして、ユダヤ人同士のつてで、この従者とマリヤさまが出会うのである。その男の名は、ルカ、カペナウムの百卒長の僕(しもべ)である。ルカは、宿の二階の広間に通されたとき、弟子たちと話をしていた者が振り向いた時、「イエスだ。イエスが生きていた」と叫んだ。だがそれは男装のマリヤさまだった。そのマリヤさまの物腰(ものごし)と、その霊感に満ちた容貌とに「聖母」を見、われ知らず、ひざまづくのである。ルカもまた、民衆の暴動を恐れていたが、聖母を見たときに、それは杞憂(きゆう)だとわかった。イエスさまは、この母に育てられたのだ、そう思った。 |
| 次へ |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに制作してよい」 |
| ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 |
| 略称:オリジナル教会 |
| ささくら修道会(マリヤさまの宣教主体) |
| 2019/9/8、11/13、11/20、12/19(処女受胎の意味の独立リンク) 2024/9/1(全面推敲) |
| ささくら修道会の宣教理念 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version) |
| 聖句引用:日本聖書協会 口語訳聖書 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 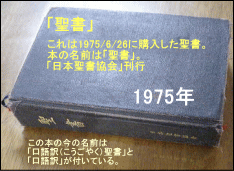 |
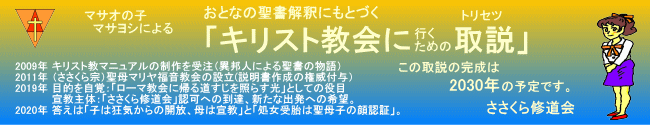 |
| トップ・メニュー |