| このテーマについては、この2023年に仕上げた原稿に、さまざまな気付きのひとつとして書き上げています。端的に言うと、復活のイエスさまは男装のマリヤさまを見間違えたのです。男装は女が男に教えてはいけないからです。十字架の贖いの福音を語れる者はマリヤさま以外にはないのですが、誰が信じるというのでしょう。それはイエスさまにほめられたカペナウムの百卒長(ひゃくそつちょう)主従(しゅじゅう)とします。2024/8/9、2025/2/9 |
 |
| 自費出版:400部、2024/6/18、ひとりの孫娘のために |
| 本書は、イエスさまによる、世々の個々人に内在する「狂気」の消去という信仰の |
| 「マリヤさま」出版を踏まえての再考 2024/8/9 |
| 1.証拠が推定できなければ作り話 たとえ「聖書が神の賜物」だとしても、書いてあることに「証拠」がなければ、それは信じるに値しない偽(にせ)情報あるいは「智」の創作となってしまう。「イエスさまの復活」に証拠はあるのか、それを考えてみることにする。とはいえそれは自らの知恵ではなく与えられるものでなくてはならぬ。同じことを何度も書いている気がするので、同じことをまた言っていることになるかも知れないが、それこそは「智」によらず与えられたものという証拠になってくれればと願う。 |
| 2.処女受胎が出発点 恵まれた十二歳のマリヤさまに臨んだ「処女受胎」がキリスト教の出発点になったのである。その意味は生まれ出ると言われた子がユダ族ではなく母の家系を継ぐ者となるということであり、その家系とは「アロン家」である。アロン家は「罪の贖い」の神事に携われる唯一の家系であった。ハスモン家が腕力で大祭司を簒奪したが、ヘロデに滅ぼされた。律法によれば、アロン家の中で「大祭司」の装束(しょうぞく)を着(つ)けたものが「罪」のあがないの神事に携わることができたのである。だから、処女受胎が意味を持つためには、その時、アロン家の者はマリヤさま以外にいなかったとしなければならない。 「レビ記」21章 アロン家の男兄弟がいる場合 21-10その兄弟のうち、頭に注ぎ油を注がれ、職に任ぜられて、その衣服をつけ、大祭司となった者は、その髪の毛を乱してはならない。 |
| 3.ナザレは疎開(そかい)先 10歳のマリヤさまは、一族の「自決」に臨んで、父は「恵まれた女」の彼女の死を望まず、急遽ユダ族のヨセフと婚約させ、ヨセフの父は二人を、田舎のナザレへと疎開(そかい)させたのである。マリヤさまの実家(じっか)はユダの山里の祭司の町エマオであり、ヨセフの実家はベツレヘムである。二つの町はエルサレムを挟んでほぼ同じくらいの距離にあり、ヨセフはエルサレムでもエマオでも仕事をし、マリヤさまはヨセフに対し兄のように馴染(なじ)んでおられたのである。父はヨセフが必ずマリヤを守ってくれると信じたのである。「ヨセフ、マリヤを頼む、さらばじゃ」。 |
| 4.イエスさまが大祭司の根拠 果たせるかな、生まれ出た子は男子であった。その子がアロン家の家系を継ぐ最後の者であれば、大祭司の装束は必要なく、生まれながらの大祭司なのである。 律法学者のパウロは、マリヤさまの処女受胎を鼻から笑い飛ばし、アロン家にも思い至らなかったから、イエスさまの大祭司を導くのに「創世記」のメルキゼデクを持ち出している。 「ヘブル人への手紙」5章 5-5同様に、キリストもまた、大祭司の栄誉を自分で得たのではなく、 「あなたこそは、わたしの子。 きょう、わたしはあなたを生んだ」 と言われたかたから、お受けになったのである。 「創世記」14章 14-17アブラムがケダラオメルとその連合の王たちを撃ち破って帰った時、ソドムの王はシャベの谷、すなわち王の谷に出て彼を迎えた。14-18その時、サレムの王メルキゼデクはパンとぶどう酒とを持ってきた。彼はいと高き神の祭司である。 |
| 5.アロン家の一人娘 そのアロン家の意味は何かというと、「罪のあがない」の神事を執り行う、律法による、唯一の家柄ということであり、人の罪を犠牲の獣(牛や羊)に移し、それを屠(ほふ)って血を容器に受け、それを用いて清めを行ったのである。血は命であるゆえ、罪をあがなうことができるのである。 ある時、10歳のマリヤさまは父に声をかけた。「お父さま、獣には人の罪は負えないわ。人でないと」。それを聞いた父はぎょっとして幼い娘を見た。「この子はいったい。誰も教えないのに、兄たちの朗読を聞き、またヘブル語でものを書くのを見るだけで、ヘブル語の読み書きができるのだ。まさに恵まれた女なのだ。ああ、この子が男の子であったらと望んだことがあったが、それだと自決の道連れになってしまっていた。これも神意なのだ」。 |
| 30年の時が過ぎた。イエスさまは世間にはユダ族と認知されていた。洗礼者ヨハネの名声がイエスさまご一家の生活拠点であり、ローマ軍の駐屯地であったカペナウムにも聞こえていた。ヨハネは「人の罪を水で洗う」と称し、ヨルダン川の河畔で人々の罪を洗い流していたのである。神殿ではなく、河畔で「誰にでも」洗礼することは画期的なことであった。 |
| その時、イエスさまは時が来たことを悟られた。そして最終目的をエルサレムの「過越の祭」の恒例となっていた総督ピラトの恩赦で空くはずの十字架、に置いて行動されたのである。マリヤさまは、蓄えていたイエスさまの稼ぎを携え同行された。エルサレムには「過越の祭」の前に着かねばならぬし、宿屋にも予約の使いを出しておかねばならぬ。諸国のユダヤ人の巡礼者がエルサレムに集うし、「人の子」信仰の人々はすでにエルサレムに入り、その時に備えている。彼らは岩を掘り、入口(いりぐち)の狭い横穴をいくつも造っているということだった。それは、「人の子」が来臨し、地を改める時に逃げ込むための「シェルター」である。 |
| 「過越の祭」の前夜、イエスさまは「過越の食事」を命じられた。これは「メニュー」であり、その内容は小羊の焼肉をメインとした御馳走(ごちそう)である。その食卓にはイエスさまと十二弟子以外にも、弟子たち、マリヤさまと奉仕の女性たちも同席したと考えるのが自然である。弟子たちは、イエスさまが「ユダヤ人の王」になることを信じて疑わず、前祝(まえいわい)と決め込んで、たらふく食って、ワインを飲んだ。 |
| マリヤさまは、宿屋の息子マルコを呼んで、「今夜はイエスたちと共にいてくれない。イエスを見守っていてほしいの」と言われた。果たして、食事が終わるとイエスさまと弟子たちはいつものように城壁の外に出て行った。夜は女は城壁の出入が禁止されていたので、ワインを飲んでいないマルコに頼まれたのである。「過越の祭」は月齢であり、いつも満月である。月光に照らされた夜道は明るく、イエスさまのようすもよく見えた。 |
| 夜遅く、マルコが裸で宿に駆け込んできた。城門の番兵たちは、マルコの顔を知っていたので、裸で戻ってきた彼を大笑いで通してやったのだった。マルコはマリヤさまに報告した、「とてもお苦しみのようすでした。そして杯を遠ざけてとも、うめきながら言われました」と。そして、イエスさまはイスカリオテのユダの先導でやってきた捕縛者に捕らえられたこと、彼らは弟子たちには目もくれなかったことを報告した。 |
| マリヤさまはイエスさまが「人の罪を負った」ことを思われた。それこそはイエスさまの資質によって可能だったのであり、暗にアロン家の「獣から人に」が退けられ、「人の罪をイエスさまが負われた」が実現したのだ。その最初の杯(さかずき)に入っていたものこそはイエスさま自身の「罪」でなければなるまい。自らは自覚できない罪が「苦杯」として自身の身体に注入され、顕在化したのである。それは耐え難い「霊的な」苦痛をもたらしたはずである。こうしてイエスさまは「罪を贖(あがな)う」ための生贄(いけにえ)となられていたのである。それを木に掛けることで、アロン家の神事は成就する。 |
| マルコに続いて弟子たちが戻ってきた。酔いはすっかり覚めていた。なすすべも無く彼らは意気消沈していた。漁師である彼らには、「イエスさまを取り戻す」という発想は生まれなかった。ベールで顔を隠しておられたマリヤさまは彼らに言われた「祈りましょう」と。その声を聞いて、弟子たちは身体に気力が戻るのを感じた。そしてマリヤさまを見た。それまで弟子たちが女に注意を払ったことはなかった。イエスさまの母君(ははぎみ)が女性たちと共におられたことも知らなかった。マリヤさまに従って奉仕していた女たちもそのことは口にしなかった。 |
| 未明にペテロが帰ってきた。そしてイエスさまがユダヤの掟に従って死に定められたことを報告した。自身を「神の子」と自称したことは民衆向けであり、専門的に言うと、ユダ族の者が「罪」に関わる言動をしたことが律法違反に問われたのである。だが、「石打の刑」で民衆にイエスさまを石で打たせるなど狂気の沙汰であった。そんなことをしたら石は刑を宣告した祭司たちに飛んでくるのだから。 だから、彼らはイエスさまの罪を「政治不安をあおる者」にすり替え、ローマ総督ピラトに訴え出て、政治犯として十字架に架けることを目論んだのである。そして大事なことはイエスさまを監獄送りにしてはいけないということである。そのためには、公示されている三人の十字架のひとつを使うことである。それには「祭」の恩赦を使い、罪人とイエスさまとをスワップすることである。しかもそれは事の成り行きとして、粛々(しゅくしゅく)と、しかも確実に実行されねばならないのだ。 |
| ユダヤ人たちの作戦はまんまと成功し、イエスさまはバラバという名の罪人の十字架を負わされることになった。イエスさまはピラトが許そうとして打たせた鞭打ちのダメージが大きく、歩くのもままならないありさまだった。 |
| イエスさまに対するピラトの温情は無視された |
| 「ルカによる福音書」23章 23-20ピラトはイエスをゆるしてやりたいと思って、もう一度かれらに呼びかけた。23-21しかし彼らは、わめきたてて「十字架につけよ、彼を十字架につけよ」と言いつづけた。23-22ピラトは三度目に彼らにむかって言った、「では、この人は、いったい、どんな悪事をしたのか。彼には死にあたる罪は全くみとめられなかった。だから、むち打ってから彼をゆるしてやることにしよう」。 23-23ところが、彼らは大声をあげて詰め寄り、イエスを十字架につけるように要求した。そして、その声が勝った。23-24ピラトはついに彼らの願いどおりにすることに決定した。23-25そして、暴動と殺人とのかどで獄に投ぜられた者の方を、彼らの要求に応じてゆるしてやり、イエスの方は彼らに引き渡して、その意のままにまかせた。 23-32さて、イエスと共に刑を受けるために、ほかにふたりの犯罪人も引かれていった。23-33されこうべと呼ばれているところに着くと、人々はそこでイエスを十字架につけ、犯罪人たちも、ひとりは右に、ひとりは左に、十字架につけた。 これであれば三人を十字架につけたのは「彼ら」ユダヤ人であり、ローマ軍の兵士ではないことになる。ピラトもイエスを許そうと努めているからイエスさまの十字架はあくまでユダヤ人によるものということになる。 |
| 時は十二時ごろであり、全地は暗くなって三時におよんだ、と書いてあるのは皆既日食のことであろう。三時間も真っ暗だったわけではあるまい。イエスさまのご誕生、イエスさまの洗礼に続く、三つ目の天の異象である。聖所の幕がまんなかから裂けた、と書いてあるのは、地震のことであろうが、イエスさまがアロン家の者であることを象徴する出来事でもあるだろう。イエスさまにとって「エルサレム」とは神殿のある唯一の場所であり、「あがない」の神事は、神殿で大祭司が執り行うのである。こうしてアロン家最後の者による神事、「苦杯と十字架」による「罪の贖(あがな)い」が完了したのである。以後、嘆願者は、その都度、「狂気という名の罪」が贖われる御利益(ごりやく)が得られることとなった。 |
| 「ルカによる福音書」23章 23-48この光景を見に集まってきた群衆も、これらの出来事を見て、みな胸を打ちながら帰って行った。23-49すべてイエスを知っていた者や、ガリラヤから従ってきた女たちも、遠い所に立って、これらのことを見ていた。 群集の望みはイエスさまがユダヤ人の王になることであったが、それは頓挫してしまった。まったくあっけない結末であった。ユダ族のイエスさまは死んでしまった。イエスさまを知っていた者とは、十二弟子以外の弟子たちやマルコなど宿の者たちであろう。女たちとはマリヤさまと奉仕の女性たちであろう。 |
| 十一弟子たちはさすがにここ刑場には立てず、宿にいた。イエスさまは死んでしまう、何ということだ。彼らはほとんどパニック状態であった。だが、三時ごろ、ふっと彼らから「動揺」が消えて、心が晴れるのを感じた。喪に服して嘆(なげ)かなければならないはずなのに何ということだ。イエスさまを裏切ったばかりでなく、その態度は不謹慎だと言われるであろう。だが、心は明るく晴れ渡っていることはどうにもならなかった。しかし、せめて顔はむずかしく、あるいは恥ずかしそうに装うことにした。 |
| ローマ軍の兵士たちも暴動に警戒しつつ、イエスさまのようすを見ていた。そこには「ゆるし」に安堵する光景が見られた。ふたりの囚人は泣き叫ばなかった。イエスさまの表情は、釘で打ち付けられた肉が徐々に裂け、血がにじみ出ていく激痛の中にも、それを感じないかのように穏やかであった。何か悪いものが体内から出て行く快感とバランスしていることのように思われた。 |
| 「ルカによる福音書」23章 23-47百卒長はこの有様を見て、神をあがめ、「ほんとうに、この人は正しい人であった」と言った。 これはこの場にはいないルカの主人テオピロ(とくめい)である。本名(ほんみょう)は最終章の「エマオのふたり」のエピソードで明かされるクレオパである。 |
| ローマ軍の十字架を使い、ユダヤ人がイエスさまと二人の罪人を十字架に架けた。イエスさまは午後三時ごろ落命されたことを知らせる伝令が、各地のローマ軍駐屯地に飛んだ。カペナウムには午前一時ごろに着いた。百卒長などの将校が伝令が読み上げるピラト総督の言葉を聞いた。その後で、伝令者は自分の見た不思議な光景の感想を、思わずつぶやいた。真ん中の十字架はバラバという男のものであったが、祭りの恩赦をその男に与え、イエスさまをそれに架けるようにユダヤ人たちが総督に要求した。彼らの要求そのものが騒動になることを考えたピラトはバラバを許しイエスさまとバラバの十字架とを「人々」に与えた。この時、三人を十字架に架けたのはローマ軍ではなく人々、つまりユダヤ人である。「ユダヤ人」と書けばピラトの恥になるのだった。この年(とし)の刑場には恩赦のシンボルである「空いた十字架」はなかった。それもピラトの味わった屈辱であった。 イエスさまの身体は、ピラトが許そうと鞭(むち)を打たせたために、ぼろぼろであったので、自分の十字架を負って歩くことはできないありさまだった。十字架には、手足が釘付けされ、足は傾いた板の上に置かれ、釘が肉を一気に引き裂かないようにしてあるので、苦痛が落命するまで続く。誰もが「殺してくれ」と叫ぶ残酷刑なのである。映画「スパルタカス」のラストシーンが十字架である。 だが、イエスさまはそうは叫ばれなかった。彼の表情には、何かしら大きなことを成し遂げたような安堵感のようなものが見られた。罪人の呼びかけにも応え、「あなたはわたしと共にパラダイスにいる」と言われた。それを聞いた罪人の表情からも恐怖の色が消えたのだった。 不思議にも視界が徐々に暗くなりはじめた。ふと見上げると太陽が黒くなり黄金のリングが見えた。そして再び明るくなっていった。 |
| カペナウムでも昼頃に暗くなった。伝令の「独り言(ごと)」を耳にしたクレオパは彼を自宅に呼び食事と寝床を与えた。次の日、伝令がエルサレムに帰る際、個人的な頼みごとをした。イエスさま一行(いっこう)が泊まっていた宿に寄り、明日(三日目)の午後遅くルカと言うものがユダヤ人の長老と共に訪れるという伝言である。伝令者はその宿に寄り、クレオパの言葉を伝えた。用件は「イエスさまの死の意味が知りたい」であった。イエスさまが泊まっておられたのは巡礼者の宿であり、その宿は神殿への参道にある宿のひとつで、誰もが知っていた。イエスさまたちは隠密(おんみつ)行動をされていたわけではない。むしろ、「われわれはここにいる」という態度だったのである。 |
| 伝令者から、その言葉をお聞きになったマリヤさまに希望が生まれた。ユダヤ人の長老を友人に持ち、会堂を建てくれた将校クレオパのことはマリヤさまもお聞きになっていたのだった。誰もが「終わった」と思っている「イエスさまの死の意味を知りたい」とは、しかもそれがローマの軍人であるとは。「これこそは神さまのお計らい」、マリヤさまの時がきたのだった。イエスさまによる「罪の贖(あがな)い」の話はこのユダヤでは入れられず、ローマの異邦人に受け入れられる。 |
| 翌日(三日目)の安息日が明けた朝、女性たちがイエスさまの遺体を仮置きした横穴(シェルター)に行ってみると、そこにはイエスの遺体はなかった。処刑の日没から、今朝の夜明け前までは安息日であったから、ユダヤ人の誰かが持ち去ったとは考えられなかった。マリヤさまにとってもそれは不思議な出来事であった。だが、誰にもそれはイエスの復活とは結びつかなかった。マリヤさまは午後に、「最後の晩餐」のあった、二階の広間に集まるように言われた。 |
| 皆は広間に集まって静かにしていた。そこにマリヤさまがおられないことには誰も気付かなかった。いつもベールで顔を覆(おお)い隠しておられたから、今まで存在感がなかったのである。そこに入口(いりぐち)に人影が立った。その姿を見た皆は仰天した。「イエスさまだっ」。そのイエスさまは |
| その時、マリヤさまに来客が告げられた。ユダヤ人の長老と異邦人の二人とのことだった。客の主人は相手に不信感を与えないように、伝言に用件を付け加えさせていた、「イエスさまの死の意味を知りたい」のだと。二人は広間に通されたが、振り向いた長髪の人物の顔を見た異邦人、ルカは叫んだ、「イエスだっ!」。再び広間はざわついた。しかしイエスさまは彼らを制し、異邦人にギリシャ語で返事を返された。「その問いにお答えいたしましょう」。ルカの驚きは増幅された。「イエスがギリシャ語を話すとは?」。 |
| ペテロたち漁師と奉仕の女性たちは、あっけにとられてイエスさまとルカの話すギリシャ語をわからぬままに聞いていた。イエスさまの死の意味は、「アロン家」の神事(しんじ)、「罪のあがない」に関わるもので、罪がゆるされるためには、別の命をもって願わねばならぬこと、これまでは獣の命を、すなわち人の罪を移した獣をほふって、その血を使って罪のあがないを祈願していた。血は命であるゆえ、罪はあがなわれるとしたのである。 だが、今回は違った。人(アロン家の大祭司イエスさま)が人の罪を「苦杯」という形で受けたのである。そしてあろうことか、ローマ軍の用意した十字架にユダヤ人によって架けられたのである。これが律法の下(もと)でイエスさまに成就するためには、イエスさまがユダ族ではなくアロン家の者でなければならなかったのです、とマリヤさまは言葉を続けられた。 |
| そしてユダヤ人の長老が言った、「そのためにはマリやさま、あなたはアロン家の姫さまでなくてはなりませんね。だが、エマオのアロン家は三十二年ほど前に自決して滅んだと聞いていますが」。マリヤさまはうなずいて話を続けられた、「あの折、わたしは十歳でした。ヘロデがその30年前に大祭司を名乗ったハスモン家を滅ぼして王になったのですが、今度は大祭司のアロン家を滅ぼそうとしました。その計画は父に洩れて、一族は殺される前に自決することになりました。ですが、父はわたしを生かそうとしました。 ベツレヘムからエルサレムに仕事に来ていたユダ族のヨセフは、エマオのわたしの家にも仕事に来ました。わたしは17歳のヨセフにとても懐(なつ)いていました。父は急いでヨセフの父に手紙を書き、ヨセフとわたしの婚約を頼みました。そしてその日、わたしをヨセフに伴わせて、ベツレヘムのヨセフの実家に行かせたのです。従者に荷物、特に聖書全巻を運ばせました。そして、ヨセフとの婚約の宴が設けられ、翌日ナザレのアロン家の所有地に疎開させたのです。「お父さま、なぜわたしだけ生き残らせられました。生き残っても、わたしはアロン家の子を産めないのです。わたしの産む子はユダ族の者なのです。なぜです」。来る日も来る日も、その嘆きは尽きませんでした。 二年ほどそのような日々が続きましたが、ある日、下着に血がつきました。ばあやに話すと「おめでとうございます、マリヤさま。十二歳ですね、大人(おとな)におなりですよ」と祝福してくれました。 |
| その時、宿屋の女主人が入ってきて、「マリやさま、お食事の用意ができました」と言った。広場はほのぼのとした雰囲気に包まれた。「長老さま、ルカさま、お二人もどうぞごいっしょに」とマリヤさまが二人に声をかけられた。「お供の方々は、下の食堂で召し上がっていただきます」。「祭りが終わりましたから、宿泊客が減りました。皆さんにもお泊りいただけます」、と女主人は言った。こうして三日目の日は過ぎていった。「イエスさまが現れて「苦杯と十字架」の意味を語り」、「イエスさまの死の意味が知りたいと、はるばるカペナウウムからやってきた異邦人とマリヤさまが言葉を交わされたことは、「何かが起ころうとしている」という予感を一同に感じさせた。 |
| 知りたい者と知らせたい者、ここに相集(あいつど)いて語り合う、 |
| マリヤさまはアラム語とギリシャ語、ルカはギリシャ語とアラム語、微妙なニュアンスはそれぞれの言葉で。 |
| その間「マリヤさま」を書いて出版を目指す。このサイト構築の13年間の集大成になるだろう。タイムリミットは1年に設定した。 |
| 2022/9/15、2025/2/9 |
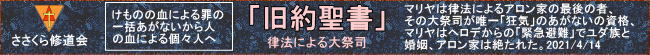 |
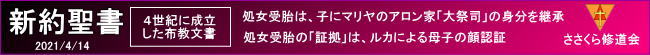 |
| 以下は旧文書 |
| 2020/10/14、15、16 |
| イエスの復活については、福音書はその多くを語らない。むしろパウロの手紙にその多くが記されている。しかし、その意味、あるいは目的は何であろうと疑問を呈した時、思い浮かんだのは、「苦杯と十字架」による「狂気(罪)のあがない」が「過去のものとならず、今を生きる者に有効であるため」だったのである。それは「パンとぶどう酒」を記念する儀式にもおよぶのである。 その「教祖」たる者が、世々生きている者とともにある、というのはキリスト教以外にはない概念であり実存であろう。だからこそ、正しい福音、聖母子にかかわる物語から信仰に入った人々の心から、「生命の光」が消えていくことはないのである。神は生きている者の神なのである。 |
| パウロ神学「復活」 「コリント人への第一の手紙」15章 15-35しかし、ある人は言うだろう。「どんなふうにして、死人がよみがえるのか。どんなからだをして来るのか」。 |
| 狂気からの開放 イエスが復活された「目的」は何であろう。天にのぼられ再びやってこられるという「再臨」思想は、イエスの復活の功徳(くどく)を消滅させている。では、ほんとうはどうなのであろう。この素朴な疑問を呈したとき、またもや、ふっとイメージが浮かんだ。 |
| 戻る |
| 「新約聖書」目次 |
| オリジナル教会の権能:「あなたの思うがままに作成してよい」 ページ制作者 (ささくら修道会)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2020/10/14、15、16 2022/9/15、2025/2/9 |
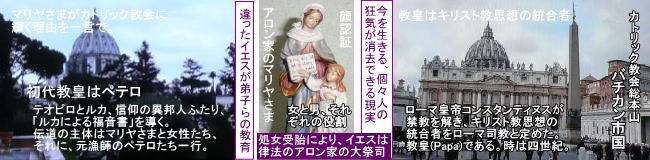 |
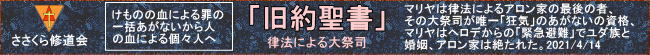 |
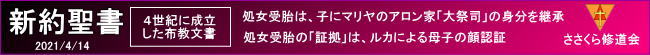 |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書、文語体聖書、バルバロ聖書差分の3つに限定する。これ以外の、聖書の引用は異端行為として厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version)世事に迎合した改編文章など異端以外の何ものでもない。(異端:=故意に対立すること) |
| ささくら修道会の指定聖書:「日本聖書協会 口語訳聖書」に準拠 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
わたしたちの「聖書」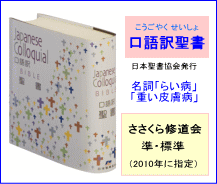 聖書の「らい病」 聖書の「らい病」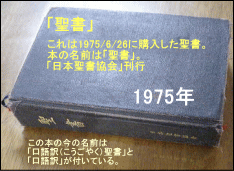 |
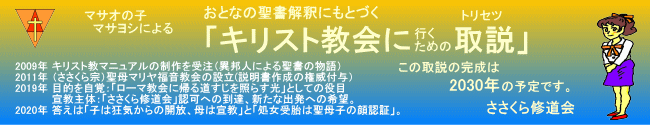 |
| トップ・ページ |