| 第1に、処刑中に芳香が漂うなどの奇跡が起こったということ、奇跡はやがて聖人と認められるための条件のひとつとなり、その慣行(かんこう)は列聖調査の中に取り入れられて、現在も変わらず続いています。 第2に遺骸への強い愛着です。古代の伝統宗教とキリスト教は、さまざまな価値観の相違がありましたが、中でも死生観(しせいかん)は大きく異なっており、両者の軋轢(あつれき)と衝突を助長(じょちょう)するものとなりました。 どちらも天の頂(いただき)を聖なる場所とするという点は変わりませんが、ローマ的な考え方では、死と生は隔離(かくり)すべきものでした。死者はネクロポリスという町外れの墓地に葬(ほうむ)られ、このような場所は彼らにとっては畏怖(いふ)の対象でした。また死者の身体は、やがて塵芥(ちり)(あくた)になるもの、朽(く)ち果てしまうもので、それ以上でもそれ以下でもないとみなします。 それに対してキリスト教徒は、遺体(いたい)をそのまま土葬(どそう)することで復活に備えますし、ポルカルポスの記録にもありますように、キリスト教徒の遺骸や遺物を聖なるものとして珍重(ちんとちょう)し、葬(ほうむ)られた場所に親しく詣(もう)でて礼拝をおこなうのです。 これはローマ人にとっては嫌悪(けんお)を催(もよお)す行為(こうい)でしたが、キリスト教徒にとっては信仰生活の重要な一部を形成するものでしたから、両者の溝は深かったといえるでしょう。 第3に、常に聖人の墓での記念集会が行われていた、ということです。あとでお話するようにこの習慣は四世紀以降(いこう)さらに発展します。 第4に殉教の日を誕生日かつ記念日としていた、という点です。キリスト教における死は、完全な終焉(しゅうえん)ではなく復活までの眠りとされます。つまり死は移行、あるところから別の場所への移行のひつにすぎないのだという考え方がそこにあります。死の瞬間から死者として新たな人生(じんせい)を生(い)きる、と言い換えることもできるでしょう。 ですから死を迎えた日は、次のフェーズに移行するため新生(しんせい)した記念すべき日です。生きている者はこのことを記憶にとどめるためさまざまな行事(ぎょうじ)をおこないます。このような死とのかかわり方は、中世(ちゅうせい)になっても基本的に変わることはありませんでした。むしろ死者のための典礼(てんれい)やとりなしといった観念、遺言書(ゆいごんしょ)や遺産の贈与(ぞうよ)、そして聖人崇敬(せいじん)(すうけい)といった形(かたち)で、つねに生(せい)と死は結びついていました。 その原型がここには見られます。このような意味でポルカルポスの殉教記録はたいへん古い記録ではありますが注目すべきものと言えるでしょう。 |
| NHK 2カルチャーラヂオ歴史再発見 「中世ヨーロッパ社会の光と影 キリスト教の果たした役割」 講師:上智大学准教授 藤崎衛(ふじさきまもる)氏 聴講内容のテキスト化: 笹倉正義(ささくらまさよし) |
| 次へ |
| (ささくら修道会規約)当会の用いる聖書は、口語訳聖書または文語体聖書に限られる。例外として、バルバロ聖書差分を、正式文書に加える。これ以外の、聖書の引用は厳禁される。日本語以外の聖書については、文語体聖書の内容に準じるものとする。異端文例(Today's English Version) |
いろいろ聖書 ささくら宗の聖書 ささくら宗の聖書 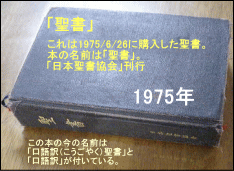 |
| ページ制作者 (ささくら宗)聖母マリヤ福音教会代表 笹倉正義 2019/8/8 指定聖書:日本聖書協会 口語訳聖書 新約聖書(1954年改訳) 旧約聖書(1955年改訳) バルバロ聖書(旧約差分) |
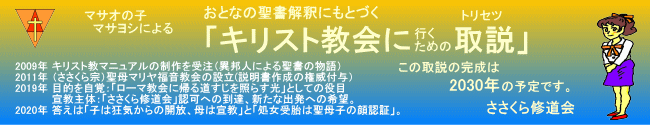 |