 (続き)プロテスタント雑記
(続き)プロテスタント雑記| (続き) (1)マルチン・ルターの場合、「ひょたうんからこま」だった。「パンドラの箱」とはちょっと違う。本来意図しなったものを出してしまったということであり、「宗教改革=プロテスタント」という言い方が浸透した。 時代は、オスマン・トルコが、東都コンスタンティノーブルを陥落させて60年余、その矛先をオーストリヤ、ドイツ(神聖ローマ帝国)に向けて侵攻を試みている時期であり、ドイツ皇帝カール五世は、スペイン王でもあって、その版図は広く、領土内領主たちとはうまくやっていく必要があった。ちょうどそのころローマでは、その富を人文のために使ったメディチ家出身の教皇が聖ペテロ寺院改築の巨費を捻出するため、免罪符の販売を思いつかれた。聖職者たちの多くは反対したであろうが、結局はその販売による巨利が財政を支えた。 皇帝カール五世が盟主のドイツ、そのドイツの諸侯の中には、教皇をけむたがる者もいたが、離脱のいんねんをつけるすきがなかった。そこに降ってわいたのが、自領の修道院の僧侶の一人が、目立つところに何かの抗議文を貼り出したという、ちょっとした事件だった。教皇に抗議するなんて、なんと向こう見ずな、おもしろいやつだろう。その抗議文の一節、「免罪符への疑問」に目をつけた反教皇諸侯たちは、自分たちのかつぐ「みこし」にその男を載せてしまった。 (2)これを契機に、反教皇諸侯たちの後ろ盾で、ローマ教会からの離脱がはじまった。この「離脱運動」は、ドイツから、北欧州へとまたたくまに広まった。ルターはなりゆきで、反教皇諸侯たちの「みこし」に載ったときから、その人生が思いもよらぬ方向をたどり、後戻りできないことを悟った。彼は修道院でも「哲学者」であったが、さらに哲学できる自由時間ができてしまった。反教皇諸侯にとっては、彼の「教え」が必要なわけではない。そこにいてさえくれればそれでいいのだ。そこで、彼は暇をもてあまし、「放談」するしかなかったのだ。大学で教えた聖書は旧約聖書の「創世記」、それはユダヤ人のための聖典ではないか。 キリスト教にとって、それらはイエスが キリストであることを論証する索引にすぎない。知恵によって人は救われない、それでは、「人は罪と死の前に無力なまま」の状態に後戻りである。 (3)ルターが反教皇諸侯の庇護のもとにあり、その「教え」そのものが離脱運動に関与していないことは、その道の人々にはすぐにわかったから、諸侯の力を借りない、いわゆる「改革派」なる一派が台頭した。 (4)英国もまた、気に食わないローマ教会から離脱したが、こちらは国王主導であり、自らの頭に自ら法冠を載せ、俗と聖の王を僭称(せんしょう)した。英国国教会(聖公会)の始まりである。この教会にもあきたらない人々は、「ピューリタン(清教徒)革命(1640年代)」を起こした。これからさらに「メソジスト(1730年代)」が起こった。偽物は偽物、神に重きを置かぬゆえ、つまり完全ではないゆえに、常に「分裂」の可能性をはらむ。そして分裂は分裂を呼ぶ。 (5)「プロテスタント」での一致は、反ローマ教会しかない。なので、教会の組織化、聖母マリヤは禁止。集会は「聖書」を中心とした牧師のメッセージが主体となる。信者はというと、聖書の中から自分を信仰に導く言葉「聖句」を見つけなければならない。推奨は、旧約聖書と「ヨハネによる福音書」である。はやい話、プロテスタントの信者は、哲学者へと導かれる。そこには、「答え」はないのであるが、その答えを知らない牧師たち自身も迷いに迷う。 (6)そこで、「説明書」制作途中であるわたしの気持ちは、「ローマ教会とプロテスタントの一致」は『「智によらない絶対従順がもたらした救い」と「答えを求めない智の海を好んで彷徨する哲学」』との一致を求めるようなものだ、に帰結する。 一致点があるとすれば、両者にある哲学者同士であり、「答えは求めない」という一致である。日本だけかも知れないが、せいぜい共同で聖書を訳し、一致点さぐる第一歩としましょうが関の山であるが、これは罠である。哲学者は、答えを出さない。理由は「宣教」という仕事をしないためである。 だから、翻訳のバージョンアップを繰り返す。信者はどの言葉を信じてよいのかわからなくなる。哲学者にとって、自分たちの思考(あるいは才能)の披露そのものが目的であって、信者のことなど何も考えてはいない。彼らにとっては、信者の数が増えること、「生めよ増えよ地に満ちよ」などには意味が無く、眼中にもない。これは、哲学者に浴びせるひどい言葉でもなんでもなく、冷静に「状態にある問題点」を見分ける目には、すぐにそれとわかるものである。 |
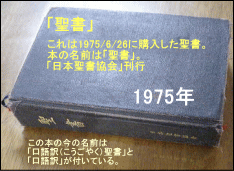 |
| (7)したがって、それにかわるスローガンは、「ローマ教会に帰ろう」が適当である。わたしの事業は、プロテスタント環境にある人々(信者をふくむ)への「聖母マリヤの聖なる愛と行動力」への認知度をあげる取り組みである。ローマの聖なる愛、すなわち聖母マリヤの愛に帰るのである。 (8)今では多くの国で個人の信教の自由が認められている。宣教が政権転覆を目論む連中に利用されない対策を立てておけば、政治不安の懸念を払拭し、これを認可する国も増える。聖なるものが、俗(政治)の思惑に利用されてはならない、とわたしは思う。 (9)インターネットの普及で、知りたい人には提供できる環境がある。インターネットは俗も聖も「何でもあり」の世界であり、それを必要とする人全員が見られるわけでもない。宣教においては、「情報収集に貧しい人」たちにも留意しなければならない。 (10)ローマ(カトリック)教会が提供するものは、哲学ではない。マリヤとイエスは、「処女受胎のしだい」と「十字架のおろかさ」、すなわち神への絶対服従という、世間の人々の絶対に真似のできない、究極の愚かさであり、そのゆえに神に属する二人である。マリヤとイエスは、地上においては人であったが、天においては「聖なる永遠の愛」と「永遠の大祭司」である。 わたしはこれを伝える裁可を得たい。信徒であるには、「アベ・マリヤ!マリヤはたたえられよ!」の唱和で足りるが、深く学びたい人には、「説明書」によってその道も開けている。 (11)プロテスタントの運動は、ローマ教会からの離脱運動の総称といえる。その「宗教改革」の実態は、アンチ聖母マリヤと「ヨハネによる福音書」による哲学である。彼らは、歴史を遡って「宗教改悪」をおこなっており、信者に提供すべき「答え」をはぐらかしている。人があがないきれない罪とか、死への恐怖への解決を、哲学(すき勝手に放談)によって混沌とさせ続けているのである。それを、広範囲にばらまいたのが、この「宗教改革」と自称している異端の実態である。 (12)コンスタンティヌス帝による改革 (1)諸派をまとめてひとつの頭とすること。−−>ローマ教会 (2)文書(聖書)を固定し、改ざんをゆるさないこと。−−>聖書 教皇グレゴリウスによる改革 (1)聖職者は独身であるべきこと。妻帯は許さぬこと。−−>教会規範 (2)プロテスタントは、聖書第一というが、都合の悪い「聖句」には目をつぶる傾向にある。聖書にこう書いてある。(パウロ神学「教師」) (13)プロテスタントの牧師 (コリント人への第一の手紙) 未婚の男子は主のことに心をくばって、どうかして主を喜ばせようとするが、7-33結婚している男子はこの世のことに心をくばって、どうかして妻を喜ばせようとして、その心が分かれるのである。7-34未婚の婦人とおとめとは、主のことに心をくばって、身も魂もきよくなろうとするが、結婚した婦人はこの世のことに心をくばって、どうかして夫を喜ばせようとする。 逆もまた真なり、でなければならない。すなわち、結婚したからには、お互いに配偶者を幸せにせねばならぬ。自分のことを考えるよりも先に相手のことを思うことが、信徒相互の模範となる。 読み返してみて、この(13)はいったい何のことだろうと思った。これは映画で見たことのある、とりすましていけ好かない牧師のことが記憶の片隅にあったからで、その男は結婚すると、妻となった女性を、まるで下女のように扱っていた。そんなこと、映画であろうと、わたしは許さない。 |
| メニューに戻る |
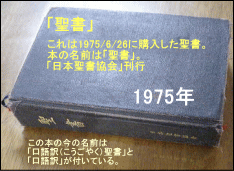 |