第四回 イエスと律法
(ラジオ放送のメモ:笹倉正義)
![]() 「新約聖書」とその時代
「新約聖書」とその時代
第四回 イエスと律法
(ラジオ放送のメモ:笹倉正義)
| カルチャーラジオNHK2東京青山のNHK文化センターで収録 歴史再発見 キリスト教の正典聖書の成立をたどる13回シリーズ 「新約聖書とその時代」 講師 千葉大学 「聖書学」 教授 加藤隆 4回目「イエスと律法」 2010/7/20 20:30-21:00 聴講ノート記録者 笹倉正義 1.福音書の内容について 福音書はイエスについての物語である、ということができる。イエスと書かれた物について、いくらか検討する。福音書はイエスの物語であって、イエスの活動について書かれている。このイエスについての情報は記されている情報の全てが生前のイエスの活動の事実を忠実に反映しているとは言えない。できるだけ忠実に伝えようとしても変化してしまう、最初の福音書であるマルコ福音書でさえ生前のイエスの事実から30年ほど経って成立したものである。生前のイエスのところで情報が発生してそれが伝えられて書き記されるまでに情報にさまざまな変化が加わってしまう。途中でいわばでっち上げられた情報もあるかもしれない。福音書に記されているイエスについての情報は生前のイエスの活動についての忠実な情報なのかどうかという観点からは間違った情報が含まれている可能性が常にあるものだということになる。 2.イエスに物語を残す意図はなかった こうした点を念頭に置いても、つぎの点は際立っている。つまり、生前のイエスは書かれた物を残そうとしなかった、という点である。そして、書かれた物ということになると、ユダヤ教の律法のことが問題になる。イエスはユダヤ人であり、ユダヤ教徒である。そして当時のユダヤ教は基本的に律法主義の立場にあった。当時の律法には書かれた律法と口頭の律法があった。書かれた律法はユダヤ教の聖書のことである。これをキリスト教では旧約聖書として引き継いでいる。 3.律法主義 律法主義とは、ユダヤ人ユダヤ教徒は日々の生活において全員律法にしたがわねばならない、ということである。律法にこのように定めれれているから、ユダヤ教徒はそれらを守った生活をしなければならない、とされているということである。また、何か問題が生じた場合には常に律法にはこのように書かれている、という議論をするのが律法主義である。書かれた物の権威があって、それに基づいて議論をし結論を導く。 4.律法の絶対的権威 現在の私たちにも書かれた法律がある。私たちもこの法律を守らねばならないが、法律自体に問題があるということになると、その法律を廃止したり、変更したりできる。場合によっては新しい法律を作れる。私たちの法律は究極のところ絶対ではない。しかし、律法は絶対的であり、一字一句変更できない、とされていて、それがいわゆるカロン(正典)になっている。律法の背後には神がいる。モーセを通じて神が民に与えた物、ということになっている。しかし、書き記された律法は、多量のものになっている。 5.律法と神との関係 神が背後にあるからこそ律法に権威があるが、律法は単なる神の言葉以上の権威があって、不動のものとして厳然と存在していて、動かせない。ユダヤ教徒はそうした律法に従うべきなので、神の新たな介入はもはや必要ではないとしてしまえる状態になっていた。キリスト教学会の批判の中にそういう傾向のあることが指摘されている。思い切って簡単に述べるならば、神との生き生きした関係において生きるのか、不動の律法に従って生きるのかが問題になっていたと思われる。 6.律法の成立、神と民との関係 歴史的な関係、重なるところがあるかも知れないが、重要なことなので、流れを確認する必要ある。イスラエルの民族の祖先たちは、紀元前13世紀に神によってエジプトから救い出されたということになって、出エジプトといわれている。このときに神は大きな恵みを民に与えた。このときに神と民の出会いがある。両者の間に絆が生じる。出エジプトの時に神との生き生きした関係において生きることが現実だった。 7.神の沈黙、民を捨てた しかし、神は沈黙してしまう。特に紀元前6世紀にはイスラエル民族の独立王国は、最終的に滅んでしまう。これ以降、ユダヤ人たちは大帝国の支配下で過ごすという状態が続いてイエスの時に至る。神は民に恵みを与えない。旧約聖書のユダヤ書に、民について、捨てられて苦悩する妻、つまり民は捨てられて苦悩する妻である、私はあなたを捨てた、という言葉がある。そのように預言者イザヤが確認した後、神は民に呼びかける、神は民を引き寄せる、将来において神と民との関係が修復されるだろうというような預言をイザヤは述べているが、こうしたことを宣言しなくてはならないことになっていること自体が民が捨てられた妻のような状態だった。 だからこそ、呼びかける引き寄せる、離れたから引き寄せることに意味がある。民が神に捨てられているという状態、神が民に恵みを与えずに沈黙しているという状態は民が神と生き生きした状態に生きることができない状態、こうした中で紀元前5世紀から4世紀ごろにかけてユダヤ教の聖書の編纂作業が始まった。ユダヤ教の聖書に含まれることになる文書が出揃うのは紀元前2世紀になってからである。内容が確定するのは紀元1世紀の後半、70年に終わったユダヤ戦争の後である。 伝統的には律法はモーセを通じて神が民に与えたものということになっている。聖書の内容にはモーセの伝えである紀元前13世紀に遡るものもあるかもしれないが、大部分はそれよりもずーっと後に成立したものが聖書の内容になっている。ユダヤ教の書かれた聖書は存在しなかった時代にもイスラエル民族には律法があったとう言い方は不可能ではない。 8.律法の遵守 しかし、ユダヤ教の聖書が存在し始めると、紀元前5世紀4世紀以降、律法の存在がはるかに確固としたものになった。そしてこの事態はイスラエル民族が独立王国を失ってからの時期である。神は沈黙している。手元には確固とした律法がある。神に忠実であろうとするならば律法を守るべきだ、ということにどうしてもなってしまう。神との生き生きした関係において生きるということは、神が沈黙しているので、いずれにしても不可能なので、不動の律法に従って生きるしかない、ということになる。捨てられた妻という比喩をイザヤ書で用いられているが、これを流用するならば、捨てられた妻がかつての夫が残した夫婦生活のきまり、そういうものが残っていてその文書を大切にして決まりを忠実に守ろうとするようなことだ、と言える。 9.イエスと律法 こうした中で、紀元後1世紀前半にイエスが登場する。これまでの説明の流れとの関連では、神との生き生きした関係において生きる、とうことがイエスにおいて再び可能になった。このことがイエスの意義だといえる。福音書の記述ではたとえば、聖霊が与えられる、神の子とされる、といった言い方がされているが、これが神との生き生きした関係において生きるという状態を示す典型的な表現と思われる。マルコ福音書のイエスの洗礼の場面だが、天が裂けてイエスに聖霊が与えられ、天の声が「あなたは私(神)の子」と宣言されたと記されている。 これは、さらに旧約聖書のイザヤ書の引用した箇所との関連でいうならば、長い間いなくなっていた夫が捨てられた妻のところに帰ってきたようなことである。生き生きした関係、夫婦の生活が再び可能になったことになる。こうした中で妻が大事にしていた夫婦生活の決まりを引き続き固守するというようなことはありえない、ということは分かると思う。目の前にいる夫と妻とで日々楽しくやっていけばいいのに、何か問題が生じた、あなたは1300年まえにこう言っているから、(ラジオの講師が笑った)こんなことが全てについて奥さんが持ち出す必要はない。目の前に夫がいるから。 イエスは既存の律法を否定する態度を示す。言葉においてでなく行動においてもこの立場を示した。たとえば、律法を守る必要がない、ということを示すために、罪人とされている人たちがユダヤ人社会にいて、罪人の人たちと共に同じテーブルについて食事をする、というのが律法で禁止されている。そのことをわざと皆に分かるように食事をする。安息日には働いてはいけないという有名な決まりがあるが、それなのに安息日にシナゴークというみんなが集まる集会所に行ってそこであく霊につかれている者からあく霊を追い出したりする。悪霊を追い出すというのは仕事だとされている、だからこれは安息日に仕事をしてはいけないという律法の規定に違反する行為を皆の前でやる、といことを冒頭でカファルナウムのシナゴークでそうしたことが行われて、ちっとも非難の声が上がらないので、イエスのほうもある意味ではがっかりしていてという感じがする。カファルナウムは小さないなか町だがそこでは律法違反という非難の声は上がらないでイエスのほうは拍子抜けしているようなエピソードがある。律法主義に対する批判はあるが、律法が守られていないということについての指摘も福音書に見られるということになる。イエスは律法を否定する態度をことごとく示した。神との生き生きした関係があるからこそ、律法を堂々と否定したということになる。 神との生き生きした関係があれば権威ある文書を再び作らないということも当然のこととして帰結する。イエスについての情報、これは重要ではない。重要なのは各人が神との生き生きした関係において生きる、という状態になることである。イエスが書いたものを残さなかったことについて、たとえイエスに書く能力がなくても、口述筆記をすればよい。当時は書く能力はあっても手紙や書物を執筆するときは秘書のようなものに口述筆記をさせることが普通だった。イエスは少なくとも一時はかなり影響力を持ってイエスにつき従う者も少なくなかった。もし、イエスに書いたものを残す意図があったならば、少なくともこの時期には執筆活動ができたはずである。したがってイエスが書いたものを残さなかったのは意図的なものだった、ということになる。 10.律法にかわる権威ある文書 イエス以降の流れ、さまざまな立場に分かれて、流れ全体において権威ある文書を再び作らない、という原則はかなり根強いものとして、残っていたと考えられる。そうした中で、十字架事件のあと30年ほどたって、マルコ福音書が書かれてしまう。そしてある程度権威あるものとして流布していたようだ。80年ぐらいまでマルコ福音書は消え去らないで、ある程度権威あるものとして流布していた、ということがマタイ、ルカの福音書の存在によって伺えることになる。 パウロが残したもの、手紙類は50年代のものが中心である。それらはやはり手紙である、広く権威あるものとして意図されていない。宛名になっている人たち、集団に意味あることを、その場限りのことを書くのが手紙である。パウロの手紙はユダヤ戦争後になるまで、ほとんど忘れられているような状態だったといえる。 11.主の兄弟ヤコブの立場 ユダヤ戦争の前の時期にキリスト教の中でユダヤ教の律法を尊重する流れが生じる。ペテロのエルサレム教会、ユダヤ戦争前の時期においては、その最初の指導者はペテロだが、途中でナンバー2の地位に落ちて、主の兄弟ヤコブという人が二代目の指導者になった。この主の兄弟ヤコブがキリスト教の流れの中でユダヤ教の律法を尊重する傾向をとる代表的な人物といってよい。神との生き生きした関係において生きる可能性についてヤコブとしては理屈としては理解できるけれども教会、エルサレム教会という組織ができているからメンバーがいる、そのメンバーの中には神からの聖霊が与えられていない者達、つまり神との生き生きした関係ができるという状態にまだなっていない者たちが集団を作るようになっていて、彼らを野放しにはできない、そしてユダヤ人出身の者については、あなたたちは従来の律法を守るように指導した、そういう風に考えられる。ヤコブは従来の律法を守ることは薦めても、権威ある文書を新たに作るということはしなかった、といってよい。また、非ユダヤ人出身のキリスト教徒のために、ユダヤ人の律法に相当するようなものも本格的に作成することもしなかった。やはり、基本的に神との生き生きした関係に生きる、ということが重要だった、といえる。 12.聖書研究の新たな立場 二資料説後の研究、聖書研究に新たな立場が生じ、研究用語ができた 1.様式史研究 2.編集史研究 と呼ばれている研究の立場は、重要である。 この二つは、20世紀の初めに共観福音書についての二資料説がある程度確定した後に、出てきた研究の立場である。 13.様式史研究(生前のイエスから福音書成立まで) 二資料説はマルコ、ルカ、マタイの3つの福音書の関係についての考え方である。この仮説では、生前のイエスと福音書、まずは最初に書かれたマルコ福音書との間のことは考えられていない。つまり、生前のイエスこのときからイエスについての情報がスタートするが、そこから福音書まで、まずマルコ福音書までの時期について、考えなくてはいけない。 二資料説の仮説の確定したあと、福音書研究の中心の課題になって、まずは様式史研究というものである。これはイエスの出来事が生じて、それが最初にマルコ福音書に本格的に書かれるまでの30年間ほどの間のことが中心に扱われている。この期間、イエスについての情報は、基本的に口頭のものであった。口で伝えられていた。しかし、この期間についてしるためのドキュメント、資料というものは現代の研究者に残られているものは福音書のテキストしかない。そこでそれをぐっとにらんで考える、ということになる。 14.テキストは日常的な口頭伝承の立場 福音書のテキストにはイエスのことが書かれている。しかし、イエスのことなら何でもかんでも書かれている、というのではない。たとえば、イエスの姿について、どのような顔だったのか、どのような体つきだったのか、といったことは一切かかれていない。そうではなくて、いくつかに分けられるようなイエスの情報しかない、ということにだんだん気がついてきた。たとえば、イエスが自分の立場に賛同するように、こうなりなさい、と薦めるような言葉、それから常にイエスの仲間である人たちにその立場を維持しなさいと励ます言葉、キリスト教徒としての生活に関するさまざまな教え、生活の内外部の態度についての教え、いろいろな対場からさまざまな批判をキリスト教が受けるからそれなの批判に対してイエスが巧妙に反論したというエピソード、奇跡物語、こうしたいくつかのジャンルのことばかりが福音書に残っている、というふうに気がついてくる。こうしたことから、イエスについての情報はある限定された特定の範囲の関心のある者たちが伝えてきたから、こうしたジャンルのものしか残っていない、というふうに考えられる。 このイエスの情報を30年の間、ある程度以上の数ものを伝えてきたものというのは、結論的にいうとイエスに賛同する者たち、つまりキリスト教会のメンバーだったということになる。そして彼らの日々の日常的な教会活動にとって意味があるとすれば、イエスの情報が教会活動の中で繰り返し用いられるということがあって、これらイエスの情報が30年間失われずに残されてきたと考えられる。つまり福音書に見られるようなイエスの情報は、それまでのキリスト教の教会という社会的な状況に左右されていて、そこで意味のあるものばかりだということになる。 15.口頭伝承の立場、民俗学がヒント このことは福音書に見られるイエスの情報を吟味すれば、それ以前の紀元後の1世紀当時のキリスト教会が置かれていた状況がかなり具体的に推測できるとうことになる。キリスト教史研究にとって重要な新しい見方になる。こうした観点というのは、新約聖書学の中で初めて発見されたというのではなくて、民俗学というかフォアクロアの研究のあり方にヒントを得て、新約聖書でも適用されるようになったと言われている。具体的には新約聖書においてこの研究が始まったのは20世紀はじめからであるが、19世紀の後半ぐらいにドイツで、このころこうした分野の研究はドイツが圧倒的に優秀だったけれども、グリム兄弟の名前が有名だが、民衆の間に伝わっているおとぎ話を採集してくる、中世における民衆たちの社会的状況を知りたいという関心かなのものだった、と言われている。つまり、中世の民衆の生活の状況ついての資料、データは残っていない、残っているものは伝えられてきているおとぎ話だ、おとぎ話を集めてきて、なぜそのような内容のおとぎ話が長い間伝えられてきたのかというと、それを伝えてきた民衆たちが中世以来関心をずーっと持ってきたからだ。だから、おとぎ話の特徴を分析していけば彼らが持っていた関心を推測できて、そういったことに関心を持つことになる社会状況に彼らが置かれていたからだ。こういう方ほうが考えられて、適用されていたのを新約聖書学に用いた。これを様式史研究という。 この観点から福音書に記されているさまざまなテキストのつながりの悪いところ、細かいところまでを見つけ出して、それは別々の言い伝えを無理につなげているからだ。福音書記者がまとめた文書を書く前のイエスのばらばらな情報、口頭で伝えられたばらばらな状態に戻して、そしてそれぞれのイエスの情報がキリスト教会の生活の中でどのような意味があったのかという風に考え、こういう作業が行われるということになった。その結果どういうことになったか。 16.編集史研究の立場 マルコ福音書ならマルコ福音書のテキストについて、この部分はつながりが悪いという議論をしてばらばらにしてしまう。そのためにマルコ福音書のつながりの悪い情報を無理につなげると支離滅裂の物語になるというイメージになった。確かにつながりが悪い、ぱっと読んでどうしてこういう議論になるのかと思うような箇所も多々あるテキストだが、ただそうした支離滅裂なテキストなのだろうか、という反省がだんだん起こってくる、それが2番目の編集史研究という立場で、マルコがさまざまなイエスについての情報言い伝えを集めてきて自分のテキストを書くが、それらを編集している。集めてきたものを使う、そのまま使うこともある、変更することもある、そうした作業を行って、マルコはマルコなりの最終的なテキストを作ったのだ。そのことに注目して、それを編集のプロセス、編集史という研究、それぞれの成果がでるようになったのは20世紀半ばぐらいからだ。 それ以降の研究は個々の伝承の所在のことを意識して、各文書のまとまった立場についても配慮する、すくなくともこの二つのことを配慮しながら作業しなければならない、ということになっている。 |
| 次へ |
ページ制作者:ささくら修道会 総長 笹倉正義
2017/8/20(コード変更 utf-jis)
指定聖書:日本聖書協会 口語訳聖書
旧約聖書(1955年改訳)
新約聖書(1954年改訳)
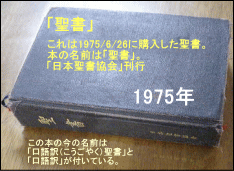 |