 |
| 第十二歌(上P311) ----冥府の話に続いて語られる、アルキノオス王の宮殿でのオデュッセウスの話である。 (9)キルケの島に戻る (12-1)(12-2)(12-3)(12-4)(12-5)(12-6)(12-7) 「オケアノス河の流れを後にした船は、波騒(なみさわ)ぐ広い海原に出て、朝のまだきに生まれる曙(あけぼの)の女神の住居(すまい)と踊り場があり、陽の神の上り口なるアイアイエの島に達したが、この地に着くと船を砂浜に揚げ、浜の渚(なぎさ)に降り立つと、そこでぐっすりと眠り込んで、輝く曙の到来を待った。(12-1-7) (12-8)(12-9)(12-10)(12-11)(12-12)(12-13)(12-14)(12-15) 朝のまだきに生れ指ばら色の曙の女神が姿を現わすと、わたしは死んだエルペノルの遺骸を引き取るために、部下の幾人かをキルケの屋敷へ遣(ツカ)った。それからわれらは直ぐに木を伐(き)り出し、海に突き出た岬の端で、大粒の涙をこぼしながら、悲しみの内に彼の葬(トムラ)いをしてやった。遺骸と故人の武具が焼けた後、塚を築き墓石を曳き上げてそこへ据え、塚の頂きに彼の遺愛の、手頃に作りなした櫂(かい)を立ててやった。(12-8-15) (12-16)(12-17)(12-18)(12-19)(12-20)(12-21)(12-22)(12-23) (12-24)(12-25)(12-26)(12-27) こうしてわれらはこれらの仕事を一つずつ片付けていたが、もとよりわれらが冥府から帰ったのを、キルケが気付かぬはずはなく、早速(さっそく)身繕(みづくろ)いをして現われ、彼女に随う女中たちが、パンに多量の肉、それに燃えるが如き赤葡萄酒を持参してくれた。 第十二歌(P312) 美(ウル)わしい女神は一同の真中(まんなか)に立って口を切り、『生きながら冥王の館に降(くだ)ったとは、なんとも不敵(ふてき)な人々じゃ。ほかの人間なら一度しか死なぬものを、そなたらは二度も死ぬのだからな。さあ今はここでひもすがら食物をとり、葡萄酒を飲んで過しなさい。そして曙の女神が現われたら、直(す)ぐに船を出すのです。 道筋も示そうし、その他(ほか)必要なことも一切わたしが教えてあげよう。海上であれ陸上であれ、そなたらがなんらかの恐るべき奸計にかかって難を蒙(こうむ)り、苦しむようなことがあってはならぬからな』。(12-16-27) (12-28)(12-29)(12-30)(12-31)(12-32)(12-33)(12-34)(12-35) (12-36)(12-37)(12-38)(12-39)(12-40)(12-41)(12-42)(12-43) (12-44)(12-45)(12-46)(12-47)(12-48)(12-49)(12-50)(12-51) (12-52)(12-53)(12-54) こういう女神の言葉に、われらの心も納得した。こうしてこの時は日がな一日、陽の沈むまでここに尻を落ち着けて、ふんだんにある肉を食べ、旨い酒を飲んで過したのであったが、やがて陽が落ち夕闇が訪れると、部下たちは、船の艫(とも)のお辺りで眠りに就いた。 キルケはわたしの手を取ると、わたしの親愛なる部下たちから離れた場所へ連れて行ってわたしを坐らせ、自分はその傍(かたわ)らで横になって、これまでの事の次第を逐一訊ねたのだ。そこでわたしは順を追って、一部始終を彼女に物語ったのだが、すると女神はわたしに向かっていうには、 『よろしい、それで万事片付いたわけじゃ。そこでこれからわたしのいうことを、よくお聞きなさい。それに神もどなたかが、そなたにそれを思い出すようにして下さるでしょう。そなたはこれから先ず、セイレンたちの所へゆくことになるが、この者たちは自分に近付く人間はこれを悉(ことごと)く惑わす魔力を具(そな)えており、知らずして近付き、セイレンたちの声を聞いた者は、もはや家郷に帰って妻や幼な子に囲まれ、その喜ぶ顔を見ることはかなわぬ。 セイレンたちは草原に坐って、すき通るような声で歌い、人の心を魅惑する。セイレンたちの周りには、腐りゆく人間の白骨がうず高く積もり、骨にまつわる皮膚もしなびてゆく。そなたはここを漕ぎ抜けねばならぬが、そなたのほかは誰も声を聞けぬように、甘い蜜蝋を捏(こ)ね、これを部下の耳に貼りつけなさい。 しかしもしそなたが自分だけは聞きたいと思うなら、そなたは帆柱の根元に真直(まっす)ぐに立ち、部下に命じて手足を縛らせ、縄の端を帆柱に結(ゆわ)えつけなさい。さすれば楽しくセイレンたちの声を聞くことができる。万一そなたが部下に縄を解いてくれと、頼んだり命じたりした場合には、さらに綱を増して縛らせるのです。(12-28-54) (12-55)(12-56)(12-57)(12-58)(12-59)(12-60)(12-61)(12-62) (12-63)(12-64)(12-65)(12-66)(12-67)(12-68)(12-69)(12-70) (12-71)(12-72) しかし部下たちが漕ぎ抜けた後は、二つの進路のどちらをとるかについて、もはやわたしから事細(ことこま)かに話すつもりはない−−−それはそなた自身、心の内で思案しなさい。わたしからはその二つの進路のことを話してあげよう。一方の路(みち)では、険(けわ)しく切り立った岩があり、海の女神、青黒い眼のアンピトリテの大波が、凄まじい音を立てて撃ち当っている。 これは至福の神々の間では「さまよう岩(プランクタイ)」の名で呼ばれている岩礁(がんしょう)で、ここは空飛ぶ鳥も通り抜けることができぬ、いやそれどころか、父神ゼウスの召し上がるアンブロシアを運ぶ気弱な鳩さえ、無事にここを越えることができず、すべすべとした岩は、必ずその一羽を捕えるので、父神はその数を補うべく、さらに一羽を送られるほどなのです。 人の乗る船も、ここへ来て無事に逃れ得たものは、かつて一艘だになく、船の板も人の死骸も波に揉(も)まれ、また業火の渦巻く疾風に煽(あお)られて、こなたかなたへ漂う有様、海原渡る船でここを越えたのは一艘のみ、アイエテスの許から帰るさの、その名(な)天下(てんか)に轟くアルゴ船がそれで、この船とてもこの時忽(たちま)ち波が巨岩に撃ちつけていたでもあろうに、イエソン(イアソン)はヘレ御寵愛の勇士であったので、女神が無事に通しておやりになったのです。(12-55-72) ---イアソンが通過した後、この岩は、動かなくなったと書かれている。 (参照)アルゴ探検隊 アポロドロス「ギリシャ神話」 1-9-22ハルピュイアどもから救われてピネウスはアルゴナウタイにその航海の路(みち)を示し、海中にあるシュムプレガデス岩について忠告を与えた。この岩は非常に大きく、風の力によって互いに相会して激突し、航海を塞(ふさ)ぐのである。岩上には深い霧がかかり、轟々(ごうごう)と鳴りひびき、翼あるものといえども岩と岩との間を通り抜けることはできない。そこで王は彼らに一羽の鳩を岩と岩との間に放(はな)って、もしこの鳩が無事に(通過したのを見た)場合には、心を許してそこを通航し、もし鳩がだめだったのを見た場合には無理に通ってはならないと言った。 これを聞いて彼らは海に出た。そして岩の近くに来た時に船首(せんしゅ)から一羽(いちわ)の鳩を放った。飛ぶ鳩の尾の端(はし)を岩が合して切り取った。そこで岩が再び退(しりぞ)くのを待機していて、力(ちから)いっぱいに漕(こ)ぎ、またヘラの助けによって、彼らは通り抜けたが、飾り艫(とも:船尾)の端がすっかり切り取られてしまった。 それ以来シュムプレーガデス岩は凝(じつ)として立っている。というのは船が一隻(いっせき)通り抜ければ、岩は全く動かなくなると定まっていたからである。 第十二歌(P317) キルケの島を出帆 (12-142)(12-143)(12-144)(12-145)(12-146)(12-147)(12-148) (12-149)(12-150)(12-151)(12-152)(12-153)(12-154)(12-155) (12-156)(12-157)(12-158)(12-159)(12-160)(12-161)(12-162) (12-163)(12-164) キルケはこのように話したが、ほどなく黄金の椅子に座す曙の女神が訪れ、世にも麗しき女神は、島の奥へと立ち去って行った。わたしは船に戻って部下を促(うなが)し、乗船して艫綱(ともづな)を解けと命じた。彼らは直ぐに乗り込んで漕座に就き、順序よく並んで坐ると、灰色の海を櫂で打ち始めた。 紺青の舳先(へさき)の船の後からは、帆をふくらます順風を−−−船旅にはこよなき友を、人語を話す怖るべき神、髪美わしきキルケが送ってくれた。 直ぐにわれらは船内の索具の操作をすべて終えて腰をおろし、あとは風と舵手とが進路を定めて船を進めるばかり。(以下の文塊番号は省略)(12-142-164) (10)セイレンの島を通過 第十二歌(上P319) (12-165)(12-166)(12-167)(12-168)(12-169)(12-170)(12-171) (12-172)(12-173)(12-174)(12-175)(12-176)(12-177)(12-178) (12-179)(12-180)(12-181)(12-182)(12-183)(12-184)(12-185) (12-186)(12-187)(12-188)(12-189)(12-190)(12-191) このようにわたしは部下たちに仔細(しさい)を語り聞かせたが、その間にもわれらの堅牢な造りの船は、穏やかな順風を背にして船脚(ふなあし)も速く、二人のセイレンの住む島に着いた。ところがこの時俄(にわ)かに風がやみ、風のない海は凪(な)ぎかえって、神は波浪を眠らせてしまわれた。 部下たちは立ち上がって帆を捲き上げ、これを船倉に納めると櫂の前に坐って、滑らかに削った櫂を動かし、海に白波を立て始めた。わたしは大きな輪型の蝋を、鋭利の剣で細かく切り刻み、逞(たくま)しい手で圧して捏(こ)ねると、圧し手の強い力と、陽の神ヒュペリオニデスの光に温められて、蝋は忽(たちま)ち熱く(柔らかに)なった。そこでわたしは順々に、部下たち全員の耳に蝋を貼りつけると、彼らは船中で帆柱の根元に立ったわたしを手足ともに縛り、縄の両端を帆柱に括(くく)りつけた。 部下たちは漕座(こぎざ)に坐(すわ)って、櫂(かい)で灰色の海を打っていたが、速やかに船を進めて、呼べば声の届くほどの距離まで近寄った時、船脚(ふなあし)速き船が近くに迫ったのを、セイレンたちが気付かぬはずもなく、朗々たる声を張り上げて歌い始めた。 『アカイア勢の大いなる誇り、広く世に称(たた)えられるオデュッセウスよ、さあ、ここへ来て船を停(と)め、わたしらの声をお聞き。これまで黒塗りの船でこの地に訪れた者で、わたしらの口許(くちもと)から流れる、蜜の如く甘い声を聞かずして、行き過ぎた者はないのだよ。 聞いた者は心楽しく知識も増して帰ってゆく。わたしらは、アルゴス、トロイの両軍が、神々の御旨(みむね)のままに、トロイの広き野で嘗(な)めた苦難の数々を残らず知っている。また、ものみなを養う大地の上で起こることごとも、みな知っている」。(12-165-191) (12-192)(12-193)(12-194)(12-195)(12-196)(12-197)(12-198) (12-199)(12-200) 美しい声を発してこういった。わたしは心中(しんちゅう)、聞きたくて耐(タマ)らず、眉(まゆ)を動かして合図し、部下に縛(イマシ)めを解けと促したが、彼らは前に身をかがめてひたすら漕ぎ進める。ペリメデスとエウリュロコスの二人が、つと立ち上がると縄の数を増してさらに強く締め上げた。しかしセイレンたちを行き過ぎ、もはやその声も歌も聞こえぬようになると、わが忠実な部下たちは直(す)ぐに、わたしが耳に貼り付けてやった蝋(ろう)を取り去り、わたしの縄を解いてくれた。(12-192-200) (11)岩の狭間(はざま)を目前に 第十二歌(P320) (12-201)(12-202)(12-203)(12-204)(12-205)(12-206)(12-207) (12-208)(12-209)(12-210)(12-211)(12-212)(12-213)(12-214) (12-215)(12-216)(12-217)(12-218)(12-219)(12-220)(12-221) ところがこの島を後にして進んでいる時、突如煙と大波が目に入り、轟々(ごうごう)たる響きを聞いた。恐れをなした部下たちの手から櫂(かい)が放れ、櫂は音を立てて悉(ことごと)く潮流(ちょうりゅう)に落ちた。彼らはもはや先の尖った櫂を漕がぬので、船はその場に停(と)まってしまった。わたしはしかし、船中(せんちゅう)を廻り部下の一人一人の傍(かたわ)らへ立って、穏やかな言葉で激励した。 『親愛なる者たちよ、われらはこれまでも危難を知らずに来たわけではない。今の場合も、キュクロプスが恐るべき暴力をふるって、われらをうつろな洞窟に封じ籠めた時にまさる危難とはいえぬ。しかもその時ですら、わたしの勇気と知略と才覚とによって、無事に難を免(まぬ)れたではないか。 現在の難儀もいつの日かよい思い出になるであろう。さればわれら一同心を合せ、これからわたしのいう通りにしてもらいたい。そなたらは漕座に坐り、あるいはゼウスがわれらに、この危地を免れることをお許し下さるかも知れぬと心に念じつつ、岩に砕ける大波を櫂で打ってゆくのだ。 さて、舵取りのそなたには、次のように申し付けておく。そなたは船の舵をとる役であるから、よく肝に銘じておくのだぞ。船をあの煙と大波から離して進め、岩を目指して行け。そなたがうっかりしているうちに、船が彼方(かなた)へ突進し、そなたのせいでわれらが破滅の淵へ陥るようなことがあってはならぬからな』。(12-201-221) ---部下の名前がないのは・・・ (12-222)(12-223)(12-224)(12-225)(12-226)(12-227)(12-228) (12-229)(12-230)(12-231)(12-232)(12-233) こういうと、一同は直ぐにわたしの言葉に随(したが)った。スキュレについては、なんとも手の施(ほどこ)しようのない災厄(さいやく)であるから、もはや何もいわなかった。部下たちが恐怖の余り、漕ぐのをやめ、船内に一塊(ひとかたまり)になってかがみ込んでしまいはせぬかと恐れたからであった。 第十二歌(P321)スキュレを見張る この時わたしは、わたしにとっては辛(つら)い忠告−−−武装して戦ってはならぬというキルケの忠告は忘れることにし、わたしは見事な武具を身につけ、二本の長槍を手にすると、船首(せんしゅ)の前甲板(かんぱん)へ歩いて行った。まずここから、やがてわたしの部下たちに惨禍(さんか)をもたらすべき、岩棲みのスキュレの姿が見られると思ったからだ。ところが、どこにもその姿を見ることができぬ。薄暗(うすぐらい)い岩に向って、あちらこちらを窺(うかが)っているうちに、目が疲れてきた。(12-222-233) (12-234)(12-235)(12-236)(12-237)(12-238)(12-239)(12-240) (12-241)(12-242)(12-243)(12-244)(12-245)(12-246)(12-247) (12-248)(12-249)(12-250)(12-251)(12-252)(12-253)(12-254) (12-255)(12-256)(12-257)(12-258)(12-259) われらは歎きのうちに、岩の狭間(はざま)を漕ぎ抜けて行った。一方にはスキュレが控えているし、他方では恐るべきカリュブディスが、凄まじい勢いで海の塩辛(しおから)い水を吸い込んでいる。そして吐き出す時には、さながら燃えさかる火にかけた鍋の如く、その全体がぐらぐらと煮えたぎり、吹き上げられた泡がしぶきとなって、二つの岩の頂(いただ)きに降りかかる。 第十二歌(P322) ところが塩辛い海水を嚥(の)み下す時には、全体が渦をなしてその内側が露(あら)わに見え、岩はあたり一面に凄(すさ)まじく鳴り響いて、底には砂で青黒く見える地面が現われる。一同は青白(あおじろ)い恐怖に襲われたが、われらが身の破滅を恐れてカリュブディスに気をとられ、その方を眺めている隙(すき)に、スキュレは腕力最もすぐれた六人の部下を、うつろな船からさらって行った。 振り返って目を船にやり、部下たちの方を見た途端、空中に吊り上げられた部下たちの手足を頭上(ずじょう)に見たのだ。彼らは悲歎(ひたん)に暮れながら、わたしの名を呼んで声をかけてきたが、それが彼らの最後の呼びかけとなった。 それはたとえば海に突き出た岩に立つ釣人(つりびと)が、長い釣竿(つりざお)で小魚(こざかな)に誘いの餌を投ぜ(とうぜ)んと、野に棲む牛の角(つの)を海中に抛(ほう)り込み、もがく魚を捕(とら)えて水からあげる如く、部下たちは身もだえしつつ岩に曳き上げられてゆく。 スキュレは自分の棲家(すみか)の門口(かどぐち)で、断末魔(だんまつま)の苦しみに悲鳴をあげながらわたしの方へ手をさし伸べる部下たちを食ってしまった。海の道々を探りながら、幾多の苦しみを味わったわたしではあるが、これほどの憐れな光景を目にしたことはかつてなかった。(12-234-259) 第十二歌(P322) (12)陽の神の島にて (12-260)(12-261)(12-262)(12-263)(12-264)(12-265)(12-266) (12-267)(12-268)(12-269)(12-270)(12-271)(12-272)(12-273) (12-274)(12-275)(12-276) しかし危険な岩から離れ、おそるべきカリュブディスとスキュレから逃(のが)れた後、われらは程もなく神の麗わしい島に到着した。ここには陽の神ヒュペリオンの飼う、額(ひたい)の広い見事な牛と丸々と肥えた羊の大群がいた。この時わたしはまだ海上の船中にあったのだが、牛舎(ぎゅうしゃ)に戻された牛の声や、羊の鳴き声をすでに聞いた。 すると途端に、テバイの盲目の予言者テイレシアス(冥府)と、アイアイエのキルケの言葉が胸に浮んだ−−−二人はわたしに、くれぐれも人間に喜びをもたらす陽の神の島は避けよと、繰り返し警告してくれたのであった。そこでわたしは、悲痛な想いで部下たちにいうには、 『戦友たちよ、そなたらは苦難続きで気の毒なことだが、しばらくわたしの話を聞いてくれ。テイレシアスと、アイアイエのキルケとが告げてくれた予言を、そなたらに話したいと思うからだ。この二人とともに、人間を喜ばす陽の島は避けよと、わたしに繰り返し警告してくれた。ここではわれらにとって恐るべき災厄(さいやく)が起るといったのだ。さればそなたらは、この島を通り抜けて船を進めてくれ』。(12-260-276) 第十二歌(P323)悪党エウリュロコス (12-277)(12-278)(12-279)(12-280)(12-281)(12-282)(12-283) (12-284)(12-285)(12-286)(12-287)(12-288)(12-289)(12-290) (12-291)(12-292)(12-293) こういうと一同はすっかり落胆したが、たちまちエウリュロコスが、憎々しげな口調で答えていうには、『オデュッセウスよ、あなたはなんともしたたかなお人だな。力は衆に勝れ、体は疲れを知らぬ。あなたは全身悉(ことごと)く鉄で出来ているに相違ない、疲労と寝不足(ねぶそく)で弱り切った仲間たちが、陸に上がるのを許さぬとはな。 陸に上がれば海に囲まれた島の上で、旨い夕食を作れるものを、このまま島を外(はず)れて足早な夜の闇を縫い、霧立ち籠める海上(かいじょう)をさまよえと申される。夜ともなれば、船を損(そこな)う害敵たる、さまざまな恐ろしい風が起こる。どうかして突如突風に襲われたならば、どのようにして苛酷な破滅を逃れたらよいのだ、それは南風か西風か、いずれも神々の思惑もものかは、船を粉々に砕くことの最も多い風ですぞ。 そこで今は、黒き夜のいうことを聴くとして、船の傍らで夕餉をととのえよう。そして夜が明けたならば、乗船して広い海原(うなばら)に乗り出したらいかがかな』。(12-277-293) (上P324) (12-294)(12-295)(12-296)(12-297)(12-298)(12-299)(12-300) (12-301)(12-302) エウリュロコスがこういうと、他の部下たちもこれに賛成した。この時わたしは、たしかにいずれかの神が、われらに禍難を企んでおられることが判ったので、エウリュロコスに翼ある言葉をかけていうには、 『エウリュロコスよ、わたしひとりが相手だというので、無理強(むりじ)いして否やをいわせぬつもりだな。よろしい、だがここで全員わたしに固く誓ってくれ、たとえ牛の群や羊の大群を見付けても、怪しからぬ驕慢(きょうまん)心から、牛または羊を屠るようなことは決してせぬとな。その代わり、女神キルケのくれた食料は好きなように食べるがよい』。(12-294-302) (上P325) (12-303)(12-304)(12-305)(12-306)(12-307)(12-308)(12-309) (12-310)(12-311)(12-312)(12-313)(12-314)(12-315)(12-316) (12-317)(12-318)(12-319)(12-320)(12-321)(12-322)(12-323) わたしがこういうと、一同は直ぐにわたしが要求した通り、禁じられたことはせぬと宣誓した。彼らが誓い、誓い終えるとわれらは港のふところの、甘美な清水の湧く場所に近く、船を停め、部下たちは船をおりて、手際よく夕餉をととのえた。やがて飲食の欲を払い去ると、今度は船内からさらわれてスキュレの餌食となった、親愛なる僚友たちを偲(しの)んで泣き悲しんだが、悲しむうちに甘い眠りが訪れてきた。 すでに夜もその三分の二を過ぎ、星々も沈みかけた頃、雲を集めるゼウスは激しい風を送って凄まじい嵐を起し、大地も海ももろともに黒雲で蔽(おお)ってしまわれ、夜の闇が上天から降ってきた。朝のまだきに生れ指ばら色の曙(あけぼの)の女神が姿を現すと、われらは船を空(うつ)ろな洞窟に曳き入れてそこに泊めた。ここにはニンフたちの美しい踊り場と、彼女らの坐る席とがあった。 さてそこでわたしは一同を集めて申し聞かせるには、『親愛なる戦友たちよ、船には食い物も飲み物もある、さればわれらは災難を避けるため、ここの牛には手を触れぬようにしよう。これなる牛や肥えた羊の群は、恐るべき神−−−この世のあらゆるものを見、あらゆることをお聞きなされる陽の神の持ち物であるからな』。(12-303-323) 第十二歌(上P326) (12-324)(12-325)(12-326)(12-327)(12-328)(12-329)(12-330) (12-331)(12-332)(12-333)(12-334)(12-335)(12-336)(12-337) (12-338)(12-339)(12-340)(12-341)(12-342)(12-343)(12-344) (12-345)(12-346)(12-347)(12-348)(12-349)(12-350)(12-351) わたしがこういうと、彼らの勇猛な心も納得した。ところが南風は丸一月の間やまず吹き続け、東と南の風以外の風は一つも起らない。部下たちも、穀物と赤い酒のある間は、さすがに命が惜しくて牛には手を付けなかったが、やがて船内の貯えも悉(ことごと)く尽きると、もはや背に腹は代えられず、獲物を求めて歩き廻り、魚であれ鳥であれ、手に入るものは何でも、曲った針で捕えたりしていた。 飢えが胃袋を苛(さいな)むのだ。丁度このような時にわたしは、われらに帰国の道を示して下さる神もあろうかと、神々に祈るべく島の奥へ入って行った。島の中を歩んでなんとか部下たちから離れると、風の当らぬ場所で手を浄<きよ>めオリンポスに住まいます、よろずの神々に祈願した。ところが神々は、わたしの瞼に甘美の眠りを振りかけられたのだ。一方エウリュロコスは、仲間たちによからぬ企みを吹き込み始めた。 『戦友たちよ、禍難に苦しむそなたらであるが、わたしのいうところを聞いてくれ。惨めな人間にとって、いかなる形の死も厭(いと)わしいものだが、飢えのために死んで命を落とすより情ない死に方はない。そこでどうだ、陽の神の牛の群の中から、特に良い牛を幾頭か曳いてきて、広き天に住まいます神々に、お供えしようではないか。 幸いに故国イタケに帰還できたら、その時は直ぐに陽の神ヒュペリオンに、壮麗な社を築き、いろいろと見事な品を奉納しよう。万一、陽の神が真直ぐに角の立つ牛のことで立腹なさり、われらの船を破壊しようと思われて、他の神々もそれに随うようなことになっても、わしは波を呑んで一思(ひとおも)いに命を落とす方が、いつまでもこの無人の孤島に留まって、じわじわと弱ってゆくよりましじゃ』。(12-324-351) 第十二歌(上P327) (12-352)(12-353)(12-354)(12-355)(12-356)(12-357)(12-358) (12-359)(12-360)(12-361)(12-362)(12-363)(12-364)(12-365) エウリュロコスがこういうと、他の部下たちも賛成した。そこで早速近くにいる陽の神の牛の群から、特に良い牛を選んで曳いてきたのだが、それというのも、角曲り額の広い見事な牛の群はいつも、紺青色の舳先(へさき)の船から、程遠からぬところで草を食(は)んでいたからで、彼らは牛を囲んで立ち、梢(こずえ)も高く聳え立つ樫の木の、柔らかな葉を摘み取って、神々に祈願した。 堅牢な造りの船には、もはや白い大麦の貯(たくわ)えがなかったからだが、祈願を終えると牛を屠(ほふ)って皮を剥(は)ぎ、腿(もも)の部分を切り取って、二重に畳んだ脂身(あぶらみ)でそれを蔽い、その上に生肉を載せる。 燃えている生贄(いけにえ)に注ぐ葡萄酒の持ち合わせもないので、水を代用して灌祭(かんさい)をお済ませ、臓腑を全部炙(あぶ)る。腿がすっかり焼き上がり、自分たちも臓腑を食べ終わると、残りの肉を細かく切って焼串に刺す。(12-352-365) (12-366)(12-367)(12-368)(12-369)(12-370)(12-371)(12-372)(12-373) 丁度その頃、わたしの瞼から甘い眠りが去り、わたしは浜辺の船へ帰って行ったのだが、両端反った船の側まで来た時、脂身(あぶらみ)を焼く香ばしい匂いが、わたしの身の周りにたち籠めてきた。思わずわたしは悲しみの声をあげ、神々に向っていうには、 『父神ゼウス、ならびに他の永遠にいます至福なる神々方よ、あなた方は無情にもわたしを眠らせ、破滅の淵へ陥れておしまいになった。船に残った部下たちは、なんとも大それたことを企てたものでした』。(12-366-373) (12-374)(12-375)(12-376)(12-377)(12-378)(12-379)(12-380) (12-381)(12-382)(12-383) たちまち裾(すそ)長き衣装を纏(まと)ったランペティエが、陽の神ヒュペリオンの許へ走り、われらの一党が、神の牛を屠ったことを告げた。心中(しんちゅう)怒りを発した神は、直ちに神々に向って仰せられるには、 『父神ゼウス、ならびに他の永遠にいます至福なる神々方よ、ラエルテスが一子(いっし)オデュッセウスの部下ども、不埒(ふらち)にもわたしの牛を殺したあの者どもを罰していただきたい。この牛どもは、わたしが星を鏤(ちりば)める天に昇る時も、天上から再び下界に向う時にも、常に心楽しく眺めていたものであった。 もし彼らが然るべき牛の代償を払わぬのならば、わたしは冥府へ降りて、亡者たちの間を照らすことにいたしますぞ』。(12-374-383) (12-384)(12-385)(12-386)(12-387)(12-388)(12-389)(12-390) するとそれに答えて、雲を集めるゼウスが仰せられるには、『陽の神よ、そなたには是非とも、不死なる神々と、穀物を恵む大地に住む人間どもの間に留まって、照り続けてもらわねばならぬ。かの者どもについては程なくわしが、葡萄酒色の大海の真只中で、白熱の雷火を放って粉々に砕いてやろう』。 これらのことをわたしは、髪美わしきカリュプソから聞いたのだが、彼女はそれを神々の使者、ヘルメスから聞いたということであった。(12-384-390) (12-391)(12-392)(12-393)(12-394)(12-395)(12-396) さてわたしは、海辺の船に帰り着くと、一人一人をつかまえて叱ってはみたものの、牛はすでに死んでいるのだから、よい算段が浮ぶ筈もない。それから間もなく神々は、部下たちに予兆を示されたのだ−−−剥(は)いだ皮が這(は)い出すし、串に刺した肉が、焼けたものであれ生(なま)のものであれ、一様(いちよう)に呻(うめ)き出して、牛の鳴き声そのままの声が響いてきた。(12-391-396) (12-397)(12-398)(12-399)(12-400)(12-401)(12-402) その後六日(むいか)にわたって、わたしの忠実な部下たちは、捕えてきた陽の神の牛の中でも、より抜きの牛の肉を食っていたが、クロノスの御子ゼウスが、七(なな)つ目の日をもたらされた時、荒れ狂っていた風も収まり、われらは直ぐさま乗船し、帆柱を張って広い海原へ乗り出した。(12-397-402) 第十二歌(P329) (12-403)(12-404)(12-405)(12-406)(12-407)(12-408)(12-409) (12-410)(12-411)(12-412)(12-413)(12-414)(12-415)(12-416 (12-417)(12-418)(12-419) この島を離れ、空と海のほかは陸のかけらも見えなくなった時、正(まさ)にこの時クロノスの御子は、うつろな船の上に黒雲を据え、海はその下に入って黒ずんできた。船はそれから長くは走り続けることができなかった−−−突如西風が激しい嵐を起し、唸(うな)りを立てて吹きつけてきたからで、帆柱の前部の綱は、二つとも突風に千切(ちぎ)られて、帆柱は後ろへ倒れ索具は悉(ことごと)く船底に崩れ落ちてゆく。 倒れた帆柱は船尾の舵取りの頭に落ち、その頭蓋骨を粉々に砕いてしまった。舵取りはさながら軽業師(かるわざし)の如く、もんどりうって甲板(かんぱん)から海中に落ち、勇魂は彼の骨を離れた。それと同時にゼウスは雷を鳴らし、船に雷火を浴びせられた。ゼウスの雷火に撃たれて船全体が震動し、船内は一面に硫黄(いおう)の臭気(しゅうき)が立ち籠めた。 部下たちは船から落ち、海がらすにも似て黒塗りの船の周りで波に漂っていたが、神は遂に彼らの帰国の望みを断ってしまわれた。(12-403-419) ---ここで、オデュッセウスは独りぽっちになってしまった。オデュッセウスがナウシカ姫の前に独りで現われた言い訳はここに完結した。 第十二歌(P330) (13)独りぽっちのオデュッセウスの彷徨 (12-420)(12-421)(12-422)(12-423)(12-424)(12-425) わたしは船内をあちこち歩き廻っていたが、やがて大波が襲って来て、側壁を竜骨からもぎとり、側壁を剥がれた竜骨を波がさらってゆく。帆柱も風に圧されて竜骨に叩きつけられた。幸い帆柱には、牛革で作った後部の帆綱が懸かっていたので、わたしはそれで竜骨と帆柱とを結び合せ、それにまたがって恐るべき風のまにまに流されて行った。(12-420-425) (12-426)(12-427)(12-428)(12-429)(12-430)(12-431)(12-432) (12-433)(12-434)(12-435)(12-436)(12-437)(12-438)(12-439) (12-440)(12-441)(12-442)(12-443)(12-444)(12-445)(12-446) この時西風は猛(たけ)り狂うのをやめたが、忽(たちま)ち今度は南風が、今一度、呪うべきカリュブディスへの道を辿(たど)れとばかり吹き寄せて、わたしの胸を悲しませた。一晩中(ひとばんじゅう)海上を漂い日の出とともに、スキュレの岩と怖るべきカリビュディスの淵に着いてしまった。 折しもカリュブディスは、塩辛い海水を呑み込んだところであったが、わたしは高い無花果(いちじく)の樹めがけて躍(おど)り上がり、蝙蝠(こうもり)の如くそれにしがみついていた。しっかりと踏んばる足場もないし、樹を攀(よ)じ登ることもできぬ。根は遥(はる)か下にあるし、長く太い枝も頭上に高く懸かって、カリュブディスに蔭を落としているのだ。 わたしは、カリュブディスが再び帆柱と竜骨を吐き出すまで、じっと耐えて樹にしがみついていた。それはあたかも、裁きを求める若者たちの、さまざまな争いごとを裁き終えた男が、集会の場を立って夕餉(ゆうげ)に向かう頃おい、そのくらいの時刻になって漸(ようや)く船材はカリュブディスの淵から姿を現した。 わたしは手足を離して上から空中を飛び、長い船材の傍らの、水中に音を立てて落下した。船材にまたがると、両手を櫂(かい)代わりにして必死に漕ぐ。人と神との父なる神は、幸いに再びスキュレがわたしの姿を見ることをお許しにならなかったが、さもなくばわたしは恐るべき破滅を免れることができなかったであろう。(12-426-446) 第十二歌(P331) (12-447)(12-448)(12-449)(12-450)(12-451)(12-452)(12-453) それから九日(ここのか)の間海上を漂い、十日目の夜になって神々は、わたしを髪美わしきカリュプソ、人語を語る怖るべき女神の住む、オギュギエの島へ漂着させて下さった。 女神は快くわたしを迎えて面倒を見てくれたが、これらのことはもはやお話しするまでもあるまい。このお屋敷で、あなたとやんごとなきお妃にお話ししたのは、つい昨日のことであった。すでに腹蔵なくお話したことを、繰り返し語るのも煩わしいことですから」。(12-447-453) ---オデュッセウスは、ここまで語って、カリュプソの話はすでに話したと言っている。それは第五歌までの話しであって、それらはアルキノオス王と妃アレテらに話したことであると言う。第五歌からこの第十二歌までは、すべてアルキノオスの館での話しであった。そこで、話の順序として、第十三歌に進む前に、第五歌に戻ってみよう。 |
| 次へ |
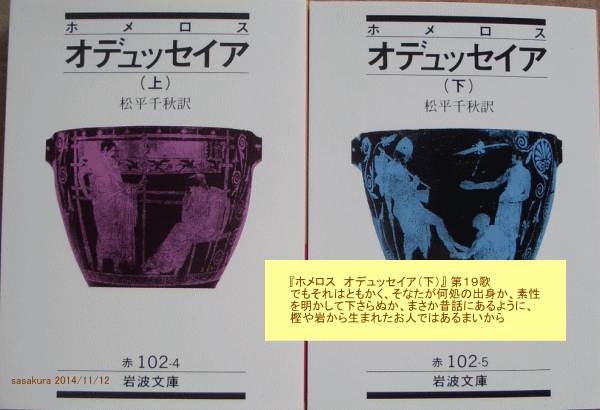 |
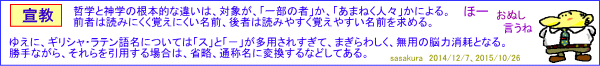 |
| 読後感想を述べたり、独自解釈のための引用にしては、常識を超えた量でになっているかも知れない。それは全文ではないし、翻訳者の注釈や付加資料は転載してはいないのだから、ぜひ本を手に入れて読んでいただきたい。あなたが若ければ若いほど、その知的資産は隠し味となって、あなたの人生に長く作用するだろう。この「オデッセイア」は、女性の視点で書かれていると信じるので、女性の方々の目に止まるようにと祈る。 |
 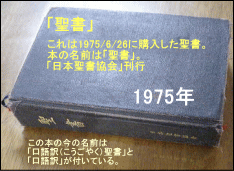 |
2015/4/8 オリジナル教会(初代代表) 笹倉正義
正式名称:(笹倉宗)聖母マリヤ福音教会