 |
| (8)冥府にて 第十一歌(P277) (11-1)(11-2)(11-3)(11-4)(11-5)(11-6)(11-7)(11-8)(11-9)(11-10)(11-11)(11-12) 「しかし、われらは海辺の船に戻ると、真先(まっさき)に船を浄(きよ)らかな海におろし、黒塗りの船に帆柱を立て帆を張った。ついで羊をつかまえて船に載せ、われらも大粒の涙をこぼし悲しみにくれながら乗船した。紺青の舳先(へさき)の船の背後からは、船にとってはこよなき道連(みちず)れ、帆をふくらます順風(じゅんぷう)を、人語を語る恐るべき女神、神美わしきキルケが送ってくれた。 船内の索具を悉(ことごと)く取り付けて腰をおろした後は、風と舵取りが進路を守って船を進める。わたつみを渡る船の帆は、ひもすがらピンと張り続けた。やがて陽は沈み、町の通りはすべて闇に閉ざされた。(11-1-12) (11-13)(11-14)(11-15)(11-16)(11-17)(11-18)(11-19)(11-20)(11-21)(11-22) 船はやがて、深く流れるオケアノス河の涯に着いた。ここではキンメリオイ族が国土と町を構え、霧と雲に包まれて住んでいる。輝く陽の神も、星をちりばめる天空に昇る時と、天空から再び地上に向かう時とを問わず、彼らには光明(こうみょう)の矢を注ぐことが絶えてなく、憐れな人間どもの頭上には、呪わしい闇が拡がっている。ここまで来て、船を陸に揚げると羊をおろし、われわれはオケアノスの流れに沿って歩き、やがてキルケの教えてくれた場所に着いた。(11-13-22) (11-23)(11-24)(11-25)(11-26)(11-27)(11-28)(11-29)(11-30)(11-31)(11-32) (11-33)(11-34)(11-35)(11-36)(11-37)(11-38)(11-39)(11-40)(11-41)(11-42) (11-43)(11-44)(11-45)(11-46)(11-47)(11-48)(11-49)(11-50) ここでペリメデスとエウリュロコスとが、犠牲獣をつかまえておさえると、わたしは腰の鋭い剣を抜き放ち、縦横それぞれ一腕尺(聖書の長さの単位:キュビト)の穴を掘り、その穴の縁(ふち)に立ってすべての亡者に供養(くよう)した。はじめは乳と蜜とを混ぜたもの、ついでは甘美の酒、三番目には水を注ぎ、その上に白い小麦粉を振りかけた。 それから活力なき亡者たちに向って懇(ねんご)ろに願(がん)をかけ、イタケに帰還した暁(あかつき)には屋敷の中で、仔を産まぬ牝牛の最良のもの一頭を供え、祭壇をくさぐさの見事な供物で満たし、テイレシアスのみには特に、全身漆黒(しっこく)の羊−−−わが家で飼う家畜の群の中でも、異彩を放つ一頭を供えると誓った。 さて亡者の群に祈って嘆願した後、羊を掴まえ穴に向けて頸(くび)を切ると、どす黒い血が流れ、世を去った亡者たちの霊が、闇の底からぞろぞろと集ってきた。若妻あり、まだ妻を娶(めと)らぬ若者あり、世の辛酸(しんさん)をつぶさに嘗(な)めた老人あり、また胸の悲しみもまだ生々しい、うら若い乙女たちの姿もある。 さらには青銅の槍の穂に撃たれて戦場に倒れ、いまも血塗(ちまみ)れの武器を身につけた多数の男たちなど、これら亡者の大群が、不気味な声をあげながら、穴の周(まわ)りをここかしこと飛び廻り、わたしは蒼白(あおじろ)い恐怖に襲われた。 そこでわたしは部下たちを促し、非情の刃に屠られて横たわっている羊の皮を剥(は)いで肉を焼き、神々−−−偉大なる冥王と恐るべきペルセポネイアに祈れと命じた。そう命じておいてわたしは、腰の鋭利の剣を抜き放って待ち構え、テイレシアスに訊き質(ただ)すまでは、活力なき亡者たちが、血に近付くのを許さなかった。(11-23-50) (P279) (11-51)(11-52)(11-53)(11-54)(11-55)(11-56)(11-57)(11-58) (P279)冥王の世界のリアリティ 最初に近付いてきたのは、部下エルペノルの亡霊であった。彼はまだ、道広き大地の下に埋葬されていなかったからであるが、それというのも、われらはほかの緊急な用事で心せくまま、彼の遺体に哀哭の礼も果さず、埋葬もせぬまま、キルケの屋敷に残してきたからであった。彼の姿を見てわたしは涙を催し、憐れみを禁じ得ず、翼ある言葉をかけていうには、『エルペノルよ、そなたはどのようにしてこの暗鬱な闇の世界へ降ってきたのだ。黒塗りの船で来たわたしより、徒歩(かち)のそなたの方が先に着いたとは』。(11-51-58) (11-59)(11-60)(11-61)(11-62)(11-63)(11-64)(11-65)(11-66)(11-67) (11-68)(11-69)(11-70)(11-71)(11-72)(11-73)(11-74)(11-75)(11-76) (11-77)(11-78) わたしがこういうと、彼は悲しみの声をあげて答えるには、『ゼウスの裔にしてラエルテスが一子、智謀に富めるオデュッセウスよ、わたしを破滅させたのは、神霊(ダイモン)の下された悪運と深酒でした。わたしはキルケの屋敷で寝ていた時、迂闊(うかつ)にも長い梯子(はしご)を伝って下へ降りることに気付かず、真逆様に屋根から落ちました。頸が付け根から折れ、魂が冥王の館へ降ってしまったのです。 ---深酒して屋根に上るなど変だし、くだらない話なのだが、これはくだらない人間でも死ねば冥王の館に来るという話に現実味を持たせるためのものであろう。 さて−−−これは、いずれも国許に残っておられ、ここにはおいでにならぬ方々ばかりですが−−−あなたの奥方(おくがた)、幼いあなたを育てられた御父上、またお屋敷に残しておいでの、たった一人の御子息テレマコスにかけてお願いしたいことがあります。あなたはこの冥王の館を去られた後、必ずやアイアイエの島に、堅牢な船をお着けになりましょう。 その折はその場で、王よ、是非ともわたしのことを思い出していただきたい。どうかそこをお発(た)ちになる時には、わたしに哀哭と埋葬の礼も施さぬまま、わたしに背を向け置き去りにするようなことはなさらぬように−−−わたしのために神々のお怒りを招かれるようなことがあってはなりませぬから。 それから、わたしの武具一切(いっさい)とともに、わたしの遺体を火葬に付し、灰色の海の渚(なぎさ)に、後の世の者たちがわたしのことを偲(しの)ぶよすがとして、この不運な男の塚を築いて下さい。これらの願いを果たして下さったならばさらに、わたしが生前(せいぜん)仲間に混じって漕(こ)いでいた櫂(かい)を、塚の上に立てて下さいますよう』。(11-59-78) (11-79)(11-80)(11-81)(11-82)(11-83)(11-84)(11-85) (11-86)(11-87)(11-88)(11-89)(11-90)(11-91)(11-92) (11-93)(11-94)(11-95)(11-96) こういう彼に、わたしが答えていうには、『不愍(ふびん)な男よ、そなたの願いはきっと、いう通りにしてやるぞ』。このようにわれら二人は、悲しい言葉を交わしていたのだが、わたしは(穴の)こちら側で血の上に剣をかざし、部下の亡霊は向こう側で、くどこどと言い続けていた。 ---生前つまらない者は、死んでからも、くだらないことを言うものだ・・・。 次に近付いてきたのは、世を去ったわたしの母の亡霊で、度量宏きアウトリュコスの娘アンティクレイアであった。わたしが聖都イリオス(トロイ国の首都イリオン)へ出征した折には、まだ存命の彼女を家に残し別れを告げたのであったが−−−母の姿を見て、わたしは憐れを催し落涙したが、深い悲しみに襲われながらも、テイレシアスに訊ねるまでは、母を先に血に近付かせることはしなかった。 そこへ現われたのが、テバイの人テイレシアスで、黄金(おうごん)の杖を握り、わたしと知ると語りかけていうには、『ゼウスの裔にしてラエルテスが一子、智謀に富めるオデュッセウスよ、そなたは不運なお人じゃ、どうしてまた、亡者どもやなんの喜びもないこんな場所を見ようとして、天日の光を後にしてやってこられたのか。血を飲んで誤りなき真実をお話しするから、どうか穴の傍らを離れ、鋭利の剣を引いて下さらぬか』。(11-79-96) (P281) (11-97)(11-98)(11-99)(11-100)(11-101)(11-102)(11-103)(11-104) (11-105)(11-106)(11-107)(11-108)(11-109)(11-110)(11-111) (11-112)(11-113)(11-114)(11-151)(11-116)(11-117)(11-118) (11-119)(11-120)(11-121)(11-122)(11-123)(11-124)(11-125) (11-126)(11-127)(11-128)(11-129)(11-130)(11-131)(11-132) (11-133)(11-134)(11-135)(11-136)(11-137) こういうので、わたしは穴から退き、銀鋲(びょう)打った太刀(たち)を鞘(さや)に納めた。テイレシアスは黒い血を啜(すす)るとようやく、この世に類(たぐ)いなき予言者が、わたしに語りかけていうには、『英明高きオデュッセウスよ、そなたは心楽しき帰国を求めているのであろうが、その帰国はさる神が、苦難の旅になされるであろう。 そなたが大地を揺(ゆす)る神の目を逃れることは、到底できぬと思うからだが、この神は己れの倅(せがれ)をそなたによって盲(メシ)いにされたのを憤(いきどお)り、心中(しんちゅう)深く怨(うら)んでおられるからだ。しかし、そうはいうものの、途中苦しい目に遭いつつも、なお帰国の望みはある−−− そなたが自分と部下たちの気持を制御できればのことだが。それはそなたが菫(すみれ)色の大海を後にして、堅牢の船をトリナキエの島に近付け、そこで、いかなるものも見逃さず、いかなることも聞き逃さぬ、陽の神エエリオスの飼う牛と、肥えた羊の草食(は)む姿を見る時のことじゃ。 その時、もしそなたが家畜の群に危害を加えず、ひたすら心を帰国に向けているならば、そなたらの一行は、よしんば途中数々の苦難に遭おうとも、なおイタケへ帰ることができるかも知れぬ。しかし、もし危害を加えようものなら、その時は船も部下も失われるとわしは推量する。そなた自身は難を免(まぬか)れても、帰国は遅れ部下の全員を失い、他国の者の船に乗って、惨(みじ)めな帰国を果すことになるであろう。 また、屋敷へ帰っても、さまざまな災厄(さいやく)に遭うであろう−−−不逞(ふてい)の輩(やから)が、その美貌(びぼう)女神とも見紛(みまが)うそなたの妻に、妻問いの品々を差し出しては言い寄り、家の貯(たくわ)えを食い潰している有様(ありさま)を目にすることになる。 そなたが帰国すれば、この者たちの乱暴狼藉(ろうぜき)を懲(こ)らしめることは必ずできようが、しかし屋敷の内で求婚者どもを、策略を用いるなり、堂々と鋭利の剣を揮(ふる)うなりして討ち取った後は、手頃の櫂(かい)を手に持って、海を知らず、塩を混ぜた食物を食うこともせぬ人間たちの住む国に達するまで、旅を続けねばならぬぞ。 この国の者たちは、船首の頬(ほお)を紅(くれない)に染めなした船も、船には翼の用をなす、手に合う櫂も知らぬ。ここで、明らかにそれと判る、しるべとなることをそなたに話して進ぜよう−−− 明らかなしるべであるから、よもや気付かぬことはあるまい−−−すなわち、道行く途中で出会った男が、そなたの逞(たくま)しい肩にかつぐものを、「殻竿(からざお)」であろうと申したならば、その時こそ櫂を大地に突き刺し、御神ポセイダオンに盛大な生贄(いけにえ)を−−−牡羊(おひつじ)に牡牛(おうし)、それに牝豚(めすぶた)とつるむ牡豚を、それぞれ捧げ、それから国許へ帰って、広大な天空をしろしめす不死なる神々のすべてに、一柱ずつ順々に、贄(にえ)を献じなされ。 そなたの最後はどうかといえば、それは海からは離れたところで訪れる−−−それも頗(すこぶ)る安らかな死で、恵まれた老年を送りつつ、老衰して果てることになる。そしてそなたを囲む民もまた栄えるであろう。以上がそなたにわたしが語る真実なのじゃ』。(11-97-137) (11-138)(11-139)(11-140)(11-141)(11-142)(11-141)(11-142) (11-143)(11-144)(11-145)(11-146)(11-147)(11-148)(11-149) この言葉にわたしが答えていうには、『テイレシアスよ、それらのことは、神々が御自身のお計(はか)らいで定められたことであろうが、どうかこれからお訊ねすることに答え、ありのままを教えていただきたい。あそこに世を去ったわたしの母の亡霊が見えるのだが、黙って血の傍(かたわ)らに坐ったままで、わが子の顔をまともに見ようとも、話しかけようともして下さらぬ。 老師よ、どうしたら母に、息子のわたしをそれと知ってもらえるのであろうか』。こういうと、彼は即座に答えて、『それをそなたに言いきかすことは、いともたやすいことじゃ。そなたが血に近付くことを許せば、どの亡者も真実を話すのだが、それを拒めば、拒まれた亡者は引き退(さが)ってしまうのだ』。(11-138-149) (11-150)(11-151)(11-152)(11-153)(11-154)(11-155)(11-156) (11-157)(11-158)(11-159)(11-160)(11-161)(11-162) こういって予言を告げ終えると、老師テイレシアスの霊は、冥王の館の中へ入ってしまった。しかしわたしは、その場を去らずに留まり、母が近付いて黒い血を飲むまで、待っていたのだが、果たして母は直ぐさまわたしをそれと知り、おろおろと泣きながら、翼ある言葉をかけていうには、 『倅(せがれ)よ、まだこの世に生(せい)を享(う)けている身でありながら、どのようにしてこの暗鬱(あんうつ)な闇(やみ)の世界に降りてきたのです。この場所は生きている人間には容易に見ることのできぬところ、ここへ来るまでには、数々の大河(たいが)、恐るべき流れを幾つも越えねばならぬ。 なにより先ずオケアノスの流れがあるが、堅牢な船を持たぬ限り、徒歩では到底渡ることができぬ。ところでそなたは今、トロイから帰国の途次、部下たちと共に長の年月、海上を漂泊しつつここまで来たのですか、いまだイタケには帰らず、屋敷へ帰って妻の顔を見ておらぬのですか』。(11-150-162) (11-163)(11-164)(11-165)(11-166)(11-167)(11-168)(11-169) (11-170)(11-171)(11-172)(11-173)(11-174)(11-175)(11-176) (11-177)(11-178)(11-179) こういう母に、わたしが答えていうには、『母上、わたしはテバイの人、テイレシアスの予言を訊くために、どうしても冥王の館へ降りてこねばならなかったのです。わたしはまだアカイアの地に近付いたこともなく、わが故国の土を踏んでもおらぬのです。はじめ勇武のアガメムノンに随(したが)って、トロイ勢と戦うべく、駿馬に名高きイリオスに出征してこの方、今日までずっと苦難を嘗(な)めつつ漂泊を続けております。 しかしそれはさておき、これからお訊ねすることに答え、包まずお話し下さい。母上を襲った、悲しみ尽きぬ死の運命はどのようなものであったのですか。長患(ながわずら)いの果てでしたのか、それとも雨の如く矢を注ぐアルテミスが、苦しみを与えぬ矢でお命を奪ったのでしょうか。また父上や、家に残してきた倅(せがれ)のこともお話しください。 わたしの王権はまだ二人の手にありますのか、それとも、わたしはもはや帰らぬと皆が思い、誰か他の者の手に移っておりますのか。また、妻が何を思い何を望んでいるかもお話し願いたい。妻は倅の許(もと)に留まり、世帯(せたい)の一切をしっかりと守っておりましょうか。それとも誰ぞアカイアの名立たる男が、すでに彼女を娶っておりますのか』。(11-163-179) (上P285) (11-180)(11-181)(11-182)(11-183)(11-184)(11-185)(11-186) (11-187)(11-188)(11-189)(11-190)(11-191)(11-192)(11-193) (11-194)(11-195)(11-196)(11-197)(11-198)(11-199)(11-200) (11-201)(11-202)(11-203) こうわたしがいうと、高貴の母は直ぐに答えて、『もとよりそなたの妻は、堅忍の心を胸にそなたの屋敷に留まっています。あの人にとっては、夜も昼も涙の内に過ぎてゆく、辛(つら)い日々が続いているのだが。 そなたの大切な王権は、まだ他人の手に移ってはおらぬ、テレマコスは王領地を、平穏(へいおん)無事(ぶじ)に管理しており、法を司(つかさど)る人間に相応(ふさわ)しく、人々が等しく楽しむ公(おおやけ)の宴会にも顔を出している、誰もが皆招(よ)んでくれるからです。 そなたの父は田舎(いなか)に引き籠ったまま、町へはお出掛けにならぬ。父上はまた、寝台、敷布(しきふ)、豪奢(ごうしゃ)な毛布などの寝具は用いられず、冬は屋敷の召使いどもと同じように、暖炉の傍らの埃(ほこり)まみれの場所でおやすみになり、身につけておいでの衣服も粗末なものです。 しかし夏が来、穣(みの)りの秋が訪れると、葡萄畑の斜面のどこにでも、地面に落葉を敷いて、父上の寝床ができる。父上は悲歎にくれつつ、そのような所におやすみになり、そなたの帰国を待ち侘(わ)びながら、心の中に悲しみを育てておられるのだが、その上さらに、老いの苦しみが父上の身に迫っているのです。それはわたしも同じことで、わたしが世を去った理由もそうだったのです。雨の如く矢を注ぐ眼光鋭き女神が、屋敷の内にわたしを訪れ、苦しみのない矢で命を奪われたのでもなく、あるいはまた、しばしば苦しい衰弱の果てに、肢体から命を奪う患いに襲われたわけでもない。わたしの甘美の命を奪ったのはほかでもない、名も高きオデュッセウスよ、そなたの明知、そなたの孝心を偲(しの)びつつ、帰って来ぬそなたを待ち侘びる辛い気持だったのだよ』。(11-180-203) (11-204)(11-205)(11-206)(11-207)(11-208)(11-209)(11-210) (11-211)(11-212)(11-213)(11-214) 母のこの言葉に、わたしは心の内で、世を去った母の霊をこの腕に抱きたいと思い、抱こうと心が逸(はや)るままに、三たび母に駆け寄ったが、三たびとも母は影か夢にも似て、わたしの手をふわりと抜けてしまう。 そのたびにわたしの胸は、ますます痛みを増すばかり、翼ある言葉をかけて母にいうよう、『母上、冥土にあっても、せめて互いに抱き合い、胸を凍らす嘆きに浸(ひた)って気持を晴らしたいと、抱こうとするこの手を、どうしてお逃(のが)れになるのです。それとも今見るお姿は、わたしをさらに悲しませ歎(なげ)かせるために、尊(とうと)いペルセポネイアがお遣わしになった幻なのでしょうか』。(11-204-214) (上P287) (11-215)(11-216)(11-217)(11-218)(11-219)(11-220)(11-221) (11-222)(11-223)(11-224) こうわたしがいうと、高貴の母は直ぐに答えて、『倅よ、そなたはこの世の誰よりも不運な男じゃ。ゼウスの御息女、ペルセポネイアが、そなたを欺(あざむ)いておられるわけではない。人間は一(ひと)たび死ねば、こうなるのが定法(じょうほう)なのです。 もはや肉と骨とを繋ぎとめる筋もなく、命の力が白い骨を離れるやいなや、これらのものは燃えさかる火に焼き尽され、魂は夢の如く飛び去って、ひらひらと虚空(こくう)を舞うばかり。さあ、そなたは急いで一刻(いっこく)も早く光ある世界へお帰り、そして後になってそなたの妻に語り聞かせることのできるよう、ここの一切を見知っておきなさい。(11-215-224) (11-225)(11-226)(11-227)(11-228)(11-229)(11-230)(11-231) (11-232)(11-233)(11-234) われら二人(ふたり)がこのように言葉を交わしている間に、高貴のペルセポネイアに促されて、女たちがぞろぞろと現われてきた。いずれも名立(なだ)たる将領の妻や娘たちであったが、黒い血の周りに集まってくる。 わたしはそのひとりひとりに、どのように訊ねたものかと思案したが、心中思いめぐらして、次のようにするのが一番良かろうと考えた。すなわち、逞(たくま)しい腰のわきから、刃の永い剣を抜き放ち、皆が一時に血を飲むことを許さなかった。そこで女達は順々に進んできて、それぞれ己(おのれ)の素姓(すじょう)を明かし、こうして皆の女に訊ねることができた。(11-225-234) (上P288) (11-235)(11-236)(11-237)(11-238)(11-239)(11-240)(11-241) (11-242)(11-243)(11-244)(11-245)(11-246)(11-247)(11-248) (11-249)(11-250)(11-251)(11-252) ここでわたしが最初に会ったのは、高貴な生れのテュロであったが、その語るところによれば、彼女は優れたサルモネウスの娘で、アイオロスの息子クレテウスの妻であったという。かつて女は河(神)に恋をした−−− その河とは、地上を流れる河々の中でも特に美しい聖なる河エニペウスで、さればこそテュロは、エニペウスの美しい流れのほとりに、いつも足を運んでいたのだが、大地を抱き大地を揺(ユス)る神が、河神の姿をかりて現われ、渦を巻く河の河口の辺(あた)りで女と供寝した。 この時、紫色の山ほどもある大波が弓なりに巻き上がって辺りを閉ざし、神と人の子の女との姿を隠した。神は処女の帯を解き、その瞼(まぶた)に眠りを注がれたが、やがて愛の営みを終えるや、娘の手をとって優しく語りかけ、 『女よ、この愛の契(ちぎ)りを喜ぶがよい、一年の過ぎゆくうちに、そなたは優れた子らを産むであろう。神々の閨(ねや)の契りが実を結ばぬことは決してないのだ。そなたはその子らを慈(いつく)しみ育てるのだぞ。さあ家へ帰り、口を慎んで決してわたしの名を明かすでないぞ。よいか、われこそは大地を震わすポセイダオンである』。(11-235-252) (11-253)(11-254)(11-255)(11-256)(11-257)(11-258)(11-259) (11-260)(11-261)(11-262)(11-263)(11-264)(11-265) (1)テュロ こういうと、神は波打つ海の底へ姿を消された。テュロは身籠ってペリエス(ペリアス)とネレウスとを産み、この二人はともに、大神ゼウスの力強い従者となった。ペリエスは多数の家畜を所有して広大なイアオルコス(イロルコス)に、ネレウスは砂浜の国ピュロスに住んだ。女らのうちにも特に秀でた王妃テュロは、クレテウスとの間にも、アイソン、ペレス、戦車を駆って戦うアミュタオンを儲けた。 (2)アンティオペ テュロに次いで会ったのは、アソポス(河)の娘アンティオペで、これはなんと、ゼウスの腕に抱かれて眠ったと誇る女性であったが、アンピオン、ゼトスの二子(にし)を産んだ。二人は七つの門のテベ(テバイ)の町を初めて築き、これに城壁を繞(めぐ)らせた。−−−勇猛の二人ではあったが、広大なテベに、城壁なしでは住むことができなかったのだ。(11-253-265) (11-266)(11-267)(11-268)(11-269)(11-270)(11-271)(11-272)(11-273) (11-274)(11-275)(11-276)(11-277)(11-278)(11-279)(11-280) (3)アルクメネ(ヘラクレスの母) アンティオペの次にわたしが会ったのは、アンピトリュオンの妻アルクメネ、大神ゼウスの腕に抱かれて交わり、勇猛無比、獅子の心を持つヘラクレスを産んだ女性であった。 (4)メガラ(ヘラクレスの妻) また剛毅(ごうき)のクレイオン(クレオン)の娘で、その力、衰えることを知らぬ、アンピュトリュオンの息子(ヘラクレス)が妻としたメガレ(メガラ)にも会った。 (5)エピカステ(息子の妻) わたしはまた、オイディポデス(オイディプス)の母、それと知らずして己(おの)れの息子の妻となり、おそるべき大罪を犯した美貌のエピカステにも会った。息子は父を殺した後、母を娶ったのであったが、神々はたちまちそれを広く世に知らしめられた。オイディポデスは、呪わしき神意によって苦しみを味わいつつ、麗わしいテベの町でカドモスの民を治め続け、母は苦悩のあまり、高い梁(はり)に綱を結んでだらりと垂らし、冥府の門を衛る恐るべき冥王の館へ降ったが、息子に残していったのは、やがて母の怨霊(エリニユエス)が果すべき、あらゆる禍難の苦しみであった。(11-266-280) (11-281)(11-282)(11-283)(11-284)(11-285)(11-286)(11-287)(11-288) (11-289)(11-290)(11-291)(11-292)(11-293)(11-294)(11-295)(11-296)(11-297) (6)クロリス(ネレウスの妃) また絶世の美女、クロリスにも会った−−− かつてネレウスがその美貌に魅せられ、莫大な結納(ゆいのう)を与えて娶った女性であったが、彼女はその昔ミニュアス族の住むオルコメノスの王として勢威をふるった、イアソスが一子アンピオンのお末娘であった。王妃としてピュロスに君臨し、ネストル、クロミオス、高貴のペリクリュメノスら、優れた子を産んだ。 この子らに加えて、さらに気品高きペロを産んだ−−−人みなの讃歎おかぬ美貌の女性で、近隣の住人はこぞって妻にと望んだがネレウスは、角曲り額(ひたい)広き牛の群−−−容易には扱い難いその牛の群を、剛勇無双のイピクロスから奪い、ピュラケより曳いてくる者のほかには与えぬ、といった。 この時、他に比類なき占いの名手が、牛を奪って曳きつれてこようと請け合ったが、神の下された苛烈な運命に阻(はば)まれた。すなわち野に住む牛飼たちの手に落ち、酷(キビ)しい鎖につながれてしまったのだが、一年(ひととせ)の巡るにつれて、月は移り日々が過ぎ、次々に季節も帰りくると、豪力無双のイピクロスは、占い者が託宣の悉(ことごと)くを明かしたのに免じて彼を解き放ち、かくしてゼウスの神慮は果されたのであった。(11-281-297) (11-298)(11-299)(11-300)(11-301)(11-302)(11-303)(11-304)(11-305) (11-306)(11-307)(11-308)(11-309)(11-310)(11-311)(11-312)(11-313) (11-314)(11-315)(11-316)(11-317)(11-318)(11-319)(11-320) (7)レダ(テュンダレオスの妃) また、テュンダレオスの妃、レデ(レダ)にも会った。彼女はテュンダレオスとの間に、豪胆な二人の息子、馬を馴らすカストルと、拳闘の名手ポリュデウケスとを儲けたが、ものみなに命を授ける大地が、生きながら二人を蔽(おお)っている。二人は地下にありながら、ゼウスから特権を与えられ、一日ごとに交る替る生きては死ぬことを繰り返す。二人は神々と同じ特権に与(あず)っているのだ。 (8)イピメディア ついでアロエウスの妻、イピメディアの姿を見た。その語るところを聞けば、ポセイダオンと交わったということで、神にも見紛(みまが)うオトスと、勇名轟くエピアルテスとを産んだ。二人は短命ではあったが、名も高きオリオンに次いでは、穀物を恵む大地が育てた、最も巨大で最も美貌の子らであった。九歳にして身幅は九腕尺(キュビト:約4.2メートル)、背丈(せたけ)は九尋(ひろ)(約一六メートル)もあった。 彼らはこともあろうに、オリンポスなる神々に対し、狂暴な戦いの騒乱を起すぞと脅した。天空に登る道を作るため、オリンポスのの上にオッサ(山の名前)を、オッサの上に樹葉揺れるペリオン(山の名前)を重ねんとした。もしも彼らがすでに青春の齢(よわい)に達していたならば、それを仕遂げたでもあろうが、髪美わしきレトが産みたもうたゼウスの御子(アポロン)は、彼らのこめかみの下に柔毛が生え出て、その顎(あご)の辺りを勢いよく伸びた鬚(ひげ)で蔽(おお)う前に、討ち取ってしまわれた。(11-298-320) (11-321)(11-322)(11-323)(11-324)(11-325)(11-326)(11-327) (11-328)(11-329)(11-330)(11-331)(11-332) わたしはまた、(9)パイドレ(パイドラ)に(10)プロクリス、さらに麗わしき(11)アリアドネにも会ったが−−−アリアドネは残忍なミノスの娘、かつてテセウスは、クレテから聖都アテナイの丘へ連れ帰ろうとしたが、女と楽しく暮らす願いは終(つい)に果すことができなかった−−−それより先にアルテミスが、ディオニュソスの証言に従い、四方を海に囲まれたディエ(ディア)の島で、彼女の命を奪ったからであった。 (12)マイラに(13)クリュメネ、また高価なる黄金のために夫を売った、忌(い)むべき(14)エリピュレにも会った。 しかし今ここで、わたしの会った英雄たちの妻や娘の悉(ことごと)くについてお話しし、その名をあげることはできそうにない。話し終(おえ)る前に、神聖な夜は明けてしまうであろうから。今はもう、船の仲間の許へ帰ってか、あるいはここで眠る時刻となった。帰国させていただく件は、神々とあなた方にお任せしよう」。(11-321-332) (小休止)読者にアルキノオスの館でオデュッセウスが話しているのだということを思い出させる。 (11-333)(11-334)(11-335)(11-336)(11-337)(11-338)(11-339) (11-340)(11-341)(11-342)(11-343)(11-344)(11-345)(11-346) こういうと、小暗い広間の一座は、物語に魅せられた如く、静まり返って言葉を発する者もない。ようやくにして白き腕(かいな)のアレテが、口を切り一同に向っていうには、「パイエケス人たちよ、このお人の容姿、またその内なる均斉とれた分別を目の当たりにして、そなたらはこのお人をどのようにお見受けなされるか。この方はわたしには大切なお客であるが、そなたらもまたみな、その接待(せったい)役たる栄には与(あずか)る者たちじゃ。されば匆々(そうそう)にお帰しするようなことがあってはならぬし、このように難儀しておいでのお人に引出物を惜しんではなりませぬぞ。 そなたらの屋敷には、神々のお恵みによって、莫大な財宝の貯(たくわ)えがあるものだものな」。すると一座の中の長老である、老雄エケネオスが、一同に向っていうには、「皆の衆、賢明なお妃の仰せられたことは誠に適切であり、われらの思いにも適(かな)うことじゃ。されば方々(かたがた)はお妃の仰せに従うがよかろうが、これからどういい、どうするかは、アルキノオス王の御一存にかかっておる」。(11-333-346) (11-347)(11-348)(11-349)(11-350)(11-351)(11-352)(11-353) (11-354)(11-355)(11-356)(11-357)(11-358)(11-359)(11-360)(11-361) それにアルキノオス王が答えていうには、「わしが世に在って、櫂(かい)愛(め)でるパイエケス人の王たる限りは、きっと妃の申す通りにしよう。客人にはさぞや帰国を急(せ)いておられるではあろうが、まあ御辛抱願って明日までお待ちいただきたい。 それまでにわしが引出物一切を取り揃(そろ)えよう。国許(くにもと)へお送りする件については、皆の者が心掛けねばならぬが、とりわけてこのわしは、国の主権を握る者である以上、特に配慮するつもりだ」。 そういうアルキノオスに、智略に富むオデュッセウスが答えていうには、「万民に優れて名も高きアルキノオス王よ、もしあなた方がわたしに、もう一年ここに留(とど)まれ、さすれば帰国の面倒も見、立派な土産(みやげ)もやろうと仰せられたら、それはむしろわたしには好ましいことであり、また財宝を手に一杯抱えて帰国する方が、どれほど得(とく)か判(わか)りません。 またその方が、イタケに帰還したわたしに会う者たちも、わたしを重んじ歓迎もしてくれましょうからな」。(11-347-361) (上P294)ほら話 (11-362)(11-363)(11-364)(11-365)(11-366)(11-367)(11-368) (11-369)(11-370)(11-371)(11-372)(11-373)(11-374)(11-375)(11-376) するとアルキノオスは彼に答えていうには、「オデュッセウスよ、黒き大地は、出所を確かめる術(すべ)もない偽りの物語を捏(こ)ね上げる輩(やから)を、多数育てて四方(よも)に撒(ま)き散らしているが、あなたの様子からは、法螺(ほら)を吹いたり人を欺(あざむ)くようなお人とは見受けられぬ。 あなたの語り口はまことに見事であるし、内には優れた才覚(さいかく)を具(そな)えておられる。さながら楽人の語る如く、アルゴス軍の総勢、ならびにそなた自身の痛ましい苦難の数々を見事に方って下さった。 そこで、あなたとイリオス攻めの征旅を共にしてその地で果てた、神にも紛(まが)う戦友たちの幾人かにも会われたのかどうか、包まずありのままに話して下さらぬか。この頃(ごろ)の夜は長く際限(さいげん)もないし、まだ屋敷の中で眠る時刻でもない。是非とも驚くべきことごとを話していただきたい。 あなたが今この屋敷で、あなたの蒙(こうむ)った悲運の数々を敢えて語って下さるのならば、わしは美(うる)わしき曙(あけぼの)が訪れるまででも、辛抱して聴こう」。(11-362-376) ---福音書の真偽 福音書とは、イエスがキリストであることを証する「喜ばしい文書」である。その文書に、イエスの両親がユダヤ社会全体がエホバの神と共に歩んでいたこと、マリヤによってイエスが誕生した次第と、それを確証する事件らがつながっていなければならない。洗礼者ヨハネが重要なのは、彼が老女から生まれたのであり、その事件は村人たちの記憶に残るものであり、かつその老女エリザベツはマリヤの親戚であり、アロン家の娘の一人であったのである。 そのことから、マリヤの家系がレビ人である可能性が大である。イエスの十字架事件の直後、彼の死を遡って、彼の持っていた言葉の権威、さらには彼の誕生について、それらの全てを知りたいと思ったのは、誰あろう、ローマ軍の百卒長テオピロだったのである。 彼すなわち主人の意を呈して、マリヤから聞き書きし、ユダの山里に赴いて30年前の事件、「老女の初産」を確かめたのは、その百卒長の信頼篤いしもべ「ルカ」であった。マリヤがルカに語ったことは、イエスの弟子たちをはじめ、ユダヤ人には絶対に話せないことが含まれていた。それは聖霊によるマリヤの処女受胎である。ユダヤ人はイエスをヨセフの子と信じていたからであり、外面的なものしか見ない彼らにとって、処女受胎は姦淫の証にほかならないからである。霊的には彼らは盲目である。イエスに癒されたルカと、それを頼んだテオピロは、霊的な信仰に最初に足を踏み入れたイエスの「友」なのである。 (11-377)(11-378)(11-379)(11-380)(11-381)(11-382)(11-383)(11-384) 智謀に富めるオデュッセウスが、それに答えていうには、「万民に優れて名も高きアルキノオス王よ、長話にも時期があるが如く、眠りにも時期があるとはいうものの、あなたが是非ともさらに話を聞きたいとお望みならば、今お話ししたよりもさらに悲しむべき物語の数々を語ることを拒(こば)むものではありません−−− それはすなわち、戦い終った後に果てた戦友たちの苦難ですが、彼らはトロイ勢の恐るべき叫喚(きょうかん)の修羅場(しゅらば)は逃(のが)れたものの、凱旋(がいせん)の折(おり)、不貞(ふてい)の女の奸計に斃れた者たちでありました−−−(11-377-384) 第十一歌(P295)冥府の続きを語る (六)アガメムノンと郎党たちの霊 (11-385)(11-386)(11-387)(11-388)(11-389)(11-390)(11-391) (11-392)(11-393)(11-394)(11-395)(11-396)(11-397)(11-398) (11-399)(11-400)(11-401)(11-402)(11-403) さて、聖なるペルポセネイアが、女たちの亡霊をかなたこなたへ追い散らしてしまわれた時、アトレウスが一子、アガメムノンの亡霊が悲しみに打ち沈んで現われ、アイギストスの屋敷で、彼とともに討たれて死んだ他の亡霊たちも、その周りに群がっていた。 黒い血を飲むや忽(たちま)ちわたしをそれと知った彼は、大粒の涙をこぼしながら、必死にわたしに届こうと、こちらへ手を差し伸べつつ、声をあげて泣いていたが、かつてはそのしなやかな四肢に宿っていた力も勢いも、もはや彼には残されていなかった。その姿を見てわたしも泣き、憐れみを禁じ得ず、彼に翼ある言葉をかけてこう言った。 『誉れも高きアトレウスの子、万民に王たるアガメムノンよ、どのような悲しむべき死の運命が、あなたを亡ぼしたのだ。海を渡るあなたをポセイダオンが、凄まじく吹き荒(すさ)ぶ嵐を起して打ち拉(ひし)いだのか、あるいはまた陸上で、牛や見事な羊の群をさらわんとした際とか、または城を陥して女どもを奪わんとして戦ううちに、敵の手にかかって果てたのか』。(11-385-403) (11-404)(11-405)(11-406)(11-407)(11-408)(11-409)(11-410) (11-411)(11-412)(11-413)(11-414)(11-415)(11-416)(11-417) (11-418)(11-419)(11-420)(11-421)(11-422)(11-423)(11-424) (11-425)(11-426)(11-427)(11-428)(11-429)(11-430)(11-431) (11-432)(11-433)(11-434) わたしがこういうと、彼は直ちに言葉を返していうには、『ゼウスの裔にしてラエステルが一子、知略縦横(じゅうおう)のオデュッセウスよ、海を渡るわたしをポセイダオンが、凄まじく吹き荒(すさ)ぶ嵐を起して亡ぼされたのでもないし、陸上において、牛や見事な羊の群をさらわんとして、敵の手にかかって果てたのでもない。 アイギストスめが不埒(ふらち)なわしの妻と組んでわしの暗殺を謀(はか)り、家へ招いて食事を供(きょう)した後、さながら飼葉桶(かいば・おけ)の傍(かたわ)らで牛を屠(ほふ)るが如く、わしを殺したのだ。かくの如く、わしは世にも惨めな最後を遂げたのだが、わしの周りではわしの他に部下たちも、次々に殺されていった−−− さながら権勢を誇る富豪の屋敷で、婚礼の祝いとか持ち寄りの会食、あるいは豪奢(ごうしゃ)な宴会の折に屠られる白き牙の猪の如くにな。おぬしはこれまでたびたび、人の殺される場に居合わせたことがあろう−−− 一騎討ちで討たれる者、乱戦の中に斃(たお)れる者など、しかしあの時の有様を目にしたならば、必ずやかつて覚えたことのないほどの憐れみを催したであろう−−− 広間の中で混酒器と料理を盛った食卓のまわりに、われらは倒れ伏して床一面は血の海であった。この時わしは世にも痛ましい声を聞いた−−− 奸智(かんち)のクリュタイムネストレめがわしの傍らで殺した、プリアモスの娘カサンドレ(カサンドラ)の声をだ。わたしは剣(つるぎ)で身を貫かれ、瀕死(ひんし)の身であったが、両手を持ち上げて大地を打とうとした。だが恥知らずの売女(ばいた)めはわしに背を向けて、冥府(めいふ)に旅立つわしの瞼(まぶた)を閉じようとも、口を塞ごうともしてくれなかった。 されば、かかる行為を思い付くような女よりも、恐るべくまた破廉恥なものは他にはない。現にあの女も、連れ添う夫の殺害を謀るという、誠に怪しからぬ行為を企んだではないか。わしは子らや家僕(かぼく)らに喜び迎えられて帰国できるとばかり思っていたが、あの、世にも邪悪な心根(こころね)の女は、己(おのれ)のみならず、後の世のすべての女たちに−−−操(みさお)正しい女に対してまでも、汚辱を振りかけたのだ』。(11-404-434) (上P297) (11-435)(11-436)(11-437)(11-438)(11-439)(11-440)(11-441) (11-442)(11-443)(11-444)(11-445)(11-446)(11-447)(11-448) (11-449)(11-450)(11-451)(11-452)(11-453)(11-454)(11-455) (11-456)(11-457)(11-458)(11-459)(11-460)(11-461) こういう彼にわたしは答えて、『なんとも恐ろしいことじゃ。いかにも、遥かに見晴かすゼウスは昔から、アトレウス一族をいたく憎まれ、その憎しみを女の企みを用いて晴らそうとなされたのだ。ヘレネのゆえにわれらの戦友の多くが命を落し、あなたには、その不在の間にクリュタイムネストレが奸計をめぐらしたのであった』。 わたしがこういうと、彼は直ぐに答えて、『さればおぬしも、妻といえどもうっかり気を許してはならぬぞ。おぬしがよく承知しておることでも、すべてを打ち明けてはならぬ。一部は話してもよいが、一部は隠しておくことじゃ。 だがオデュッセウスよ、おぬしは妻の手にかかって殺害されるようなことはあるまい。イカリオスの娘、聡明なペネロペイアは、まことに思慮深くよい分別をお持ちだからな。われら出征の折(おり)、別れを告げた時の彼女は、まだ初々(ういうい)しい若嫁で、幼な子がその乳房に縋(すが)っていたが、いとけない赤子であったその御子も、今はもう一人前(いちにんまえ)の男の仲間に入っておられるであろう、仕合せな御子じゃ、やがてえ父親は帰って来てわが子と再会し、子は親を迎える子としては当然のように、父を抱いてその帰国を喜ぶであろう。 だがわしの妻は、わしが倅(せがれ)の姿を心ゆくばかり眺めることも許さなかった。その前に当のわしを殺したのだからな。もう一つおぬしにいっておくことがある、心に留めておくがよい。おぬしが国許へ帰る時には、密かに船を着け、決して人目に立ってはならぬ、女どもにはもはや信は置けぬのだ。 ところで、これから訊ねることに答え、ありのままに話してもらいたい。おぬしらは、わしの倅がまだどこかで生きているという噂を聞いたであろうか。それはオルコメノスか砂浜のピュロス、あるいはまた広大なスパルテなるメネラオスの許かも知れぬが。いずれにせよ、わしの大切なオレステスは、地上でいまだ死んではおらぬはずだからな』。(11-435-461) (11-462)(11-463)(11-464)(11-465)(11-466)(11-467)(11-468) (11-469)(11-470)(11-471)(11-472)(11-473)(11-474)(11-475)(11-476) そういう彼に答えてわたしがいうには、『アトレウスの子よ、どうしてそのようなことをわたしに訊ねるのだ。オレステスの生死については、わたしは何も知らぬ。とりとめのない風説をあなたに語るのは宜しくないしな』。 このようにわれら二人は、悲歎にくれて大粒の涙を流しながら、悲しい言葉を交わしつつ相対していたが、とかくするうちにペレウスの子、アキレスの霊が現われ、彼とともにパトロクレス(パトロクロス)、非の打ちどころなきアンティロコス、さらには、無双の勇士アキレスに次いでは、その容姿体躯ともにダナオイ勢の間に双(なら)びなきアイアスの霊も近付いてきた。 第十一歌(P299)冥府にて (七)アキレスの霊 アイアコスの裔(すえ)なる駿足の勇士(アキレス)の霊は、泣きながら翼ある言葉をわたしにかけていうには、『ゼウスの裔(すえ)にしてラエルテスが一子(いっし)智謀に富めるオデュッセウスよ、なんたる無茶をする男か、これよりも更に大それたことを目論(もくろ)むことはできまいに。 どうしてまたおぬしは、冥府に降(くだ)ろうなどという気を起したのだ、ここはなんの感覚もない骸(むくろ)、果敢(はか)なくなった人間の幻にすぎぬ者たちの住む場所であるのに』。(11-462-476) (11-477)(11-478)(11-479)(11-480)(11-481)(11-482)(11-483) (11-484)(11-485)(11-486) こういう彼にわたしが答えていうには、『ペレウスが一子、アカイア勢にあっても他に比類なき勇士アキレスよ、わたしはテイレシアスの託宣を求めてここへ来たのだ、いかにすれば岩根こごしきイタケへ帰国できるのか、なにかその方策を授けてくれはせぬかと思ってのことであった。わたしはまだ、アカイアの国の近くにも行っておらぬし、わが領地の土も踏んでおらず、ずっとこれまで苦難に悩まされ続けている。 おぬしの方はしかし、アキレスよ、これまでもおぬしより仕合せな者はいなかったし、今後もそれは渝(か)わるまい。以前おぬしが世に在った時は、われらアルゴス勢はみな、おぬしを神同様にあがめていたし、今はまたこの冥府に在って、おぬしは死者の間に君臨し権勢を誇っているではないか。さすればアキレスよ、死んだとて決して歎くことはないぞ』。(11-477-486) (11-487)(11-488)(11-489)(11-490)(11-491)(11-492)(11-493) (11-494)(11-495)(11-496)(11-497)(11-498)(11-499)(11-500) (11-501)(11-502)(11-503) こうわたしがいうと、彼は直ぐに答えて、『勇名高きオデュッセウスよ、わたしの死に気休(きやす)めをいうのはやめてくれ。世を去った死人全員の王となって君臨するよりも、むしろ地上に在って、どこかの、土地の割当ても受けられず、資産も乏しい男にでも傭(やと)われて仕えたい気持だ。 それよりもわたしの倅の消息をなにか聞かせてくれぬか、わたしの後を追って出陣し、一軍の将として働いたのか、そうではないのか、またわたしの優れた父ペレウスについて、なにか知っていることがあったら話してくれ。多数のミュルミドネス人の間において、父は今も渝(か)わず王たる栄位を保っておられるか、それともヘラスならびにプティエ(プティア)の民どもは、老齢に手足も弱られたのをよいことに、父を辱めているのではないか。 それというのも、わたしはもはや天日の下(もと)、かつて国広きトロイに在って、アルゴス勢を衛りつつ、敵の精鋭を屠った折のままの姿で、父の力となることはできぬからだ。一時(いっとき)でもよい、あの折の姿に戻って、父の屋敷へゆくことができたら、どんなにかよかろう。その時には、父を痛めつけ栄位にあるのを妨げんとする輩に、わたしの力と無敵の腕の恐ろしさを、思い知らせてやるものを』。(11-487-503) 第十一歌(上P301)アキレスの息子 (11-504)(11-505)(11-506)(11-507)(11-508)(11-509)(11-510) (11-511)(11-512)(11-513)(11-514)(11-515)(11-516)(11-517) (11-518)(11-519)(11-520)(11-521)(11-522)(11-523)(11-524) (11-525)(11-526)(11-527)(11-528)(11-529)(11-530)(11-531) (11-532)(11-533)(11-534)(11-535)(11-536)(11-537) こういったが、わたしはそれに答えて、『おぬしの立派な父御、ペレウスについては、まったくの話、何も聞いておらぬが、おぬしの愛(いと)しい息子(むすこ)、ネオプトレモスについては、おぬしの望み通り一切(いっさい)の真実をお話しよう。彼をスキュロスから均斉(きんせい)とれたうつろな船に乗せて、脛(すね)当見事なアカイア勢の許(もと)へ連れて行ったのはこのわたしだからだ。 トロイ城下(トロイ国の首都イリオンのこと)で評議する時はいつも、彼が一番に発言し、そのいうところは的を外(はず)れなかった。彼に勝るのは、僅(わず)かに神の如きネストルとわたしの二人だけであった。しかし、われらアカイア勢が、トロイ平原において戦う折には、多数の味方が群がる場所には決して留まることなく、その力は何者にも譲らぬ勢いを示して、遥か前線に突進して行った。 恐るべき死闘の間に、彼の討ち取った敵は多数に上る。非の打ちどころなき御子息が、アルゴス勢のために討ち果した敵の、その悉(ことごと)くの名を挙げて語るわけにはゆかぬが、彼が刃(やいば)にかけたテレポスの倅(せがれ)エウリュピュロスは、いかに優れた勇士であったことか。 彼の周りでは、その部下であるケテイオイ人も多数討たれたが、これもみな一人の女が受け取った贈物のせいであった。彼こそはわたしの見た限りでは、勇士メムノンに次いで、容姿最も優れた武将であった。 第十一歌(上P302) ところでわれらアルゴス勢の中でもよりぬきの精鋭が、エペイオスの製作した木馬に乗り込み、その頑丈な潜伏所(どころ)を開くも閉じるも、わたしの裁量に任されていたいた時のことであるが、他のダナオイ勢の将領(しょうりょう)たちや参謀たちは、いずれも涙を拭(ぬぐ)ったり脚(あし)が震えたりしておったのに、ひとり御子息(ごしそく)のみは、その艶(つや)やかな肌(はだ)が青ざめたり、頬(ほお)の涙を拭うのを、わたしは一度も目にしなかったのだ。 彼は木馬から出撃させてくれと、幾度もわたしに頼み、太刀(たち)の柄(つか)と青銅の穂先も重い槍を握り、トロイ勢に目に物見せんと意気込んでいた。しかしわれらが遂に、険しく聳え立つプリアモスの城を陥した時、捕獲品の分け前と、その軍功に報いる厚い褒賞を手にして、恙(つつがな)く船で発(た)って行った。戦(いく)さの神アレスが荒れ狂う乱戦においてはあり勝ちな、鋭利な槍(やり)に当ることも、白兵戦で刺されることも彼は免れたのだ』。(11-504-537) (11-538)(11-539)(11-540)(11-541)(11-542)(11-543)(11-544) (11-545)(11-546)(11-547)(11-548)(11-549)(11-550)(11-551) (11-552)(11-553)(11-554)(11-555)(11-556)(11-557)(11-558) (11-559)(11-560)(11-561)(11-562) わたしがこういうと、アイアコスの末裔、駿足(しゅんそく)のアキレスの霊は、己れの息子が抜群の誉れに輝いたとの、わたしの言葉を聞いて嬉しげに、アスポデロスに蔽(おお)われた野を、大股(おおまた)に歩み去った。 (八)無言のアイアスの霊 他の亡者たちの霊も、悲しみの面持(おもも)ちでその場に立ち、それぞれが心にかかる事柄(ことがら)について訊(たず)ねてきた。ひとりテラモンの子、アイアスの霊のみは、他から離れて佇(たたず)んでいた。かつて軍船(ぐんせん)の傍(かたわ)らで、アキレスの武具をめぐる判定を競い合って、わたしが勝ったのを今も憤(いきどお)っているのであった。 (上P303) その武具を武功の賞に賭けられたのは、アキレスの母なる尊貴の女神(ティティス)で、判者はトロイ人の子らとパラス・アテネとであった。ああ、わたしはこのような褒賞を争って勝つのではなかった、あの武具ゆえに、あれほどの人物が地下に眠る仕儀となってしまったのだから。あのアイアスこそは、その容姿といい、その働きといい、無敵のアキレスを措(お)いては、ダナオイ軍中他に並ぶ者のない勇士であったのに。 そこでわたしは、彼に優しく語りかけていうには、『無双の勇士テラモンの子アイアスよ、おぬしは死後もまお、かの呪うべき武具ゆえの怒りを忘れようとはしてくれぬのか。あの武具は神々が、アルゴス勢に禍いたれと設けられたものに相違ない。おぬしの死によって、アルゴス勢は頼むべき砦を失ったも同然だからな。われらアカイア勢はそなたの死を、ペレウスの子アキレスのそれに劣らず悲しんでやむ時もないのだ。 しかしこれは他の誰の罪でもない、ゼウスは勇猛ダナオイ人の軍勢に、怖るべき憎悪の念を抱かれ、おぬしにこのような運命を降されたのだ。さあここへ来て、わたしのいうところ、語るところを聞いてくれ、怒りを制し昂ぶる気持を抑えてくれ』。(11-538-562) (11-563)(11-564)(11-565)(11-566)(11-567)(11-568)(11-569) (11-570)(11-571)(11-572)(11-573)(11-574)(11-575) こういったのだが、彼はそれに一言(ひとこと)も答えず、他の亡者たちの後を追って、暗黒の世界へ帰って行った。とはいえ、この時あるいは、怒りつつも彼がわたしに語りかけ、またはわたしが彼と話すことも、あるいはできたのかも知れなかったのだが、わたしの胸の内にはそれよりも、他の死者たちの霊に会いたいという気持が強く動いたのであった。 (上P304) (九)ミノス いかにもこの時わたしは、ゼウスの優れた息子ミノスが黄金の杖を持って坐り、死者に裁きを下す姿を見たのだ。亡者たちは門口(かどぐち)広き冥王の館の中で、ミノス王を囲んで、あるいは坐りあるいは立って、その裁決を請うていた。 (十)巨人オリオン ミノスの次にわたしの目は、巨人オリオンの姿にとまった−−−アスポデロスに蔽(おお)われた野を、総(すべ)て青銅作りの不壊(ふえ)の棍棒を握って、人気なき山中で、自ら屠った野獣どもを、駆り集めている姿であった。(11-563-575) (11-576)(11-577)(11-578)(11-579)(11-580)(11-581)(11-582) (11-583)(11-584)(11-585)(11-586)(11-587)(11-588)(11-589) (11-590)(11-591)(11-592) (十一)ティテュオス また名も高き大地のガイアの息子、ティテュオスが地上に横たわる姿も見た。九プレトロン(約270メートル)にわたって、長々と横たわっている。その両側には二羽の禿鷹(はげたか)がとまり、臓腑(ぞうふ)の中まで嘴(くちばし)を突込んで、肝臓を食い破っているが、彼は己れの手でこれを防ぐことができぬ。ゼウスの高貴な妃レトが、風光(ふうこう)明媚(めいび)なパノペウスを過ぎて、ピュト(デルポイ)に向われる折、彼女に狼藉を働いた報いであった。 (十二)タンタロス また、耐え難い責苦を受けつつ、水中に佇(たたず)むタンタロスの姿も見た。水は頸(くび)の辺(あた)りに近付き、咽喉(のど)が渇いて飲まんと焦るが、水を捕えて飲むことができぬ。必死に飲もうとして老人が身をかがめるたびに、水は吸い込まれたように消え、足下(そっか)には黒い土が現われる−−−神霊が悉(ことごと)く干し涸(か)らしてしまわれるのだ。また樹葉茂り高く聳(そび)え立つ、さまざまの果樹が頭上から果実を垂らしている−−−梨(なし)に石榴(ざくろ)の樹(き)、その実も艶(つや)やかな林檎(りんご)の樹、甘い無花果(いちじく)の樹や茂り栄えるオリーブの樹。だが老人が手を差し伸べてその実を取ろうとするたびに、風が小暗い雲間めがけてそれを吹きとばしてしまう。(11-576-592) (下P305) (11-593)(11-594)(11-595)(11-596)(11-597)(11-598)(11-599) (11-600)(11-601)(11-602)(11-603)(11-604)(11-605)(11-606) (11-607)(11-608)(11-609)(11-610)(11-611)(11-612)(11-613) (11-614)(11-615)(11-616)(11-617)(11-618)(11-619)(11-620) (11-621)(11-622)(11-623)(11-624)(11-625)(11-626) (十三)シシュポス また巨大な岩を両の手で押し上げつつ、無残な責苦に遭っているシシュポスの姿も見た。岩に手をかけ足を踏ん張って、岩を小山の頂上めがけて押し上げてゆく。しかし漸(ようや)くにして頂上を越えんとする時、重みが岩を押し戻し、無情の岩は再び平地へ転げ落ちる。彼は力をふりしぼって再び岩を押すが、その全身から汗が流れ落ち、頭の辺りから砂埃(すなぼこり)が舞い上る。 第十一歌(P306)冥府にて (十四)ヘラクレス 次にわたしは豪勇ヘラクレスの姿を見たが、これは彼の幻影に過ぎず、当の身は不死なる神々の間に在って宴遊を楽しみ、大神ゼウスと黄金のサンダルを召すヘレの御娘、踝(くるぶし)美わしきヘベを妻に持つ。ヘラクレスの周りでは亡者たちが、さながら脅えてこなたかなたへ飛び交う鳥の声にも似た叫びをあげている。 彼はぬばたまの夜の如き暗鬱な面持ちで、蔽(おお)いをはらった弓を握り、弦には矢を番(つが)えていつなりと放つ見構えで、形相凄まじくあたりを見廻している。胸の周りにかけわたした、剣を吊るす黄金の帯は見るも恐ろしく、これには見事な細工が施され、熊に野猪、また眼光爛々たる獅子の姿、さらにまた合戦、戦闘、殺戮、殺人の光景を写している。技を尽してこの剣帯の意匠を仕上げた職人が、また今後再び作らねばよいにと、祈らずにはおれぬほどの凄まじい光景であった。 さて彼は、わたしに目をとめると、直ぐにわたしと判り、泣きながらわたしに翼ある言葉をかけていうには、『ゼウスの裔(すえ)にしてラエルテスが一子、知略に富むオデュッセウスよ、そなたは気の毒なお人じゃ。そなたもまた、かつてわしがいまだ陽光を浴びて世に在った時、背負っていたと同じ悲運を曳きずって生きているのだな。わしは名に負うクロノスの子、ゼウスの息子として生まれながら、際限もない苦難に悩まされ続けたのだ。 わしより遥かに劣る男に仕えさせられ、この男から数々の難業を課せられた。かつてこの場所へも、冥府の犬を連れ帰るべく、差し向けられたことがあった。これよりも苦しい難業は、彼も思いつかなかったわけだ。わしは見事にその犬を、冥王の館から曳いて地上へ帰ったのだが、この時はヘルメスと、眼光輝くアテネとが、わたしに付き添ってくださった』。(11-593-626) (11-627)(11-628)(11-629)(11-630)(11-631)(11-632)(11-633) (11-634)(11-635)(11-636)(11-637)(11-638)(11-639)(11-640) こういうと、彼は冥王の館へ帰って行ったが、わたしは、過ぐる日に果てた英雄たちの中の誰かが、また現れるかも知れぬと思い、その場でじっと待っていた。こうして何事もなくば、わたしの望んだ往昔の勇士たち−−−例(たと)えばいずれも神々の誉れ高き子なる、テセウスやペイリトオスにも会えたものを。 ところがかくなる前に無数の亡者の群が、奇怪な叫びをあげながらその場に集(つど)ってきたので、たちまちわたしは蒼白な恐怖に襲われた。冥府の女王ペルセポネイアが冥王の館の中から、恐るべき怪物、ゴルゴの首でも差し向けてくるのではないかという気がしたのだ。 そこで早速(さっそく)船へ戻り部下たちに、乗船して艫綱(ともづな)を解けと命ずると、直ぐさま一同は船に乗り込み漕座(こぎざ)についた。船は水流の波に乗ってオケアノスを下り、初めのうちは櫂(かい)を用いたが、後には順風が船を運んだ」。(11-627-640)第11章(完) |
| 次へ |
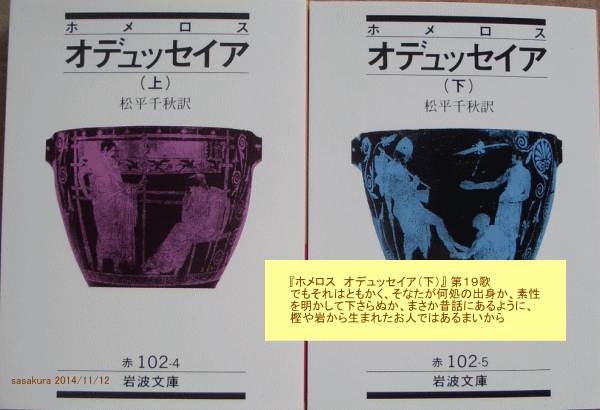 |
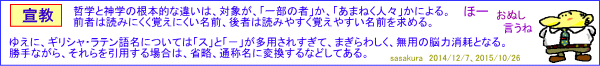 |
| 読後感想を述べたり、独自解釈のための引用にしては、常識を超えた量でになっているかも知れない。それは全文ではないし、翻訳者の注釈や付加資料は転載してはいないのだから、ぜひ本を手に入れて読んでいただきたい。あなたが若ければ若いほど、その知的資産は隠し味となって、あなたの人生に長く作用するだろう。この「オデッセイア」は、女性の視点で書かれていると信じるので、女性の方々の目に止まるようにと祈る。 |
 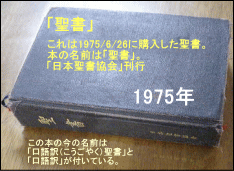 |
2015/4/8 オリジナル教会(初代代表) 笹倉正義
正式名称:(笹倉宗)聖母マリヤ福音教会