 Mariaが「マリヤ」は
Mariaが「マリヤ」は| このサイトでは口語訳聖書準拠の「マリヤ」を採用しています。 「マリア」は黙読から、「マリヤ」は音読に由来しています。 |
| TV6CH相棒「わたしのダイヤはどこ?」 |
| 赤ちゃんをママは「ダイヤ」と呼んだ。その子の名は「大愛(だいあ)」 |
| (1)「マリヤ」は ドイツ語聖書には、「der Jungfrau war Maria」と書いてあり、「乙女マリア」と読める。なぜ、文語体聖書はこれを「マリア」ではなく、「マリヤ」と日本語訳したのだろうか。それが長年の疑問だった。その疑問が、こう考えることで解けた。 マスコミの外来語の日本語表記には、ダビンチはダ・ヴィンチ、バイオリンはヴァイオリンなどのように、ヴァとかヴォとかが多用される。これらは本来の日本語の発音には馴染まず、濁って汚い音である。真面目に発音しようとすると、口元や顔がゆがむ。だから、結局のところ「ダ・ヴィンチ」は、「ダビンチ」と発音している。そもそも日本語には発音記号はない。 戦後教育を勝ち抜いたマスコミの編集者たちの多くは、目学門による知識集積脳である。目で物を読み知識として脳に蓄えることが得意である。だから、目に映る文字にこだわり、発音のことには考えが及ばない。「ダビンチ」よりも「ダ・ヴィンチ」の方が知的に映るのだ。 ひるがえって、 「Maria」を「マリヤ」と日本語表記した人々は、それが教会で読まれることを意識していたと考えられる。なぜなら、「マリア」は意外と発音しにくい。その点、「マリヤ」は発音しやすいし、自然な発音を聞くと「マリア」と聞こえるのである。「知」と「愛」。文語体訳聖書とそれを継承した口語訳聖書は、「愛」なのである。愛は自己主張しないものである。 |
 |
| (2)イタリヤ語の場合 イタリヤ語のアルファベット(alfabeto)は、 A B C D E F G H I L M N O P Q R S T U V Z の21文字である。 J K W X Y は外来語の表記に使われる。 イタリヤ語のMariaは、ネイティブ・スピーカーでも「マリヤ」と言っている。「マリーア」でも「マリア」でもない。「ria」を「リ・ア」ではなく「リ・ヤ」と発音しているのには、そもそもYを表記する習慣がないからであり、特別な意味はない。彼らの発音はMariyaであり、日本人にとってもこの方が自然な発声ができる。 イタリヤ イタリヤ語でイタリヤはItaliaと書く。黙読ではイタリアと読めるが、発音するとイタリヤになってしまうと思う。その方が言い易いからであり、実際イタリヤ人のネイティブの発音もイタリヤと(言っているように)聞こえる。Italiaというイタリヤ語の表記は、彼らがYを使わない習慣から、Italiyaとは書かずにItaliaとなっているのである。多分、Yがあると美しくないのだ。 |
| (3)文豪の場合 ちくま文庫 中島敦全集2 1993年3月24日第一刷発行 筑摩書房 中島敦(あつし) 環礁 −−−ミクロネシヤ巡島記抄−−− マリヤン マリヤンというのは、私の良く知っている一人の島民女の名前である。マリヤンとはマリヤのことだ。聖母マリヤのマリヤである。パラオ地方の島民は、凡て発音が鼻にかかるので、マリヤンと聞えるのだ。マリヤンの年が幾つだか、私は知らない。別に遠慮した訳ではなかったが、つい、聞いたことがないのである。とにかく三十に間があることだけは確かだ。 マリヤンの容貌が、島民の眼から見て美しいかどうか、之も私は知らない。醜いことだけはあるまいと思う。少しも日本がかった所が無く、又西洋がかった所も無い(南洋でちょっと顔立が整っていると思われるのは大抵どちらかの血が混っているものだ)純然たるミクロネシヤ・カナカの典型的な顔だが、私はそれを大変立派だと思う。人種としての制限は仕方が無いが、その制限の中で考えれば、実にのびのびと屈託の無い豊かな顔だと思う。しかし、マリヤン自身は、自分のカナカ的な容貌を多少恥ずかしいと考えているようである。というのは、後に述べるように、彼女は極めてインテリであって、頭脳の内容は殆どカナカではなくなっているからだ。それにもう一つ、マリヤンの住んでいるコロール(南洋群島の文化の中心地だ)の町では、島民等の間にあっても、文明的な美の標準が巾をきかせているからである。 |
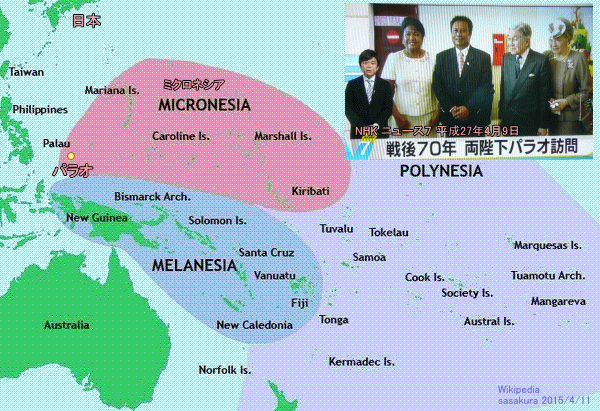 |
| 戻る |
| 聖母マリヤ |
| ページ制作者: 「笹倉キリスト教会」 笹倉正義 2012/5/3、2012/5/13、2013/1/28(イタリヤ語表記のマリヤ、文豪の場合)、2013/1/29(Mariya)、 2013/2/1(イタリヤ)、2013/2/16(題名:なぜマリヤなの?を変更)、2013/3/3(同左) 2015/4/11、2015/11/6(ロゴの変更) 2024/3/22(レイアウト変更)、9/4、11/4 |
| 引用聖句:日本聖書協会 わたしたちの聖書 |